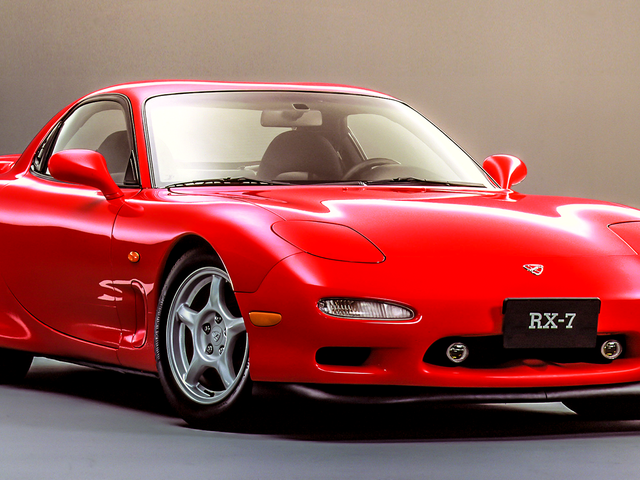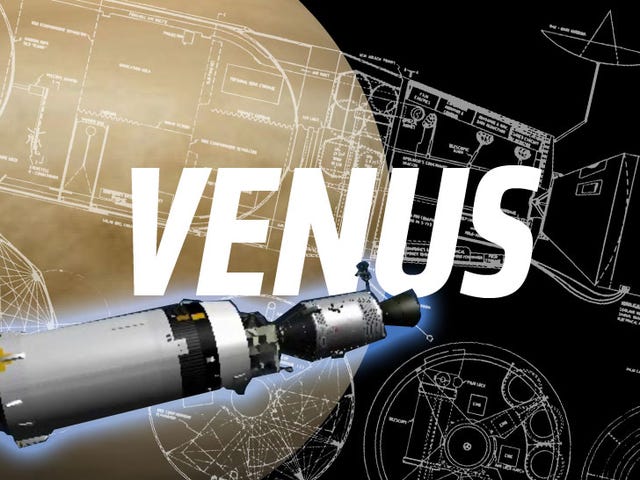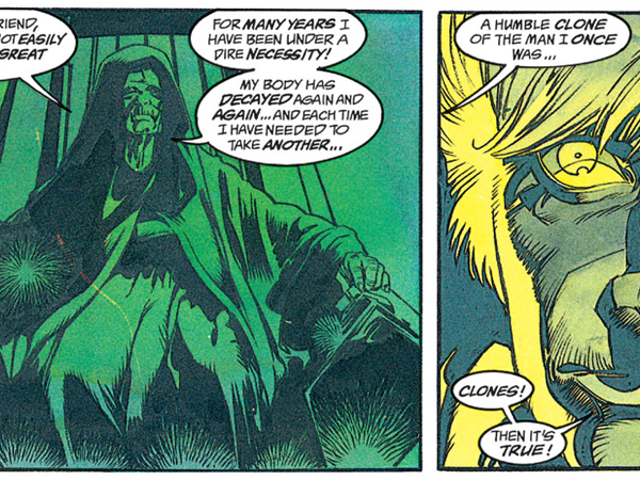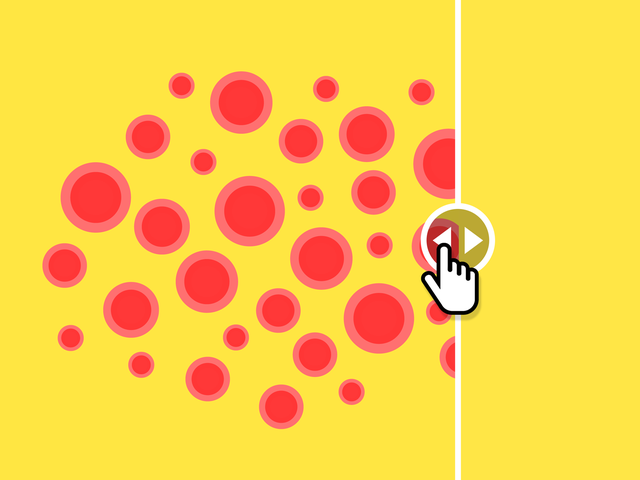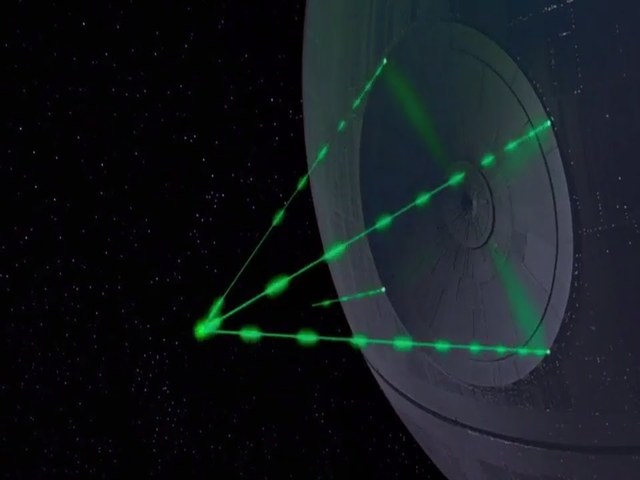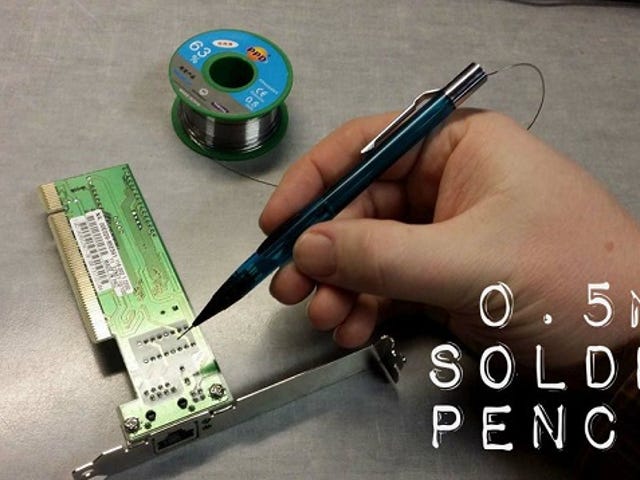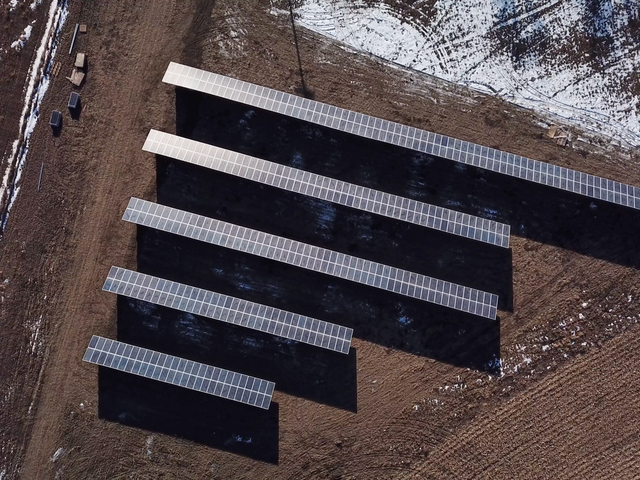Kinds Of Kindness レビュー: ヨルゴス・ランティモスの最高傑作

ヨルゴス・ランティモス監督の新作アンソロジー映画「三部作寓話」 Kinds Of Kindnessの原題には、破壊的なスリルがあった。 映画を「そして」と名付けることは、SEO やマーケティングの常識のほとんどすべてに反する。そのアイデア自体が、スタジオの重役やあらゆる検索エンジンに中指を立てるような厚かましい行為のように思えた(たとえ、上映時間を探している人にとっては少々悪夢だったとしても)。
関連性のあるコンテンツ
しかし、 『Kinds Of Kindness 』を観ると、ランティモスは『女王陛下の お気に入り』と『Poor Things』 以外のほぼすべての作品で共同執筆しているエフティミス・フィリッポウと再タッグを組んでいるが、その改題の賢明さが明らかになり、元のタイトルの反抗的な魅力はすぐに忘れ去られる。ランティモスの映画を見たことがあれば、この新しいタイトルに明らかに皮肉な意味合いがあることに気づくだろう。彼の無味乾燥な世界には思いやりや無私無欲が常に欠けているからだ。しかし、ランティモスとフィリッポウの他の共同作品以上に、『Kinds Of Kindness』は二人の心理的ディストピア(アイデンティティがシュールなほど歪んでおり、感情が不安になるほど冷たい)への強烈な冷徹な没入でもあり、そのため、人間関係を強調するこのタイトルは完璧にふさわしいように感じられる。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
Kinds Of Kindnessの 3 つの章は、タイトルによって最も明確に結びついています。「RMF の死」、「RMF は飛ぶ」、「RMF はサンドイッチを食べる」は、いずれも実際のキャラクターというよりはストーリーの軸に近い、寡黙で名も知れない男性について言及しています。各エピソードには、ジェシー・プレモンス、エマ・ストーン、ウィレム・デフォー、マーガレット・クアリー、ホン・チャウ、マモドゥ・アシー、ジョー・アルウィン (ハンター・シェーファーは最終章のみに登場) といった、緊密な俳優陣も共通しています。
しかし、その核心において、映画の 3 つの物語を最も結びつけているのは、選択とコントロール、服従と服従の共通の探求です。この映画は、5 つの愛の言語(インターネットで有名な自己啓発の愛情分類法) に対する病人の解釈と似ていますが、ここでは、自発的な「奉仕行為」が、感情的な暴君のサディスティックな要求を満たすためになされる犠牲として再考されています。
たとえば、あるストーリーでは、プレモンスは、大人になってからの人生のすべての決定を上司のレイモンド(デフォーが冷徹に完璧に演じている)に決められている従順なビジネスマン、ロバートを演じている。ロバートは、ある特に衝撃的な指示についに反発し、自分の人生から冷たく締め出され、レイモンドの気まぐれな好意を取り戻そうと必死で狂った試みをする。別のストーリーでは、脚本が逆転し、今度はプレモンスが、海で遭難して戻ってきた海洋生物学者の妻(ストーン)に、サイコパス的な献身のテストを求める。プレモンス演じる疑り深いダニエルの目には、妻は偽者のように見えた。
これら 2 つの作品は、ぞっとするような光景と感情的な残酷さにより、観客に吐き気を催すような挑戦を突きつけているが、映画の残酷さの表現には蓄積された性質がある。Kinds Of Kindnessの最終章では、こうした愛情の抑制と感情の独裁がすべて、論理的な終着点に至っている。「RMF Eats A Sandwich」は、ストーン演じるエミリーが所属するカルト集団を中心に展開する。このカルト集団は、一見穏やかそうなデフォーとチャウが率いている。このエピソードでは、前の 2 つの物語を軽くしていた不条理なユーモアが苦い皮肉に変わり、残酷なシーンは退席を誘うほどに増え (特にストーンと犬が登場するシーン)、閉所恐怖症は窒息しそうなほどにまで達する。『Kinds Of Kindness』の残りの部分では、心理的なBDSMがスクリーン上で展開されるが、この時点では、この映画を観るという体験自体が、服従の罰のような行為のように感じられるかもしれない。実際、このひどく醜い結末にたどり着く頃には、確固たるランティモスファンでさえ、サウンドトラックで使用されている、恐怖に満ちたオペラ風の「NO」としか歌っていない合唱団の歌声に、自分の考えが言葉で表現されているのを聞き取るかもしれない。
エピソードごとに暗さが増していくことが、主に『Kinds Of Kindness』の三部作構造を正当化している。均等なタイミングで展開されるこれらの物語は、それぞれ単独での方がうまくいくとは思えない。物語は互いに積み重なって複雑化し、いわゆる「寓話」の説明にふさわしい、心に残るものに溶け込んでいく。単一の包括的なプロットを描く必要性を排除し、代わりにテーマ的に関連のある3つの単発作品を選ぶことで、ランティモスとフィリッポウは、これまでで最も冷静な視線で彼らの鏡の中の人間関係を見つめる姿を観客に提供している。さらに、各章を通して俳優たちの役割がシーソーのように入れ替わることで、全体像に心地よい完成度が与えられている。すべての演技が互いを引き立て合い、最も緊迫した最終章でのストーンの中心的な存在が、最初の2章でのプレモンスのショーを盗むような演技とバランスをとっている。その効果に磨きをかけているのは、体を舐める行為、奇妙に共通するイニシャル、予知夢など、映画全体に響き渡る不気味な反響である。
一見すると、『カインド・オブ・カインドネス』にはランティモス作品に最も関連した表面的な要素がいくつか欠けているように思えるかもしれない。例えば、撮影監督のロビー・ライアンは、『プア・シングス』では多用していた魚眼レンズを、本作ではほとんど使用していない。しかし、より深いところでは、本作はランティモスの最高傑作のように感じられる。監督は、より親しみやすい映画で他の脚本家たちと数年間コラボレーションした後、再びフィリッポウとタッグを組み、これまでにない大胆で賛否両論を呼ぶ独特のスタイルを貫いている。『プア・シングス』でハッピーエンドに短期間進出した後、『カインド・オブ・カインドネス』では、ランティモスは「楽しめる」と言うのがひねくれた感じの映画に戻っている。つまり、ギリシャの奇人が帰ってきたということだ。