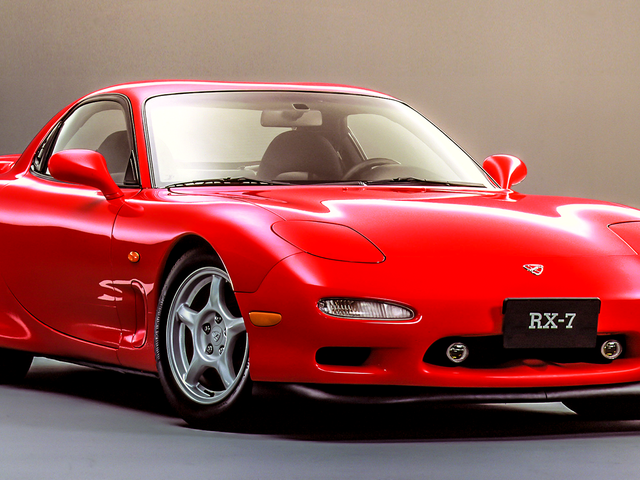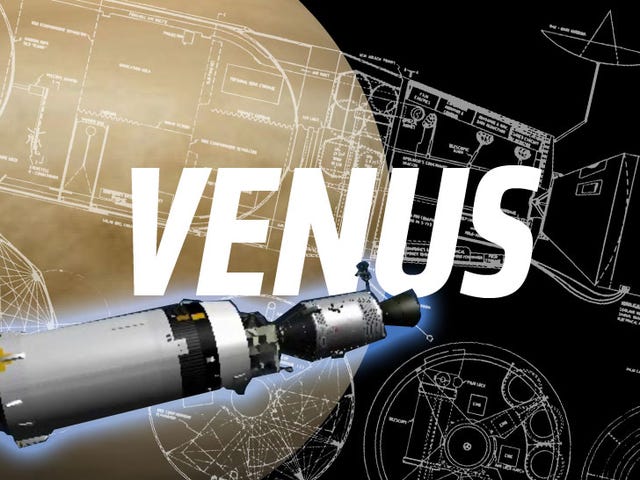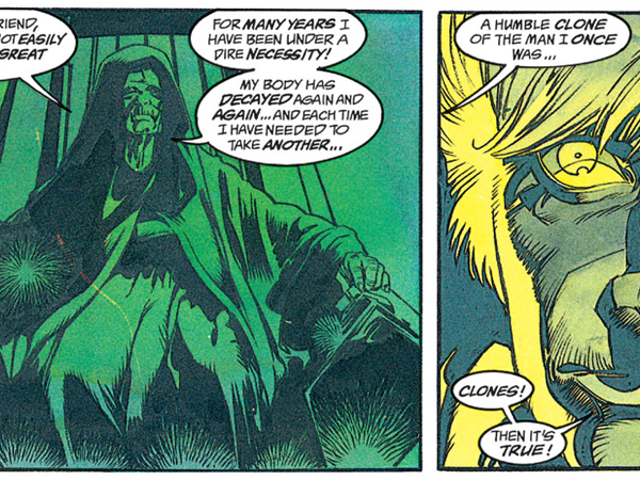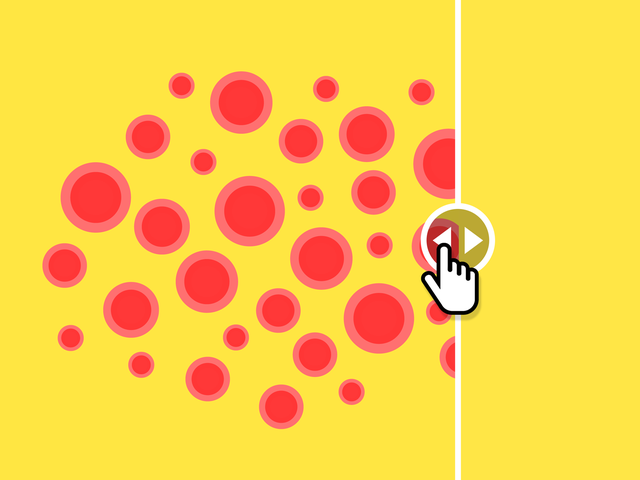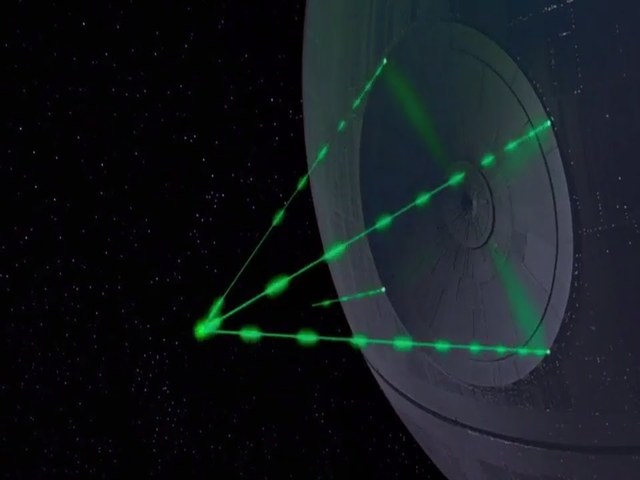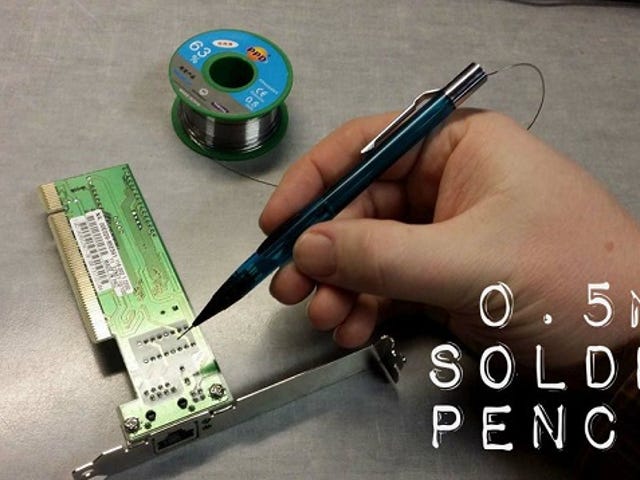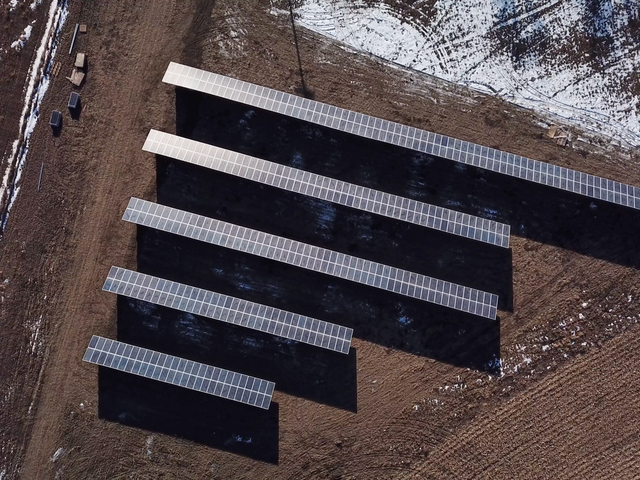「Back To Black」をスキップして「Amy」を観よう

エイミー・ワインハウスのファンは、彼女の伝記映画が作られるというニュースをあまり喜んでいなかった。2011年に27歳でこの歌手が悲劇的な死を遂げて以来、彼女のファンたちは、質の疑わしい死後のアルバムから幸いにもキャンセルされたホログラムツアーまで、彼女の名の下に行われたあらゆる種類の安っぽくて搾取的な金儲けを目撃することに慣れてしまっていた。サム・テイラー=ジョンソンが監督した伝記ドラマ『バック・トゥ・ブラック』は、このプロジェクト全体が歴史の隠蔽であり、ワインハウス自身を記念するよりもレコードの売り上げに関心があるのではないかという懸念を否定するのにはあまり役立たなかった。もちろんこの映画はひどいもので、彼女の短い人生をいい加減であからさまに磨き上げた要約であり、彼女の創作プロセスと依存症の苦しみの両方にはまったく関心がないように見える。『バック・トゥ・ブラック』は、歴史をあからさまに変えていないときでも、ワインハウスの苦難に関する広範囲に記録された真実を臆病に避けており、映画製作者たちはワインハウスが誰であるかさえ知っていたのだろうかと思わずにはいられないほどだ。もっとはっきり言えば、9年前にこの映画よりも優れたオスカー受賞ドキュメンタリーが あるのに、なぜこの映画が存在するのかという疑問を避けることはできない。
関連性のあるコンテンツ
アシフ・カパディアのエイミーは、バック・トゥ・ブラックにはないすべてを備えている。思いやりがあり、巧みに作られ、親密で、中心となる主題の生、死、そして悩みに心から関心を持っている。エイミーは、ワインハウスの幼少期と音楽業界での初期の頃の本当に美しいアーカイブ映像を活用し、友人、家族、ファンがナレーションで思い出を語るなか、彼女に焦点を当てている。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
『エイミー』は、このジャンルでよくある、生涯を描いた典型的なミュージシャンドキュメンタリーのように感じられます。彼女の幼少期の愛らしいビデオ、有名になるまでの物語、痛々しいほど詳細に描かれた没落、そして彼女の最高の曲の素晴らしい映像がたくさんあります。しかし、カパディアの作品が際立っているのは、その細部です。それは、ワインハウスの日記を覗き見るようなもので、それに伴う率直さと辛辣さが、彼女の短いキャリアに対する世界の反応と関連しています。
エイミーは、ワインハウスの波乱に満ちた人生をひるむことなく描きながらも、観客を驚かせるために心を犠牲にしないという、細い綱渡りのような映画だ。彼女の並外れた才能は、子供の頃にマリリン・モンロー風の「ハッピーバースデー」を歌うときに発揮されるが、最も痩せていてヘロイン中毒に苦しんでいたときの自撮り写真でもよくわかる。エイミーのユーモアや自虐的な魅力が表れるたびに、彼女のトラウマの影響を示す対照的な瞬間がある。絶頂期の、今では伝説となっている彼女のパフォーマンスを見ると、心が和むと同時に動揺する。彼女の才能が最高潮に達した瞬間は、次に何が起こるかを知らずして楽しむことはできない。カパディアは、何千もの観客が怒りのブーイングを送る中、ワインハウスがステージ上でかろうじて立っている様子を映した手ぶれの激しい映像をためらわずに映している。
映画「エイミー」で最も胸が張り裂けるようなシーンは、彼女の絶頂期のひとつである、ワインハウスがグラミー賞を5部門で受賞し、憧れのトニー・ベネットが栄誉のスピーチをする中、ロンドンから衛星放送で賞を受け取った夜に訪れる。この機会のためにシラフで過ごし、ロサンゼルスでのイベントに参加できなかったワインハウスは、上機嫌で、バンドのメンバーと冗談を言い合ったり、ベネットが自分の名前を読み上げるのを見て心から畏敬の念を抱いたりしている。最優秀レコード賞を受賞した後、故郷の友人や家族は歓喜する。その後、ナレーションで、友人の一人が、この高揚した瞬間にエイミーが「ドラッグがないとこんなにつまらないもの」と言ったことを思い出すのが聞こえる。薬物中毒の虜になり、それがワインハウスの人生を一変させたため、彼女はプロとしての絶頂期を楽しむことができなかった。『バック・トゥ・ブラック』には、このセリフは存在しない。それだけでも十分侮辱的だが、映画ではワインハウスのジョークやベネットに対するファンガール的な尊敬もすべて削除されている。テイラー=ジョンソンの手の中で、彼女は単なる操り人形となり、伝記映画のような動きをし、予想通りのリズムに別のミュージカルナンバーを付け加えるだけである。
『バック・トゥ・ブラック』はエイミーの人生の影に隠れているだけでなく、ファンにとって長らく悪役だった父ミッチによるメディア操作の影にも隠れている。ミッチはスポットライトが大好きで、エイミーの人生の「真実の物語」と彼が考えるものを語る伝記映画に熱心だった。どうやら、それはエイミーのキャリアを、父が聖人のような導き手であるというバージョンで描くことを意味するようだ。エディ・マーサン(本当にひどい白髪染め)が演じるミッチは、常に正しく、かわいそうなエイミーをいつも気遣い、仕事や個人的なアドバイスをくれる頼れる人物だ。テイラー=ジョンソンは少なくともミッチを文字通りの天使にはしない程度には抑制しているが、エイミーの人生のこのバージョン、つまり彼を彼女の存在そのものの道徳的中心と位置づけるバージョンは、本当に『バック・トゥ・ブラック』が作られた理由を思い起こさせる。これはすべてミッチに関するものであり、エイミーに関するものではない。
もしエイミーが、ミッチを利己的でスポットライトを浴びたがり、明らかに演技ができない娘に演技を強要し続ける人物としてしっかりと描いていなかったら、 『バック・トゥ・ブラック』は存在していただろうか?そんなことはないだろう。ミッチがエイミーに、リハビリに行く必要はないと言ったのは、彼女がその経験について愛される曲を書いたからだと誰もが知っているが、ドキュメンタリーの中で、皆の反対にもかかわらず、ミッチがあの時は介入する必要はなかったと言い続けたことは、いまだに侮辱されているように感じられる。ドキュメンタリーの後半で、彼はセントルシアにカメラクルーを連れて行くが、そこでエイミーは実際にリハビリに行った後に回復しており、父親が自分を見世物のように扱うことに彼女は本当に悲しんでいるように見える。
エイミーから罪悪感の臭いを漂わせながら出てくるのは、彼だけではありません。彼女の悪名高い元夫ブレイク・フィールダー=シヴィルは、彼女にハードドラッグを教えたのは自分だと驚くほど率直に認めています。伝記映画ではこれが完全に変わり、奇妙なことに彼は自分の結婚生活において受動的な傍観者になっています(筋肉隆々のジャック・オコンネルが演じている彼は、世界で最も健康的なクラック中毒者でもあります)。何年もタブロイド紙の話題をさらった後、2011年にベオグラードで明らかに酔ってぐったりした姿でステージに送り出されたエイミーが映し出され、私たちが問うことができるのは「一体なぜマネージャーのレイ・コスバートはこんなことを許したのか?」ということだけです。誰かがこれほど世界レベルで失敗するには、かなりの責任を負わなければなりません。
ミッチ・ワインハウスは、エイミーが娘を「あまり良い印象で描いていない」と主張した。マスコミによって喜劇のように扱われた不穏な没落を世界に再び経験させることに彼が不安を感じるのは理解できるが、彼は正直さと軽蔑を混同している(エイミーの友人や同僚の証言がすべてそれを裏付けているにもかかわらず、彼が自分の描かれ方に腹を立てているのもおそらくそのためだろう)。確かにエイミーは見るのがつらいときもあるが、そうあるべきだ。摂食障害と精神疾患を抱えた中毒者がステージに連れ出され、よろめき、ブーイングを浴び、観客が彼女をさらに深い穴に落ち込ませるのを見たことを思い出すのは恥ずかしいことだ。 (『バック・トゥ・ブラック』ではこうしたパフォーマンスは一切描かれていないため、彼女がわずか数年で公の場で悲劇に陥ったことを十分に伝えるのは難しい。)フランキー・ボイルやジョージ・ロペスなどのコメディアンがワインハウスを嘲笑する映像、特にロペスは彼女がグラミー賞候補になったと発表する際にそうしたが、今にして思えば痛烈に印象に残る。当時はみんな笑ったのではないだろうか? ワインハウスの危険なほど痩せ細り、あざと泥だらけの体が、何十人ものカメラマンにカムデンで尾行される映像が挿入されると、それほど笑えなくなる。
しかし、エイミーは、近過去や社会の失敗をまとめただけの映画ではありません。これは、ジャズ ポップを大衆に広め、そのジャンルの先駆者たちを尊敬した、一世一代の歌手の美しい記録です。このドキュメンタリーは、物語の簡単さのために A から B へのつながりに重点を置いた伝記映画よりも、はるかに緻密に彼女の創作過程を探求しています。彼女がついにベネットとのデュエットを録音する時、師匠とその弟子が仕事をしているのを見るのは興奮します。エイミーは、自分を傷つけた人々にあまり共感しないかもしれませんが、主題を尊重していることは明らかです。
ミュージシャンの伝記映画の多くは、レコード会社や遺産管理団体の要求に応じることにこだわりすぎていて、つまらない。それは通常、タイムラインから問題のある事実をいくつか削除し、芸術作品を生み出す神秘的なプロセスを大幅に簡略化し、貴重な知的財産を傷つける可能性のある詳細を回避することを意味する。その結果、クイーンの伝記映画では、フレディ・マーキュリーが、バンドの将来と、たまたま生きていてバンドのブランドをコントロールしている本当のスターたちを傷つける、やっかいなゲイのトラブルメーカーとして扱われることになった。『バック・トゥ・ブラック』は『ボヘミアン・ラプソディ』ほど道徳的に不快ではないが、その意図は同じだ。そこに避けられない問題がある。エイミー・ワインハウスの真実の伝記映画は、楽しく観られるものではなく、視聴者に彼女のアルバムをダウンロードするよう促すこともないだろう。観客、批評家、家族、友人、マネージャーなど、あまりにも多くの人々が、自分の行動と向き合わざるを得なくなるだろう。エイミーの痛みを思い出させるよりは、黙ってヒット曲を演奏してくれることを望む人が大勢いる。