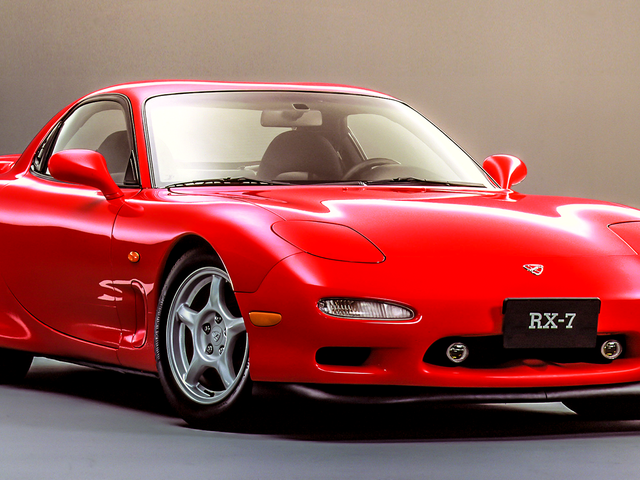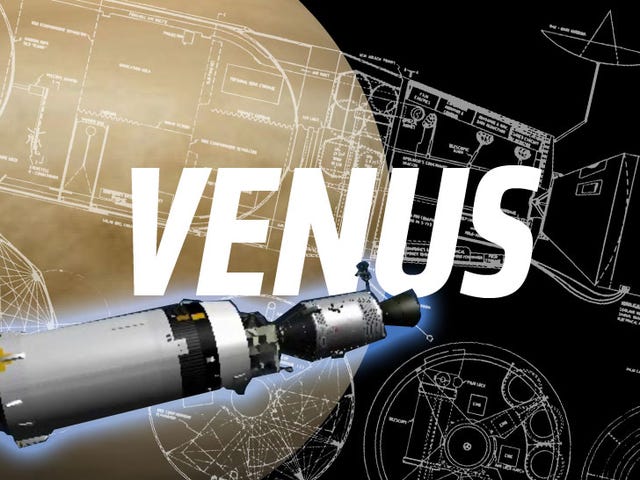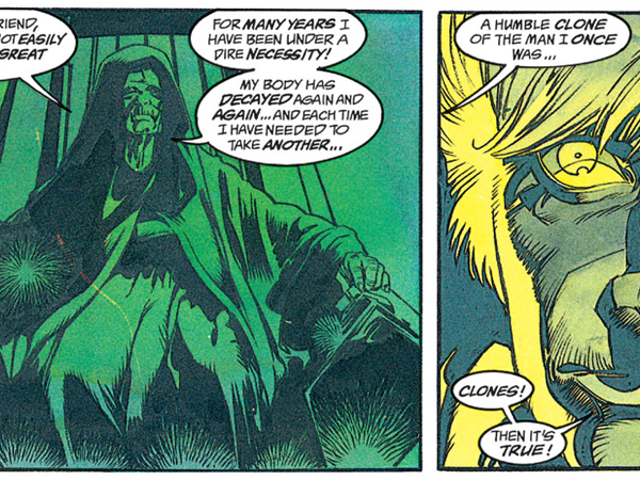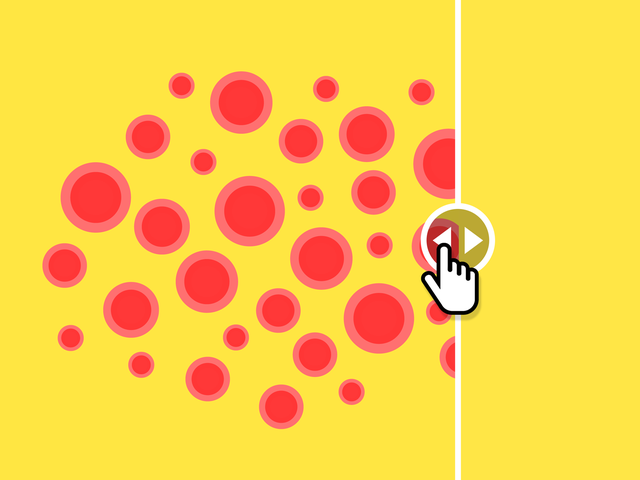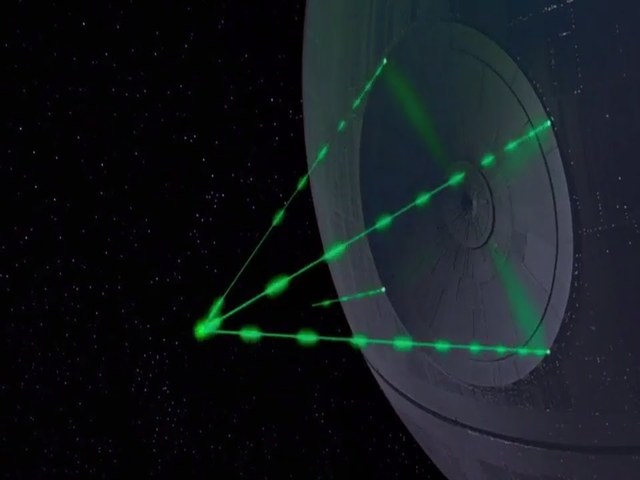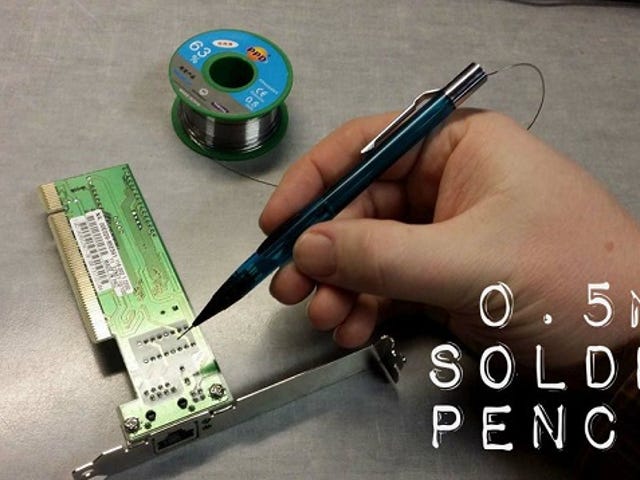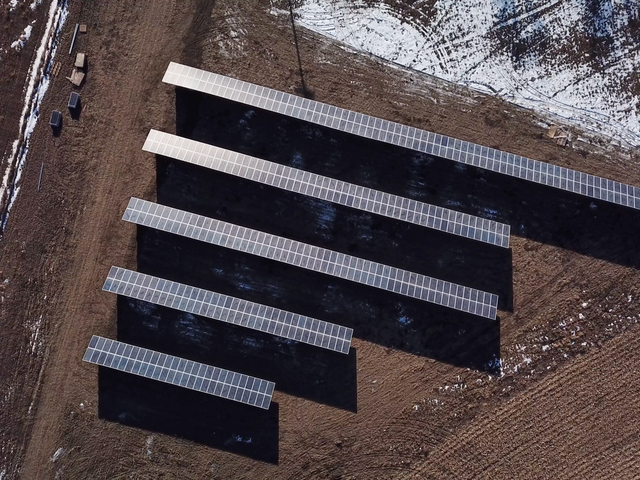2024 年のベスト映画 25 選 (これまでのところ)

映画祭が落ち着き、大ヒット作が本格的に公開され始めた今、今年のこれまでの映画を振り返るには絶好の機会だ。初冬の鑑賞で忘れていた作品を鑑賞したり、見逃してしまった逸品で鑑賞リストを充実させたりできる。2024年のベスト映画は今のところ、いつの間にかストリーマーに忍び寄り、ジャンルに関する会話を静かに独占したり、ロードショーを終えたり、カンヌやSXSWで次々と賞を獲得したりと、長い間その登場が喧伝されてきたため、誇大宣伝と現実をようやく比較したときにがっかりする恐れがある。
しかし、それらの映画が大規模なSFフランチャイズ作品であろうと 、単に「ポーション売り」の男のエッチなスポーツファンタジーであろうと、一つだけ確かなことは、ゼンデイヤが主演だったということだ。しかし、彼女がいなくても、いくつかの映画は独力で成功した。濱口竜介とジョージ・ミラーは、最高傑作の続編で期待を裏切らず、まったく異なるボリュームレベルで運営した。ジェーン・シェーンブルンとミンハル・ベイグはインディーズ映画の間で飛躍し、彼らを魅了するトピックと美学をさらに豊かに活用する方法を見つけた。ライアン・ゴズリングはテイラー・スウィフトに泣きついた。トランスジェンダーでありながらそれを楽しんでいるジョーカーは、階段をキックダンスで駆け下りたが、初めてそれが良かった。ホラー映画やアクション映画は新しい味を加え、おしゃれなタッチスクリーンのソーダマシンのような古いお気に入りをリミックスした。そして何よりも、ビーバースーツを着た男たちがお互いに暴力を振るった。
関連性のあるコンテンツ
関連性のあるコンテンツ
映画界の古い悪役たちは、自主的な検閲であれ、(信じられないことに)垂直統合された独占であれ、2024年もまだ存在しているかもしれないが、私たちがこの芸術形式に固執し続けている理由もまた同じだ。今年のベスト映画がIPスペクタクルという売れる殻の中に隠れていたとしても、その核心には、映画製作者、ミュージシャン、コメディアン、脚本家が、生活費を稼ぐための作品にこっそりと持ち込んでほしいと私たちが願うすべてのものが存在している。これらの映画は、形式(『イン・ア・バイオレント・ネイチャー』 、『ピープルズ・ジョーカー』)、私たちの身体に対する期待(『テルマ』、『アイ・ソー・ザ・TV・グロウ』)、そして照明、カメラ、アクションを通してどんなイリュージョンが可能かという私たちの理解(『フォール・ガイ』、『フュリオサ』、『Hundreds of Beavers』)を巧みに操っている。映画の敵が原点に戻ろうとしているのなら、映画の最高のものすべてが彼らを迎え撃つだろう。
野獣
ヘンリー・ジェイムズの最も心に残る物語の1つにインスピレーションを得た、足場にSFのコンセプトを取り入れた人間ドラマ、ベルトラン・ボネロ監督の『野獣』は、緊迫感と2人の素晴らしい主演俳優の演技が組み合わさり、今年の映画館で最も衝撃的な体験の1つを提供します...ただし、今見たものを解き明かすのにしばらく時間がかかるかもしれません。2044年、人間の労働力の多くは人工知能に置き換えられました。人工知能は、以前の世界的大惨事を引き起こした欠陥のある人間の思考よりも安全で感情的ではないと考えられています。この未来のパリで、ガブリエル(レア・セドゥ)は目的意識を切望しています。自分の能力を証明したいという強い思いから、彼女は過去の人生をさかのぼって感情の不安定さを一掃する手術に同意します。その考えは、遺伝子コードに残っているトラウマに立ち向かい、最終的にそれを解消することで、仕事にもっと適格になるだけでなく、より満足して従順になれるというものです。その間ずっと、彼女は3人の異なるルイ(ジョージ・マッケイ)と交流する。ルイは時に恋人、時に友人、時に恐ろしい存在だ。この想像上の未来にはあからさまな荒涼感があるが、ボネロのカメラが呼び起こす、世紀の変わり目のパリの豊かな赤と緑、2014年のロサンゼルスのプールの水のような涼しい青といった鮮やかな色彩によって、その荒涼感は打ち消される。セドゥとマッケイは、最も甘ったるいシーンから感情を絞り出す、素晴らしく力強い演技をしている。3つの異なる時代の人間体験を注意深く、系統的にたどるなかで、ビーストはあなたに爪を立て、それが残す傷について熟考するよう求める。[マシュー・ジャクソン]
挑戦者たち
一見3人のテニス選手についての物語である『チャレンジャーズ』は、実際は、出世して望む報酬を得るためにテニスの試合のように恋をする3人の登場人物についての物語である。映画の枠組みは、ライバルでありかつての親友であるパトリック(ジョシュ・オコナー)とアート(マイク・ファイスト)のキャリアにおける重要な試合である。2人の間には、一方の元恋人でもう一方の現在の妻でコーチでもあるタシ(ゼンデイヤ)がいる。ルカ・グァダニーノは常に、人間関係の激しい感情の底流を捉えることに長けており、それは『アイ・アム・ラブ』や『君の名前で僕を呼んで』などの映画で証明されている。彼の登場人物の多くにとって、欲望は存在理由であり、物語の流れの原動力である。ジャスティン・クリツケスの脚本では、欲望は3人の主人公によって大胆に、時には巧みに使われる武器である。サヨムブ・ムクディープロムのカメラは俳優たちの体を熱く見つめ、彼らの目の光の揺らめき、震える唇、汗ばんだ額のすべてを捉える。これらすべてが、現代のアメリカ映画ではあまり見られない、性的興奮に満ちた映画を作り上げている。テニスの試合では、グァダニーノはいくつかのトリックを用意している。まず、トレント・レズナーとアティカス・ロスの、大音量でドキドキする音楽。次に、多くのシーンをほとんど停止状態までスローダウンし、俳優たちの顔の動きの微妙なニュアンスを見せる一方で、興味をそそらない小さな黄色いボールは無視する。『チャレンジャーズ』が成功したのは、きらめくスクリーンスターになる途中の俳優たちが演じる複雑なキャラクターのおかげである。[ムルタダ・エルファドル]
デューン パート2
『デューン パート2』は、前作の続きから始まり、良くも悪くも前作と同じリズム、見た目、雰囲気を保っている。どちらの映画も単独では成立しないからだ。フランク・ハーバートの小説を5時間に及ぶ映画化した作品として、両方を合わせて観るべきだろう。これは、宗教の権力者が人々の信仰体系を操作して権力を獲得する方法について論争を巻き起こす作品であり、観客がハリウッド大作で通常得るもの以上のものだ。物語は、ポール・アトレイデス(ティモシー・シャラメ)が砂漠の惑星アラキスの人々を率いて悪の勢力と戦うまでの展開を追う。これは単純明快で、このような映画に期待される要素がすべて揃っている。必須の恋愛要素、暴力的な宿敵、そして主人公が自分の力に気づきそれを受け入れる。しかし、宗教的なテーマがあるからこそ、この映画は単なるスペクタクル以上のものになっている。そして、その点もクリアしている。すべてが少しだけ豪華で印象的だ。戦闘はより大規模で、砂嵐はより激しい。『デューン パート2』は、 2時間半の上映時間に見合うスリル満点の作品です。[ムルタダ・エルファドル]
悪は存在しない
『悪は存在しない』は時間をかけて作られている。冒頭、不吉な音楽が流れ、カメラが自然や植物の上を移動する。すると、どこからともなく登場人物が現れ、観客を驚かせる。登場人物が言葉を発するまでに、ほぼ30分が経過する。この忍耐と警戒の二分法にこそ、オスカー受賞作『ドライブ・マイ・カー』に続く濱口竜介監督の天才性が宿っている。これは、単純な善と悪のゲームのような寓話であり、息を飲むほどの密度の物語で展開される。濱口監督の簡潔なストーリーテリングは、空間感覚を構築することから始まる。観客は、山間の田舎の村、水引に紹介される。カメラは地形、水源、背の高い木々にクローズアップし、その後登場人物が姿を現す。マーケティング会社が町にやって来て、グランピング施設を建設する計画を発表すると、一人の人物が中心的役割を担う。町のことを一番よく知っていると思われる何でも屋のタクミ(大甕仁志)だ。すぐに代理店の人たち(小坂竜二と渋谷彩夏)は、タクミが町民に計画を納得させるのに役立つ人物だと考え始める。しかし、まずタクミを説得し、納得させる必要がある。こうしてゲームが始まり、参加者が特定され、賭け金が明らかになる。[ムルタダ・エルファドル]
スケープゴート
何よりも、『ザ・フォール・ガイ』は観客を喜ばせる作品だ。グレン・A・ラーソン制作の同名テレビシリーズをドリュー・ピアース ( 『ホテル・アルテミス』) が脚色したデヴィッド・リーチ監督のこの映画は、正真正銘の魅力的な俳優たちを同じフレームに収めるための大々的で巧妙な口実だ。彼らは爆発やカーチェイスで取り囲まれ、バックでKISSやダークネスの音楽が鳴り響く中、楽しい時間を過ごしている。「スケープゴート」はベテランスタントマンのコルト・シーヴァース (ライアン・ゴズリング) で、好きな仕事があり、カメラマンのガールフレンドのジョディ (エミリー・ブラント) はもっと気に入っている。コルトが代役を務める俳優で自己中心的なトム・ライダー (アーロン・テイラー=ジョンソン) が、コルトにもう一度大規模な落下スタントを要求してくるまでは、全てコルトにとって思い通りに進んでいるかに見えた。物事がうまくいかなくなり、コルトは背中を負傷し、さらにプライドを傷つけられてスタントマンの座から退く。リーチはスタントマンとしてキャリアをスタートさせ、この映画に全力を注ぎ込み、マイアミ・バイスへのオマージュからゴミ収集車との予想外の格闘シーン、そしてもちろん、世界中の映画セットで仕事をしているスタントチームへのオマージュまで、あらゆるものを私たちに提供してくれた。アクションとスタントマンがフルスロットルで稼働しているにもかかわらず、ザ・フォール・ガイを本当に成功させているのは、ゴスリングとブラントのパートナーシップだ。彼は、ザ・ナイスガイズなどの映画で非常にうまく演じたように、再び償いを求める打ちのめされたヒーローを演じ、一方、彼女は、キャリアと心の欲望のバランスを取ろうとしている野心的な女性を演じている。これは、映画スターが絶対的な魅力マシンである2時間であり、時にはそれだけで十分だ。[マシュー・ジャクソン]
フリップサイド
クリス・ウィルチャが新作ドキュメンタリー『フリップサイド』で試みているすべてのことを理解するのに、特定の年齢である必要はないが、年齢が高ければ理解できるのは確かだ。このプロジェクトがジェネレーションXの経験に語りかける方法は、特に自分をアーティストだと思ったことがある人にとっては、非常に具体的で、まるで攻撃のように感じられる。誤解のないように言っておくと、それは褒め言葉だ。映画のタイトルでさえ、映画の中で頻繁に登場するニュージャージーのヴィンテージレコード店と同じで、自分の前にあるものよりも後ろにあるものの方が多いことに気づく人生のあの瞬間を思い起こさせる。この映画のメッセージがウィルチャの世代以外の人にとってわかりにくいというわけではない。後悔や世界に足跡を残したいという願望など、普遍的に共感できる概念も扱っている。ただ、監督がかつての理想主義的で野心的な子供と、50代の男性になった自分を折り合わせる旅は、自分の人生を振り返る立場にある人たちの心に深く響くだろう。フリップサイドは、ウィルチャが生涯の仕事の原点に立ち返ろうとする試みであり、25年間の人生経験から得られる距離と後知恵をもって、個人的な自己反省である『The Target Shoots First』に戻るというものだ。それは聞こえるほど内省的ではない。より広い視点で自分の主張を述べるために、ウィルチャは放棄したドキュメンタリーの映像を取り入れ、ある種の決着を求めて以前の被写体のいくつかに戻ることさえある。ウィルチャは、自分の理想主義が現実主義に、野心が自己満足に取って代わられたことを認めている。彼は若い自分をじっと見つめ、ひるむ誘惑に抵抗している。[シンディ・ホワイト]
フュリオサ: マッドマックス サーガ
『フュリオサ:マッドマックス サーガ』は、ジョージ・ミラーが『フューリー・ロード』がなくても存在しうるフュリオサの内面生活と歴史を構築することに全力を注いでいるため、私の厳重に管理された高評価の前編のライブラリに正式に加わった。そしてミラーは、フュリオサで集められた人間関係、つながり、喪失をサブテキストに変えるという、すでに崇高な『フューリー・ロード』をさらに素晴らしいものにするという、前編の最高の技を繰り広げている。フュリオサの物語は5つの章に分かれており、緑の母親たちの隠れた牧歌的なコミュニティに住む子供(アリラ・ブラウン)として彼女と出会うところから始まり、彼女の15年間の人生を経て、20代半ばで彼女がずっと若いイモータン・ジョー(ラチー・ハルム)の城塞の中で皇帝フュリオサ(アニャ・テイラー=ジョイ)になったところで終わる。そして『フュリオサ』はやはり体験だ。それはあなたを砂のように飲み込み、最後の最後までしっかりと抱きしめてくれる。撮影監督サイモン・ダガン(『華麗なるギャツビー』)は、『フューリー ロード』の撮影監督ジョン・シールから映像のバトンを受け継ぐ際、一歩も間違えない。 『フュリオサ』は、特にIMAXで観ると感覚を圧倒する。ダガンとミラーは、砂丘を轟音を立てて走る車や、シタデルとブレットファーム、ガスタウンを結ぶ道路を走る車の中に観客を没入させる。『フュリオサ』のほぼすべてのシーンが直感的でリアルで、たまに映画館でこのような体験ができるのがいかに特別なことかを思い出させてくれる。[タラ・ベネット]
ゴーストライト
アレックス・トンプソンと脚本家のケリー・オサリバンが共同監督を務める『ゴーストライト』には、実在の夫婦とその娘が出演し、真実味を帯びている。その結果、深く不快な感情を建設的に解消する方法を見つけることを描いた、小さな特注品が生まれた。イリノイ州の郊外で、建設作業員のダン(キース・クプフェラー)は感情的な行き詰まりに悩まされており、妻のシャロン(タラ・マーレン)と十代の娘デイジー(キャサリン・マーレン・クプフェラー)との間に疎遠になっている。デイジーは最近の反抗的な行動のせいで退学の危機に直面している。仕事中にダンがキレたとき、このつかの間の公衆の怒りの瞬間が女優のリタ(ドリー・デ・レオン)の注意を引く。何かを感じ取ったリタは、ダンを台本読みに引き込み、原作を知らないにもかかわらず、彼女が制作する簡素なコミュニティシアターの『ロミオとジュリエット』に参加するよう勧める。ダンは最初は完全に拒否し、その後懐疑的になるが、グループのリハーサルに引き戻される。この展開は妻と娘には秘密にしている。映画が展開するにつれ、家族に降りかかる漠然としたトラウマ、そして3人が抱える複雑で時には対立する感情が、より鮮明に浮かび上がってくる。この家族のドラマと癒しは、その後、劇の初日に向けてのいくつかの紆余曲折を背景に展開する。オサリバンとトンプソンは、控えめで率直な技術パッケージを巧みに監督し、飾り気のない魅力を生み出している。映画のキャラクターの細部に対する鋭い目と、控えめなユーモアと哀愁の自然な融合は、撮影監督のルーク・ダイラによってワイドフレームでうまく捉えられ、やや高めの感情のピッチと生来の喜ばせたい気持ちを克服している。最も基本的な意味で、ゴーストライトは悲しみとそれを処理するコミュニティの有用性についての映画であり、それが明白に思えるとしても、ここで表現されているように、それはそれでもかなり鋭い。 [ブレント・サイモン]
緑の枠
ポーランドの巨匠映画監督アニエスカ・ホランド の最新作「グリーン・ボーダー」は、直接行動への呼びかけにほかなりません。この映画は、ポーランドとベラルーシの国境で移民が直面する危険な状況を、時には率直に言って残酷ではあるものの、微妙なニュアンスで描いています。その状況は、対立する軍や活動家勢力によって悪化したり緩和されたりしています。この特定の国境は、両国を隔てる深い沼地の森にちなんで「グリーン・ボーダー」と呼ばれています。ベラルーシの独裁者アレクサンドル・ルカシェンコが画策した詐欺的なキャンペーンに騙されたアフリカや中東からの移民は、ポーランドへの迅速かつ安全な移動手段が見つかるという保証を受けて、東ヨーロッパの国(そしてロシアの有名な同盟国)へと旅し、欧州連合に亡命を申請することができます。しかし、実際に国境を越えると、ポーランドの国境警備隊は難民たちを再び集め、有刺鉄線を越えてベラルーシに送り返す。ベラルーシで彼らは虐待され、強奪され、叱責された後、暴力的にポーランドに押し戻される。ホランドは、憤慨した怒りとそれを裏付ける反駁の余地のない事実をもって題材に取り組んでいる。「ダイアログ」では、ヨーロッパでの移民の死亡者数の増加が直接述べられており、登場人物は、難民、活動家、ポーランド国境住民、匿名の国境警備隊員への何時間にも及ぶ制作前インタビューを通じて形成された。この映画を豪華な白黒で表現することにより(頻繁な協力者であるトマシュ・ナウミウクが巧みに撮影)、グリーン・ボーダーは時代を超越したアプローチを感じさせ、社会的「脅威」と見なされる人々に対する過去および進行中の暴力を再び強調している。アフリカと中東の難民、ヨーロッパのユダヤ人、パレスチナの民間人に対する扱いはすべて、国家公認のサディズムと、単純化されたプロパガンダに盲目的に従う人々によって結びついている。『グリーン・ボーダー』の最も素晴らしい点は、スリリングで悲惨な物語に支えられた、人間化への徹底的な取り組みに加え、誰も見逃さないという点だ。[ナタリア・ケオガン]
セックスの仕方
脚本・監督のモリー・マニング・ウォーカーの長編デビュー作である「ハウ・トゥ・ハブ・セックス」は、多くのティーンのセックス・コメディの伝統を踏襲している。違いは、「ハウ・トゥ・ハブ・セックス」がリアルで、セックスと同意という深刻なテーマを扱っている点だ。設定はおなじみのものだ。3人のイギリス人の友人が高校最後の年にギリシャで夏休みを過ごす。スカイ(ララ・ピーク)とエム(エンヴァ・ルイス)はタラ(ミア・マッケナ=ブルース)よりも少しだけ経験豊富で、タラはこの旅行で処女を捨てたいと思っている。この映画監督は、10代の友人同士の接し方をよく理解している。お互いを気遣い、愛情を示す優しい様子。ささいな不満や説明のつかない敵意が、時折お互いへの反応を左右する。友情と優越感。大人がいないときに感じる放縦さ。お酒を飲んだときの高揚感。それに加えて、マニング・ウォーカーは、同意が反対に、欲望が嫌悪に変わる微妙な境界線をうまく乗り越えている。彼女のカメラは、登場人物が言葉にできない物語を伝えるために、俳優たちの顔や周囲を繊細に探っている。若いケイト・ウィンスレットを彷彿とさせる、同じように温かみのあるスクリーン上の存在感と感情的な大胆さを持つマッケナ・ブルースは、素晴らしい演技でこの映画を支えている。マニング・ウォーカーはタラの視点に焦点を当て続けるので、観客は常に彼女が感じていることを感じることができる。そして、ほとんどの場合、タラは確信が持てず、それが彼女の物語を魅力的にし、この映画を魅了している。[ムルタダ・エルファドル]
何百匹ものビーバー
即席の罠猟師、ジーン・カヤック(共同脚本家/主演:ライランド・ブリクソン、コール・テューズ)は、雪解けとともにツンドラに一人きりになり、あらゆる行動に喜劇的な反応がある時代、つまり、板の端をのこぎりで切って空中に立つことができ、重力が犠牲になる前に大笑いできる猶予時間を与えてくれる時代へと、タイムスリップしてしまう。セリフのない白黒コメディ『Hundreds of Beavers』は、 『ゼルダの伝説』、チャーリー・チャップリンの『黄金狂時代』、ジブジャブス、テリー・ギリアムのアニメ、ガイ・マディン、ジャッカスといった、まったく異なる要素から構成されている。メリエス風のストップトリックやマペット人形劇の中で、アクメの名前が挙げられている。その美学は、まばらな雪のキャンバスに暴力を描くことから、精巧なドイツ表現主義の要塞の暗い奥深くを駆け抜けることまで多岐にわたる。バカバカしいが、崇高だ。マスコットの衣装を着た生き物が初めて氷の上で糞を食べるシーンでは、あなたは笑ってしまうだろう。そして、エンドロールが流れるまで笑いが止まらないだろう。ここ数年の最高のコメディーの1つである『Hundreds of Beavers』には、実はビーバーの数よりも多くのオチがあるかもしれない。映画製作者のマイク・チェスリックは、映画の初期の頃に使われていた手法を認識し、それを再利用することで、古典的なハンターとハントされる力関係をとんでもないほどエスカレートさせ、私たちがお互いを笑わせる方法に関する永続的で普遍的な真実を奇跡的にDIYで祝福している。[ジェイコブ・オラー]
テレビが光っているのを見た
脚本・監督のジェーン・シェーンブルンは、前作の傑作『みんなで世界博覧会に行く』 で、そうした執着心を、潜在的に危険な結果を伴う得体の知れないインターネットゲームという形で描いた。今回、シェーンブルンはより個人的で、より原始的に心に残る作品に取り組んでいる。『I Saw The TV Glow』は、ポップカルチャーへの執着心を見事に描き出している。それがいかに私たちを結びつけ、変え、高揚させ、不安にさせる形で私たちの人生全体に波及するのかを描いている。『I Saw The TV Glow』で特に目立っているポップカルチャーへの執着心は、『The Pink Opaque』という、土曜の深夜に放送される超自然的なティーンドラマである。物語は、超能力のつながりによって遠く離れた場所から結ばれた親友2人が、あらゆる種類のモンスターと戦うのを追う。オーウェン(10代前半のイアン・フォアマンと高校生のジャスティス・スミスが演じる)は孤独な少年で、チャンネルを回しているときにこの番組をちらっと見かけ、熱狂的なファンのマディ(ブリジット・ランディ=ペイン)に『The Pink Opaque』の本当の姿について尋ねるほど興味をそそられる。映画の映像は、退屈で色あせた現実の海を漂う2人の人物が、自分たちの人生に意味を与えてくれるつながりを求めてあちこちを航海しているのを見ているような感覚を呼び起こす。もちろん、『I Saw The TV Glow』の真髄は、シェーンブルンが登場人物の執着の変容的な性質に焦点を当て、それが変身をもたらすか、または危険で麻痺させる解離性エピソードを引き起こすだけなのかを見極めるところにある。この映画に傾倒し、シェーンブルンのトーンポエムの本能に従う気があれば、魔法のようなものが見つかるだろう。彼らは、メディアが誰かの人生を変える物語であると同時に、誰かが本当の自分を見つけるために遠回りをする物語でもある物語を描き出しました。[マシュー・ジャクソン]
あなたのアイデア
同世代屈指の女優が最高の演技を披露し、熱心な観客を席から唸らせるような真摯な情熱に満ちた『アイディア・オブ・ユー』は、ここしばらく見た中で最高のロマンティック・コメディーの1つだ。『アイディア・オブ・ユー』は、10代の娘(エラ・ルービン)の子育てと、ロサンゼルスのシルバーレイク地区で流行のアートギャラリーの経営に全力を注いでいるシングルマザーのソレーヌ(アン・ハサウェイ)を追う物語。だがソレーヌは、自分がもっと何か、つまり、計画中の一人キャンプ旅行で見つけたいと思っている何らかの充実感を求めていることも隠さず認めている。しかし、イライラした元夫(リード・スコット)が、娘とその友人たちをコーチェラに連れて行って、中学時代に大好きだったワン・ダイレクション風のボーイズバンド、オーガスト・ムーンを観させるのをキャンセルするまでは。ソレーヌは、オーガスト・ムーンのハンサムで魅力的なリードシンガー、ヘイズ・キャンベル(ニコラス・ガリツィン)と対面する。ヘイズは、ソレーヌの自信と、最初は彼だと気づかなかったことに魅了される。素敵な出会いだったが、ソレーヌはそれを気に留めなかった。ヘイズがソレーヌのギャラリーに現れ、ソレーヌのことを知ろうとするまでは。この出会いをきっかけに、40歳のシングルマザーと24歳のポップスターは世界中を旅することになる。ハサウェイは、とても人間的で傷つきやすい役柄にリラックスし、物語の重要な感情の核心部分を占め、憧れ、疑念、喜びが入り混じった感情をくすぐっている。ガリツィンが彼女と画面を共有しながら完全に焦点がぼけてしまうことは偉業だが、さらに進んで、彼女の感情のリズムに合わせて自分自身の素晴らしい演技も披露する。これらすべてに加え、非常にキャッチーなボーイバンドの曲、軽快なコメディ調、そしてベテランのロマンティック・コメディファンでさえも少しは予想を裏切る第3幕など、『The Idea Of You』はロマンティック・コメディの定番作品として非常に歓迎すべき新作だ。[マシュー・ジャクソン]
暴力的な性質の中で
クリス・ナッシュの長編映画デビュー作『In A Violent Nature』は、主人公のジョニー(ライ・バレット)が肉体のない声同士の当たり障りのない会話のあと、沈泥と枯葉の層から這い出てくるシーンで、観客をスラッシャー映画の移り変わりの激しい生態系の泥沼に即座に引き込む。まるで森自体が憑りつかれたかのようで、舞台と登場人物の境界線が曖昧になっている。これらはすべて、ナッシュの特異な映画製作の特徴だ。背景が前景に、アクションが無作為に、暴力が自然の静けさに溶け込んでいく。このようなゆったりとした見方(悪役の視点に常に固定されたまま)では、ビデオゲームの仕掛けのように感じられる可能性もあるが、ナッシュはこの整然とした視点の映画的価値を引き出す。監督はトーンと空間を厳密にコントロールしているため、騙されているという感覚は一切感じられない。ショットは長いワンテイクで丹念に構成され、邪魔になる音楽なしで、木の枝がきしんだり折れたりする音を吸収し、周囲の世界をじっと見つめることで音楽の代わりをします。暴力がエスカレートし、映画史上最も残酷な殺人シーンの 1 つ (見ればすぐにわかります) で最高潮に達する中、ナッシュは死を目撃するという純粋に肉体的な感覚に訴え、本能的な肉体的共感を駆使します。In A Violent Natureでナッシュはまったく新しいもの、つまり、落ち着いていて、身近でリアルなものを作り上げています。しかし、この映画のトーンとタイミングの感覚は、彼がなぜ観客がいつもこれらの血と血みどろのマラソンに夢中になるのかを深く理解していることも証明しています。[アナ・マッキビン]
感染した
セバスチャン・ヴァニチェク監督の『Infested』では、フランスのアパートに一匹の珍しいクモが侵入する。そこでは、進取の気性に富んだ若者 (テオ・クリスティーヌ) とその家族や友人たちが、より良い生活を築こうとしている。その後数日の間に、その一匹のクモは、恐ろしい、容赦ない、絶えず増殖するクモの軍団に変貌し、クモホラーの古典『アラクノフォビア』に匹敵する作品となっている。満足のいくほど不気味なクリーチャー映画として始まったものが、やがて、8本足の猛獣による真に驚くべき残忍な瞬間で最高潮に達する、歴史に残るサバイバルホラーの激突へと変貌する。[マシュー・ジャクソン]
ジャネット・プラネット
ピューリッツァー賞受賞劇作家アニー・ベイカーの映画デビュー作『ジャネット プラネット』は、1991年の霞がかった夏のマサチューセッツ州西部を舞台に、思春期の視線を通してこの時代と場所の質感を絶妙に捉えている。ベイカーの戯曲は閉鎖空間での長いシーンを描いているが、映画製作への進出は正式に認められており、鋭くも曲がりくねった会話と豊かな16ミリの映像に対する彼女の長年の関心が実践されている。彼女のスタイルを物語的には味気ないと感じる人もいるかもしれないが、彼女の幅広い作品のファンは、彼女が映画に映し出す静かな細部に、馴染みのある安らぎ、そして幅広い魅力を見出すだろう。11歳のレイシー(印象的な新人ゾーイ・ジーグラー)は、自殺すると無表情で家に電話した後、母親のジャネット(ジュリアン・ニコルソン)を説得して、本来は長期の合宿になるはずだった場所から迎えに来てもらう。そのとき初めて、レイシーは家に帰ることはあまり賢明な決断ではなかったかもしれないと気づく。母親の現在のボーイフレンド、ウェイン(ウィル・パットン)と空間を共有する必要があるからだ。レイシーと母親の関係には共依存の典型的な兆候が散りばめられているが、ジャネットは恋人、友人、スピリチュアルな相談相手など、次々と現れる人々と時間を共有することにあまりにも熱心であり、娘の隠し切れないフラストレーションは大きい。『ジャネット・プラネット』は、レイシーが一人でピアノ教室に通う様子から、アヴィが長々とスピリチュアルな話をする様子まで、ありふれた日常に焦点を当てている。しかしベイカーは、子供の楽観的な見方によって日常的な環境がどのように高められるかについても熟知している。ショッピングモールは手の込んだ遊び場になり、シャワータイムの新しいシャンプーは刺激的な実験になる。ここでは、夏のスモッグの魔法がそれをさらに複雑にしている。芸術的ラベルをこれほどシームレスに超越できるアーティストはほとんどいないが、アニー・ベイカーは、さまざまな媒体を駆使して静かに物語を語る天性の才能を備えていることを証明した。[ナタリア・キーガン]
優しさの種類
ヨルゴス・ランティモスの新しいアンソロジー映画、「三部作の寓話」 『Kinds Of Kindness』の原題には、破壊的なスリルがあった。 映画を「そして」と名付けることは、SEOとマーケティングの常識のほとんどすべてに反するものであり、そのアイデア自体が、あらゆるスタジオの幹部と検索エンジンに対する厚かましい中指を立てているように感じられた(たとえ、上映時間を探している人にとっては少々悪夢だったとしても)。しかし、『Kinds Of Kindness』(ランティモスが、『女王陛下のお気に入り』と『かわいそうに』を除くほぼすべての作品で共同執筆を行っているエフティミス ・フィリッポウと再タッグを組んでいる)を見ると、改題の賢明さが明らかになり、原題の反抗的な魅力はすぐに忘れ去られる。ランティモスの映画を見たことがある人なら、この新しいタイトルに明らかに皮肉な含みがあることに気づくだろう。なぜなら、彼の無味乾燥な世界には、思いやりや無私無欲が常に欠けているからだ。しかし、ランティモスとフィリッポウの他のコラボレーション作品以上に、『Kinds Of Kindness』は、アイデンティティがシュールなほど歪んでおり、感情が不安になるほど冷たい、この二人の心理的ディストピアへの強烈な冷徹さでもあり、そのため、人間関係を強調するタイトルは完璧にふさわしいと感じられる。『Kinds Of Kindness』の3つの章は、タイトルによって最も明確に結びついている。「RMFの死」、「RMFは飛ぶ」、「RMFはサンドイッチを食べる」。これらはすべて、実際のキャラクターというよりは、プロットの軸に近い、寡黙で名も知らぬ男について言及している。各エピソードには、ジェシー・プレモンス、エマ・ストーン、ウィレム・デフォー、マーガレット・クアリー、ホン・チャウ、マモドゥ・アシー、ジョー・アルウィン(ハンター・シェーファーは最終章のみに登場)という緊密な俳優陣も共通している。しかし、その核心において、この映画の3つの物語を最も結びつけているのは、選択とコントロール、服従と服従の共通の探求である。この映画は、狂人による『愛の5つの言語』の解釈と似ていないわけではない。ただし、ここでは、自発的な「奉仕行為」が、感情的な暴君のサディスティックな要求を満たすための犠牲として再考されている。一見すると、『Kinds Of Kindness』には、ランティモスの作品に最も関連した表面的な要素がいくつか欠けているように見えるかもしれない。たとえば、撮影監督のロビー・ライアンは、『Poor Things』で頻繁に使用した魚眼レンズを、この作品ではほとんど使用していない。しかし、より深い意味では、この映画はランティモスの最高傑作のように感じられる。監督は、より親しみやすい映画で他の脚本家と数年間協力した後、フィリッポウと再びタッグを組み、独特のスタイルを貫いている。この作品ほど大胆で意見が分かれることはない。『Poor Things』のハッピーエンドへの短い進出に続き、『Kinds Of Kindness』は、 ランティモス監督は、「楽しめる」と言うのが変な感じの映画に戻ってくる。つまり、ギリシャの怪物が帰ってきたということだ。[ファラ・チェデッド]
ラ・キメラ
アリス・ロルヴァケルのロマンティックな宝探し『ラ・キマイラ』では、過去があまりにも身近で、ほとんど触れられるほどだ。イタリアの田舎として知られる、生と死の間の境界領域を舞台にしたロルヴァケルの注意深く掘り下げられた物語は、喪失と希望についての可笑しくも深い満足感を与える瞑想を掘り起こす。私たちは夢の中でアーサー(ジョシュ・オコナー)に出会う。彼の一人称視点で、彼は愛し、失い、そして必死に再び見つけたい女性、ベニアミナ(イレ・ヤラ・ヴィアネッロ)の顔をうっとりと見る。彼女はアーサーの手の届かないところから彼を悩ませ、彼が引きたいと願う過去からの赤い糸を残していく。幸いなことに、それはアーサーの得意とするところだ。アーサーの主な探求は、別の種類の聖杯を求めることだ。ベニアミナと再会し、長引く借金を返済することを願ってイタリアに戻ったアーサーは、しぶしぶイタリアの墓泥棒である昔の仲間と再会する。彼らは裏庭で貴重品を探し回っているが、その助けとなるのが、アーサーのトスカーナの昔の地下室との超自然的なつながりだ。トンバロリは廃墟の中に住み、暖房も家具も床もないボロボロの小屋を家と呼んでいる。この段階では、生まれたとき着ていたと思われる朽ちかけた白いリネンのスーツを着たアーサーは、自分が探し求める遺物に似てきている。彼はベニアミナの家で最初の墓を見つける。そこにはベニアミナの母フローラ(自然と慰めてくれるイザベラ・ロゼリーニ)が住んでいる。丸みを帯びたエッジが16mmの写真を思い出させ、この映画はまるで過去から発掘された何かを見ているかのような古風な雰囲気を醸し出している。ローヴァッハーの「Happy As Lazzaro」 やアカデミー賞候補の短編「Le Pupille」の脚本を手掛けたカルメラ・コヴィーノ、マルコ・ペッテネロと共同で執筆されたローヴァッハーの脚本は、すべてのセリフの裏に驚きを隠し、アーサーの過去の要素を明らかにし、彼の現在を再構築している。驚きに事欠かない形式的な喜びである「La Chimera」は、朽ち果てていく空間と生き生きとした演技で観客を魅了する。[マット・シムコウィッツ]
モンキーマン
デヴ・パテルは十分な準備をした。しかし、影響を受けたものを知ることと、それをスクリーン上で実践しながらも、独自の声を一切失わないことは、まったく別の話だ。数々の成功を収めたパテルの映画は、そして『モンキーマン』は瞬間瞬間の成功が詰まった映画だ。この映画が最大の成功を収めたのは、監督の純粋で躍動的な映画への愛を、大胆で新しく、忘れられないものにシームレスかつ力強く変換した点かもしれない。パテルは、インドのスラム街に住むみすぼらしい若者、キッド役を演じる。キッドには、精神的にも肉体的にも、決して消えることのない傷がある。少なくとも、引き金を引いて、自分の苦痛の原因となった男たちに復讐するまでは。『モンキーマン』の多くのアクションシーンには、 『タクシードライバー』から『ドラゴン危機一発』、 『ザ・レイド』、 『ザ・ヴィランズ』など、さまざまなシーンが盛り込まれており、パテル監督と撮影監督のシャローネ・メイヤーが抑えきれない熱狂的なエネルギーで表現している。だがパテルは単に引用をつなぎ合わせているわけではなく、アクション映画を一生観ていれば身についたであろうルールをすべて守っているわけでもない。大量の流血と残虐行為があり、そのすべてが巧みに作られているが、『モンキーマン』が最も力を発揮するのは静まったときだ。キッドは何十年もの痛みを抱えた戦士であるだけでなく、落ち着かない心を静め、痛む心を癒す方法を探している男でもある。パテルは、アクションストーリーが示唆する以上に、物語のメタファーを深く掘り下げ、キッドを貧困層だけでなく、自分たちを押し戻し続ける社会で自分の道を歩もうとする追放者たちの中に埋め込んでいる。この作品は、キッドの孤独な旅では決して得られなかったコミュニティ感覚を映画に吹き込み、神話的な雰囲気を醸し出している。『モンキーマン』は力強く、感情的で、猛烈な勝利を収めた映画であり、観終わった後もすぐに戻って最初から最後まで観たくなるだろう。[マシュー・ジャクソン]
オリオンと闇
『エターナル・サンシャイン』のような形而上学的な入れ子人形映画の、不安に悩まされながらも脚本を書いたチャーリー・カウフマンが子供向けの長編アニメ映画を執筆するというのは、デヴィッド・リンチが監督したG指定のディズニー映画や、ナイン・インチ・ネイルズのフロントマン、トレント・レズナーがピクサーの音楽を作曲するのと同じくらいありそうにないことに思える。しかし、それらのことは実際に起こり、大いに称賛された。そして今、この映画もそうなった。『オリオン・アンド・ザ・ダーク』は、これまでのチャーリー・カウフマンのどの映画ともほとんど似ていないかもしれないが、彼の個性が表れている。それは幼い子供たちには少々過激かもしれないが、この物語に描かれているような11歳の子供たちにとっては、彼らの知性を過小評価しないというだけで共感を呼ぶかもしれない。この作品で彼は、4歳児が暗闇への恐怖を克服するのを助けるために書かれた児童向けの大作を取り上げ、ほとんどの子供たちが名前がなくてもそのようなものを経験し始める年齢である実存的恐怖について描いている。ショーン・チャーマッツ監督(トロールズ ホリデー・イン・ハーモニー)は、映像を子供向けに保ちながら、カウフマンの声も最初から最後まで認識しやすいものにしている。そして『オリオン・アンド・ザ・ダーク』は形式的な家族向け映画のように見えるが、愛情深くも感情的に壊滅的な解決に向かう途中で、いくつかの重大なひねりを加える。子供たちは楽しめるだろうか?デイヴィッド・フォスター・ウォレス、ソール・バス、ヴェルナー・ヘルツォーク(本人役)への言及はおそらく子供たち向けではないとだけ言っておこう。しかし、あなたには大いに楽しめるだろう。原作では、4歳児が暗闇への恐怖に立ち向かう準備ができているかどうか、親の判断が必要だが、この映画は、11 歳の子供たちが死、いじめ、気候変動、そして文字通り彼らが考えつくあらゆること、そしてそれ以上のことへの恐怖に対処する能力について、子供たちに問いかけています。[ルーク Y. トンプソン]
人民のジョーカー
DIY の創造性が溢れる『ザ・ピープルズ・ジョーカー』は、世間知らずのクリエイターが率いるファン プロジェクトにすぎないと、一般の人は思うかもしれない。しかし、映画監督のヴェラ・ドリューは、共同脚本家のブリ・ルローズとともに、2019 年の『ジョーカー』の大まかな概要を足がかりにして、コメディ業界の硬直した世界での自身の経験、傷ついた人々が恥と無知から互いを傷つける方法、そしてトランスジェンダーとしてのアイデンティティを発見する葛藤を探求している。ヤング・スーパーマンの田舎で育った子供時代を回想形式で語るハーレクイン・ジョーカー(ヴェラ・ドリュー)は、母親(リン・ダウニー)から抗うつ薬スマイレックスを処方され、コメディ界のスターの座に就くことが逃げ道となる青春時代を私たちに教えてくれる。UCBライブの舞台は、アップライト・シチズンズ・ブリゲード、SNL、およびそのショーランナーであるローン・マイケルズ(マリア・バンフォードが声を担当した、もがくアニメの模倣者)を露骨にパロディ化している。全編グリーンスクリーンで撮影された『ザ・ピープルズ・ジョーカー』は、従来の一貫性の概念に抵抗する誇らしげに人工的な美学を備えている。3Dやストップモーションで動く、または人形として動くキャラクターは、時には注意深く作られ、また時には同様に意図的なポストパンク的な無頓着さで、人間のキャストと交流する。いくつかのシーンは、アクションシーンだけでなく、非常に親密なシーンもすべて2Dでアニメ化されており、このクリエイティブな選択が予算削減のためだけのものではないことを示しています。混沌とした美学ですが、混沌としているからこそ一貫性があるように見えます。ある意味では、大予算の超大作映画がストーリーを語る人工的なメカニズムを直接風刺していますが、同時に、私たちが共有する文化的神話の枠組みの中で、非常に個人的なストーリーテリングの手段も提供しています。ピープルズ・ジョーカーは、対立と矛盾でできたキメラですが、私たちもそうです。人間の経験のジグソーパズルは普遍的に混沌としており、ドリューが私たちに伝えようとしていることが1つあるとすれば、それは、私たちはそれらのパラドックスを楽しむべきだということです。そうすれば、もう笑顔を描く必要はありません。私たちはただ幸せになれるのです。[リー・モンソン]
ロボットの夢
多才なスペイン人映画監督パブロ・バーガーはこれまでにも無声映画を製作してきたが、『ロボット・ドリームス』のような作品はこれまでなかった。冒頭の沈黙の誓いを破って『ウォーリー』 がビッグ・トーキーに身を売ったと思っている人に向けたニューヨーク観光広告である『ロボット・ドリームス』は、一言のセリフもなく延期された友情の痛みや苦しみ、喜びを伝えている。ミニマルにデザインされた登場人物は話さないが、このロボットの夢の要点は、本物の都会の音風景と擬人化された動物たちとその仲間のロボットに満ちたバーガーのニューヨーク旅行を複雑にしている。深い青の夕暮れのクイーンズボロ橋で始まる『ロボット・ドリームス』は、80年代に生き、アタリと冷凍マカロニチーズでまた夜を過ごす孤独な雑種犬のドッグを紹介する。ポンで(再び)自分自身に勝った後、ドッグはついにポンで(再び)自分自身に勝つことの孤独を認めるそこで、完璧なタイミングで流れるインフォマーシャルの指示に従って、彼は新しい友達、ロボットを作るよう命じる。首をひねると、ロボットはレーガン時代の PC に DOS がロードされるように起動し、突如、ドッグの人生に目的が生まれる。『Robot Dreams』の強みは、アボットとコステロ、あるいはローレルとハーディの動く影のようなロボットとドッグにある。これらの原型を念頭に置いて、バーガーは最大限のコミュニケーションを図るために彼らの違いを強調している。ドッグは実用的で用心深く、社会的違反の結果を認識しており、その代償を払っている。ロボットはもっとオープンマインドで、歓迎の笑顔と手を振って、新しい冒険のたびに出迎える準備ができている。しかし、離れていると、周囲の人々とつながることが難しいことに気づく。『Robot Dreams』で、バーガーは美的には穏やかだが感情的には強靭なニューヨーク市も作り上げた。その規模の都市では制御できるものはほとんどないという信念の下で、バーガーは映画が空想の飛躍を遂げ、それが再び友情へと戻ってくるようにしている。こんなにたくさんの人で溢れている街が、どうしてこんなに孤独を感じるのでしょうか? 一言も発することなく、Robot Dreams は答えを持っています。[Matt Schimkowitz]
ストップモーション
アイスリング・フランシオシが主演するこのぞっとするような不快な物語では、ストップモーション アニメーターが映画の新しいアイデアに夢中になりすぎて、疎外感や恐怖、そして最終的には危険に陥る。ストップモーション アニメーションでホラーの世界を探求するという期待は、ロバート・モーガンの映画をチェックする十分な理由だが、フランシオシの力強い演技は、ストップモーションを単なるギミックの域を超え、真に恐ろしい感情的恐怖の領域へと押し上げ、芸術とアーティストが融合して、新しく暴力的で忘れられない作品を生み出している。[マシュー・ジャクソン]
テルマ
人生で出会うすべての人に自信を持ってお勧めできる映画に出会うことは、どれほどあるでしょうか。そう多くはありません。その理由だけでも、『テルマ』は称賛に値します。それは、遊び心のあるパロディアクションや多世代にわたるキャストだけではありません。もちろん、どちらも称賛に値しますが。『テルマ』は、応援せずにはいられない愛らしい主人公が登場する、単純に楽しめる映画です。この作品の場合、主人公を演じているのが不屈の女優ジューン・スクイブ (『ネブラスカ』、その他多数 ) であることも役立っています。93 歳の彼女は、故リチャード・ラウンドトゥリー (『シャフト』本人) が長年の友人で冒険の相棒ベンを演じ、主役としてこの映画の中心をうまく担っています。電話でテルマから1万ドルをだまし取った犯人を追跡するという夢のような冒険に出て、電動スクーターでサンフェルナンドバレーを横断するこの元気いっぱいのキャラクターたちと一緒に過ごすのは楽しい。脚本、監督、編集を担当した初監督のジョシュ・マーゴリンは、テルマのキャラクターは自分の祖母をモデルにしたと語っている。テルマが見知らぬ人をずっと見覚えがあると思い込むというお決まりのギャグや、オールシニア俳優による『ANNIE/アニー』の制作でベンがダディ・ウォーバックスを演じていること、あるいは、彼らが亡くなった知り合い全員について話すときのように、笑いを誘うためではない場面など、キャラクターに深みを与える小さな工夫がたくさんある。マーゴリンは賢明にも、これらのシーンで俳優たちの邪魔をしない。彼らにスペースを与え、彼らが自由にやらせている。ある意味では、テルマはアクションのジャンルに楽しくて面白いひねりを加えた作品だ。 90 分ほどの楽しい映画です。それだけしか得られないとしても、まったく問題ありません。しかし、より深いレベルでは、人生の最終段階について重要なことを語っています。この映画は、「尊厳」や「礼儀正しさ」といった言葉を思い起こさせるかもしれません。体と心が衰え始める中で、自分の意識を維持するのがいかに難しいか、理解するよう促します。周りの年配の人たちを尊敬の念を持って見るよう促します。どのような方法でこの映画にアプローチしても、あらゆる年齢層の観客にとって素晴らしい夏のお出かけになるでしょう。[シンディ・ホワイト]
私たちは成長しました
ミンハル・ベイグ監督の傑作『We Grown Now』は、最初のショットから見る者を虜にする。誰もいない廊下(シカゴのカブリニ・グリーン住宅団地だと分かる)の静止画が、そこを探検するよう、そこに暮らす多くの人々の心を漂わせるよう、観客を誘う。私たちは、擦れる音を聞く。スニーカーがきしむ音を聞く。私たちは、2人の子供の姿を聞くとすぐに姿を現す。彼らはマットレスを運んでいる。この映像、この行動によって、ゆっくりと好奇心が掻き立てられる。そして時が経つにつれ、ベイグ監督の最新作は、独特で魅惑的な場所感覚を備えた、素晴らしい逸品としての地位をさらに確立していく。時は1992年、オープニング シーンで初めて出会う2人の少年は、親友のマリクとエリック(ブレイク・キャメロン・ジェームズとジャン・ナイト・ラミレス)で、カブリニ・グリーンを、生き生きと暮らすための広大な想像の空間にする方法を学んだ2人の黒人少年である。彼らが苦労して何段もの階段を下り、アスファルト舗装の空き地を横切り、捨てられたマットレスの隣に並べたそのマットレスは、やがて彼らにとってまた別のジャンプの手段となる。彼らが知らず知らずのうちに大切にしていた純真な子供時代へと飛び込むのだ。そのような無邪気さが『We Grown Now』の指針であり、そのタイトルは明らかに私たちを映画の結末、つまりマリクとエリックが別れを告げなければならない瞬間へと導いている。全体を通して、私たちはこの2人の少年とその家族が周囲の絶えず変化する世界を評価するのを見る。マリクのシングルマザー(心のこもったジャーニー・スモレット)は昇進し、仕事で真剣に受け止めてもらうことに苦労しているが、仕事では生活費をほとんど賄えない。エリックのシングルファーザー(地に足のついたリル・レル・ハウリー)はまだ悲しみに暮れており、手に負えない幼い息子をどう抑えるのが一番いいか分からない。おそらく彼らに必要なのは脱出方法だろう。しかし、もし彼らがカリブリ・グリーンを去るなら、それは彼らがそこで築いてきた生活にとって何を意味するのだろうか?これらの疑問、そして公営住宅、残忍な警察活動、人種差別、都市計画といったより広範な疑問に取り組むベイグの映画は、私たちが持っているもので何を作るか、そして新しい道を切り開くために必要な想像力の飛躍について、優しく瞑想している。[マヌエル・ベタンコート]