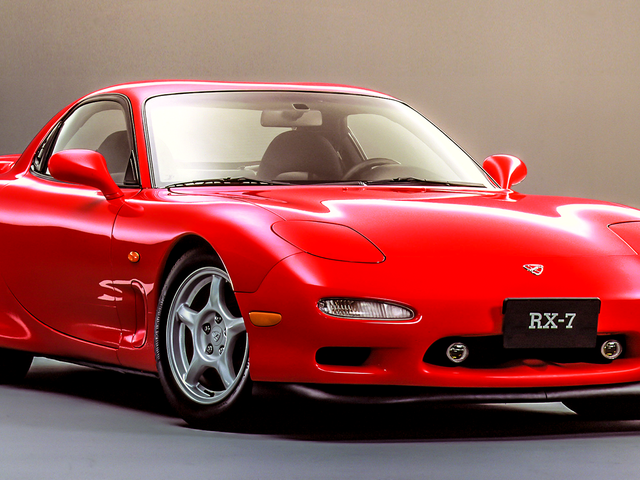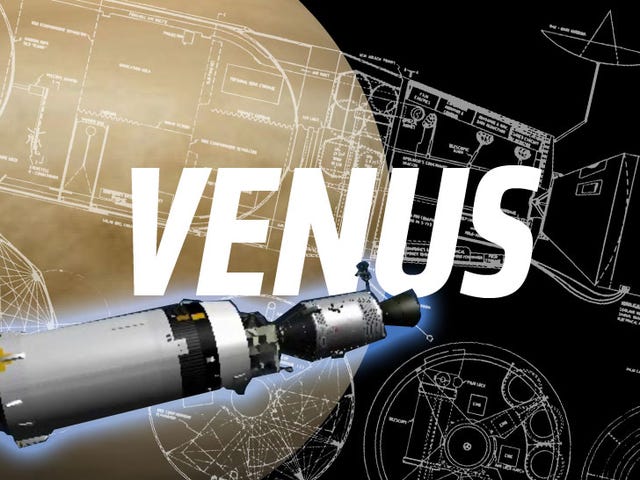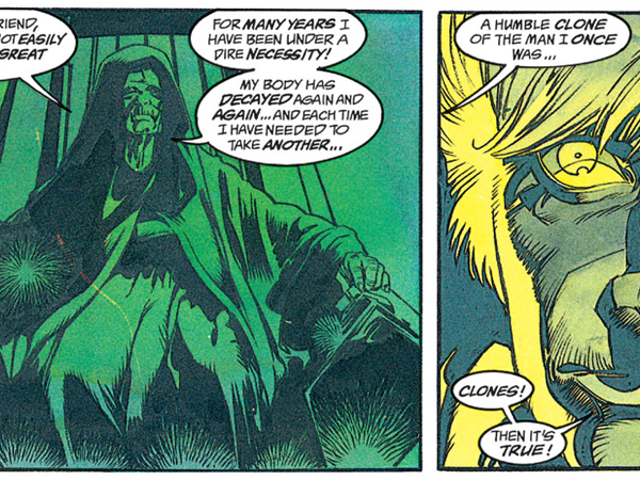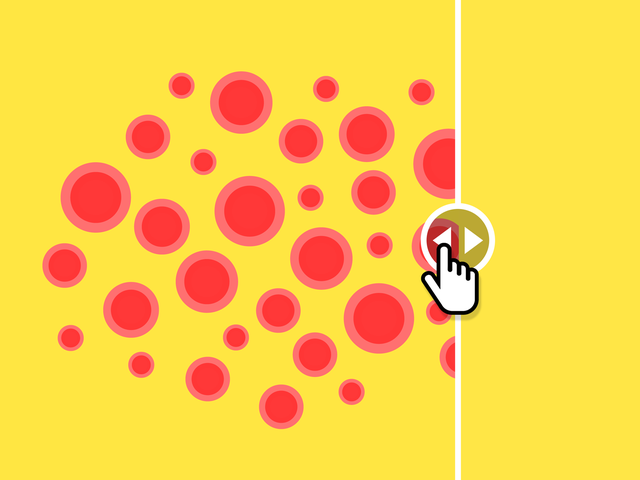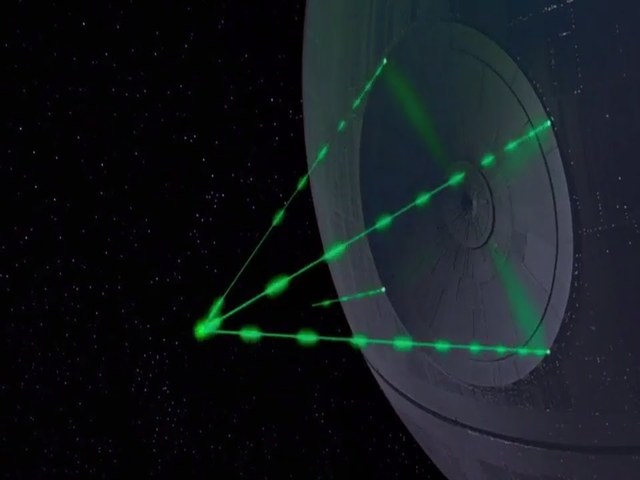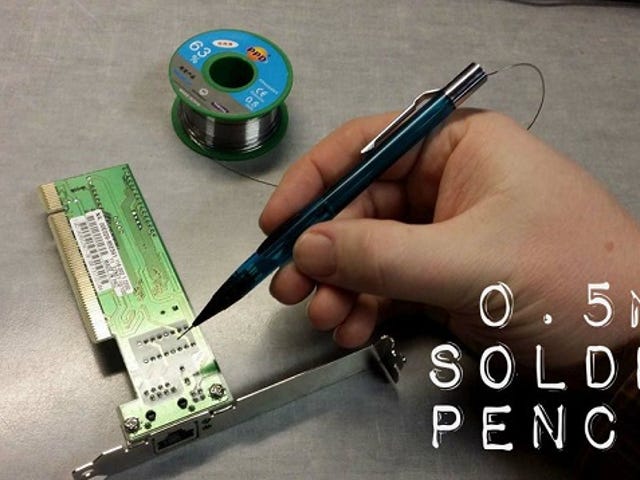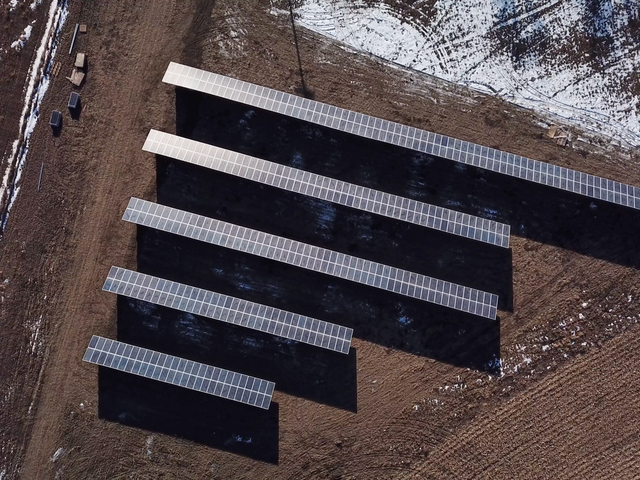『I Used To Be Funny』レビュー:レイチェル・セノットが予想通りのドラマで演技力を発揮

レイプジョークは、被害者が笑っていいと許可した場合を除いて、決して面白いものではありません。苦労して回復した後、ジョークを言った人がびしょ濡れのタオルを巻いてベッドに行き、少なくとも一度はシャワーを浴びたからと友人に褒められるというのは、かなり面白いことです。あなたの暴行を自分たちに関係したものにしようとする左翼的で家父長制に反対するタイプのボーイフレンドにユーモアを見出すのは、時には問題ありません。時には。多くの場合、これらのジョークはオチというよりは、腹に突き刺さるものです。
関連性のあるコンテンツ
「フィール・グッド」 シーズン1の 監督でインディーズミュージックビデオの人気者アリー・パンキューの長編デビュー作「I Used To Be Funny」は、緊張した表情とホッとした笑いの間の微妙な空間(前者に重点を置く)にほぼ限定して存在している。この作品は、PTSDに苦しみ何に対しても笑えないコメディアンのサムを、レイチェル・セノットが誠実に、そしてこれまでにないほど抑制して演じる。物語の大部分を占める一連のフラッシュバックを通じてわかるように、サムはかつて早熟なティーンエイジャーのブルック(オルガ・ペツァ)の乳母であり心からの友人でもあったが、悪夢のような出来事がきっかけで、大好きな仕事と幼い世話の両方を捨てざるを得なかった。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
現在、ブルックは行方不明者であり、サムは完全な緊張病より少し上の状態にあり、働くことも、2人の親友(ケイレブ・ヒーロンとサブリナ・ジェイリーズ)と暮らす家庭に貢献することもできず、ブルックの健康と安全を心配する以外、ほとんど何もすることができません。
最近のシリーズ「ベイビー・トナカイ 」や「アイ・メイ・デストロイ・ユー」と同様に、 「アイ・ユースド・トゥ・ビー・ファニー」は、暴行を受けた後の数か月の逃れようのない無感覚で説明のつかない空虚感を深く理解すると同時に、以前の作品では避けられがちな回復の側面も認める、新しいタイプの暴行証言である。自分の体を取り戻すための戦いで、生存者は愛する人を深く傷つけることがある。それは不快な真実だが、真実であり、パンキューの脚本は決してそれを否定しない。それがこの脚本の最も優れた点の 1 つである。
脚本は確かに完璧ではない。不穏な展開が続くと、ほとんど見られない。冒頭のシーンでは、最先端であろうとしてかなり残酷なセリフが出てくる(「彼女を見たと誰かに言う必要があると思う。もちろんACABだけど、クソ警察とかに」)。また、フラッシュバックの構造が軌道に乗るまでには少々時間がかかる。それでも、その結果は驚くほど心を掴む「ミステリー」となり、心底感動的なクライマックスへと盛り上がる。視聴者は予想できるかもしれないが、それでも衝撃的で緊迫感がある。
しかし、脚本はおおむね優れているものの、この作品で将来ドラマチックな役を演じる可能性を真剣に探っているセノットがいなければ、これらのハイライトはどれもこれほど高くはなかっただろう。『ボトムズ』 や『ボディーズ・ボディーズ・ボディーズ』の 俳優が大胆で突飛な役を演じられることはわかっているが、彼女はこの抑えめの形で完璧だ。彼女のコメディーセンスは、映画に頻繁に登場するスタンダップ・コメディー・シーン(ほとんどが回想シーンで、本当に面白い)に説得力を与え、また、彼女にできることとできないことを認識することで、暴行後のタイムラインで非常に重要な喪失感を深めている。ペツァも、悲しみと反抗を交互に繰り返すブルック役として堅実な演技を見せ、2人の俳優は互いに本当の相性を共有している。トラウマの部分で脇に追いやられることが多いが、メンターとメンティーの女性の友情をこれほど心を込めて描いた映画を見るのもまた新鮮だ。
残念ながら、 『I Used To Be Funny』の失敗は、パンキューがMUNAやフィービー・ブリジャーズ、その他のホットな女の子たちと親しいからこそこの映画を観るであろう観客に明らかに迎合していることから来ている。一部の人々にとって、パンキューはMUNAとブリジャーズの『But I'm A Cheerleader 』をリフした「Silk Chiffon」のビデオの監督として最もよく知られているが、この後も、おそらく彼女はそうだろう。『I Used To Be Funny』を観ながらパンキューの原点を忘れることはできない。なぜなら、この映画は、MUNA、ブリジャーズ、Big Thief、The Japanese Houseの曲をシャッフルしたSpotifyプレイリストに合わせて、10分ごとに新しい曲が流れるように感じられるからだ。これは『I Saw The TV Glow』ではない。昔のSay Yes To The Dressの知恵を借りれば、映画はサウンドトラックを着るべきであり、サウンドトラックが映画を着るべきではない。『I Used To Be Funny』は確実に着古されつつある。
この圧倒的な聴覚への執着は、ここではネタバレはしないが、この特定のアーティストグループに詳しい人なら誰でもすぐにわかるであろう、1つの大きな最後の曲につながる。実際、あまりにも明白なので、同じように予測可能な最後のシーン(カナダ版『フロリダ・プロジェクト』から直接抜粋されたようなシーン)でその最初の音が実際に流れるのを聞いたとき、この筆者は映画の全編で一番笑った。少なくとも、それはカタルシスだった。