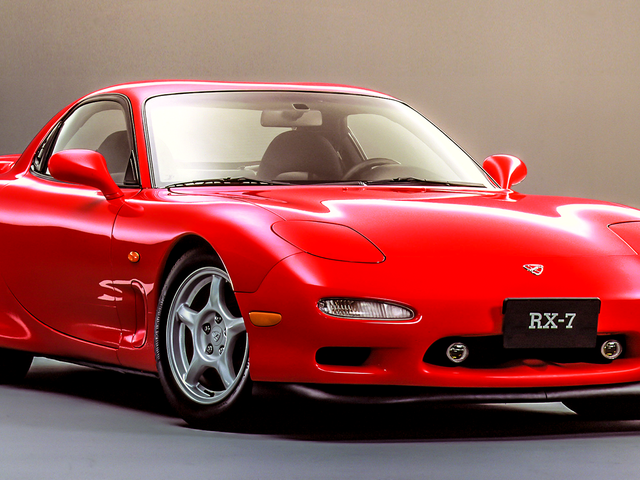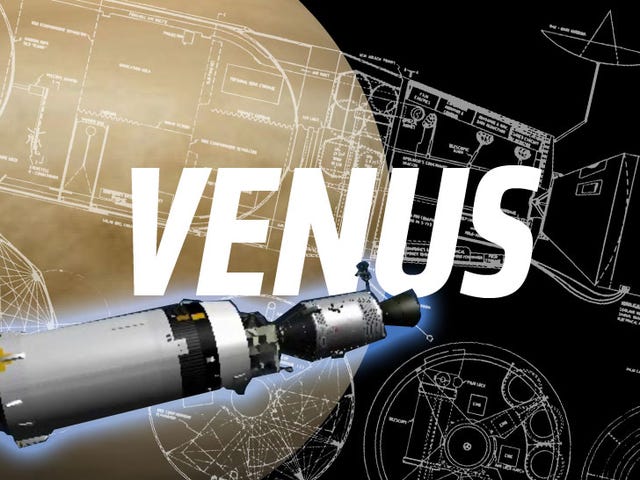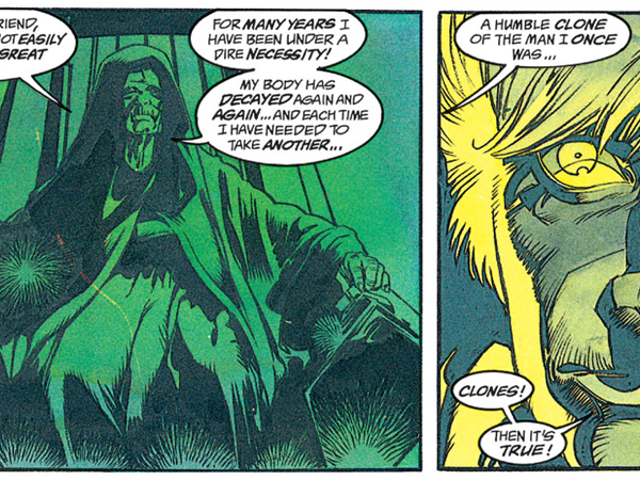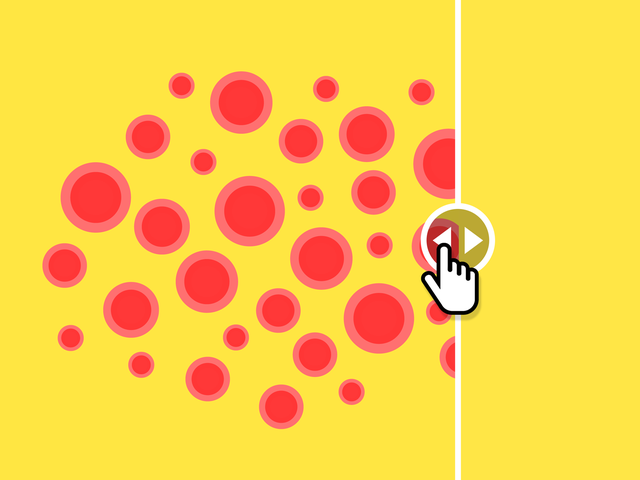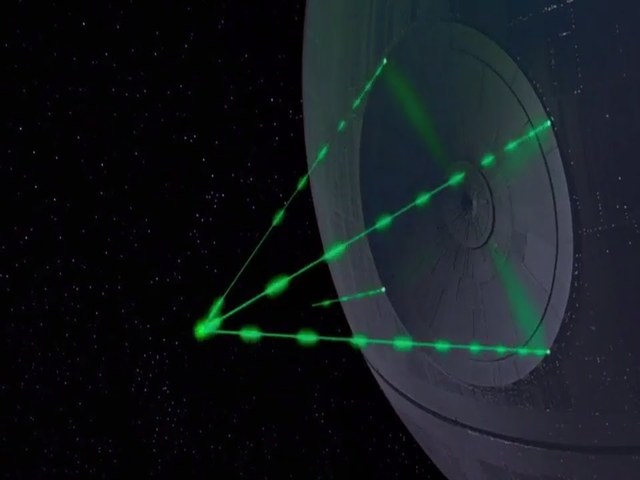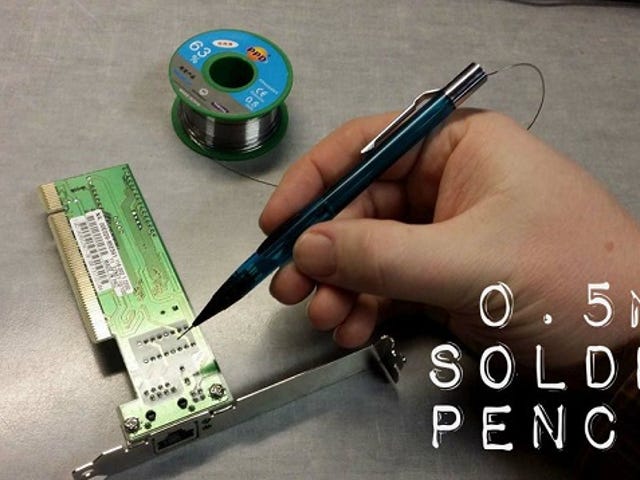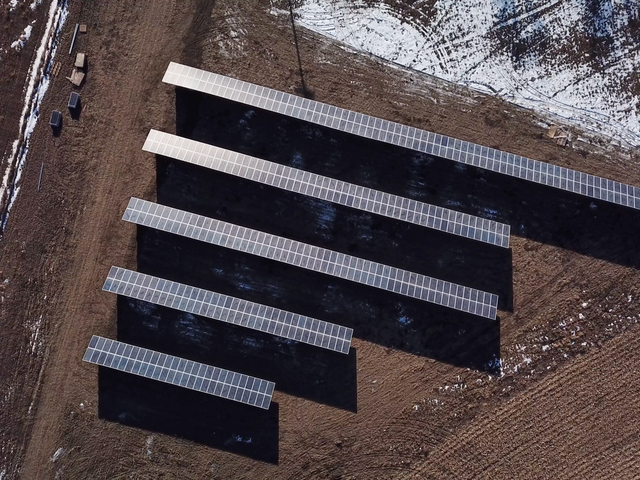ケビン・コスナーは、彼の最大のアイデアをただ一人の映画監督に託している。ケビン・コスナー
このコラムでは、できれば続編なしで、少なくとも 3 本の映画で共演した俳優と監督について書いています。この枠組みを選んだ理由の 1 つは、カメラの両側にいる多くの映画製作者が、クリエイティブな関係を探求する価値のある協力者を持っているからです。しかし、私の可能性のあるマスター リストを見ると、最も輝いているのは、惜しくも逃したスターたちです。たとえば、アル パチーノが何度も共演した有名な監督たちの中で、最も頻繁に共演しているのはバリー レビンソンだなんて信じられますか? または、トム クルーズは 7 人の監督と 2 回共演していますが、それ以上の回数共演したのはクリストファー マッカリーだけです (しかも、ほとんどが続編です)。
しかしながら、ケビン・コスナーは このカテゴリーのチャンピオンかもしれない。彼はロジャー・ドナルドソンと2度仕事をしたことがあるが、2人は、大衆向けの『ノー・ウェイ・アウト』と歴史ドラマ『サーティーン・デイズ』に続く、3作目のDC中心のスリラーではまだ再会していない。同様に、『ブル・ダーラム』と『ティン・カップ』に続くロン・シェルトン/コスナーの3作目のスポーツ映画、『シルバラード』と『ワイアット・アープ』に続くローレンス・カスダン/コスナーの3作目の西部劇があってもいいような気がするが、まだない。( 『ビッグ・チル』での死体の演技はカウントしない) 彼はマイク・バインダーの行き当たりばったりの監督の下で後期の映画を2本持っているが、 『怒りのデス・ロード』と『ブラック・オア・ホワイト』の奇妙な賛美には入らないほうがよかったのかもしれない。そして厳密に言えば、コスナーは親友でライバルでもあるケビン・レイノルズと3本の映画を作っている。『ロビン・フッド プリンス・オブ・シーブズ』と『ウォーターワールド』の前には、あまり知られていないが評価の高い、大学の男子学生クラブを舞台にしたコメディ『ファンダンゴ』があった。これは、2本の大予算の冒険映画と比べると異端の作品のように感じられる。だからといってレイノルズを失格にする理由にはならないが、同時に、これらの映画製作者たちの誰も、コスナーの最も頻繁な協力者であり、おそらく彼のお気に入りの監督であるケビン・コスナーに匹敵することはできないように思える。
ケビン・コスナーが他の誰よりも自分自身から指示を受けることが多いというのは、例えば同じく西部劇ファンのクリント・イーストウッド(ちなみに、コスナーの最も印象的な演技を監督したのはイーストウッド)のように常にカメラの後ろにいるわけではないので、なおさら注目に値する。コスナーの長編監督デビュー作『ダンス・ウィズ・ウルブズ』はアカデミー賞を受賞した大ヒット作だったが、この作品から始まった映画製作のキャリアは特に多作というわけではない。『ダンス・ウィズ・ウルブズ』から30年間で、コスナーが監督した映画はあと2本しかない。そして、デビュー作と同じく、両方とも西部劇で、コスナー自身が主演していた。しかし今、コスナーが監督する長編映画の数は100パーセントも増えようとしている。この夏、彼は『ホライゾン:アメリカン・サーガ チャプター1』で、もう一つの自ら監督した西部劇サーガを開始する。第2章は8月に続き、どうやら彼は第3章の撮影も済ませているようだが、第3章と第4章はまだゴーサインが出ていない。ジェームズ・キャメロン監督の『アバター』が『ダンス・ウィズ・ウルブズ』からいくつかの筋書きを盗用したのだとしたら、コスナーはお返しに自分の『アバター』を作ろうと決めたのかもしれない。つまり、コスナーのお気に入りのアイデアすべてをひとつの巨大なキャンバスに収めるのだ。あるいは、テレビのイエローストーンでの経験からインスピレーションを得て、テレビやテイラー・シェリダンの圧政から離れて長編西部劇を語ろうとしたのかもしれない。
いずれにせよ、最初のホライゾンが公開された時点で、コスナーは監督としてのキャリアが、少なくとも彼が言うところの、一つの作品に支配されようとしている瀬戸際に立っている。パート 1 が公開されるのは、コスナーとコスナーのコラボレーションを振り返るには奇妙なタイミングのように思えるかもしれないが、公開されているのは 3 時間のホライゾン1 本だけなので、これは 1 本の長編超大作が彼のフィルモグラフィーの大半を占める前の最後の瞬間なのかもしれない。

長い間、その支配的な大作は『ダンス・ウィズ・ウルブズ』だっただろう。コスナーが『ポストマン』や『オープン・レンジ』を制作した後も、 『ダンス・ウィズ・ウルブズ』は彼の最も有名で、ある意味悪名高い作品であり続けた。それは『ポストマン』の無駄遣いとは別の種類の悪名であり、成功した映画に対してのみ抱かれる類の恨みである。1990年当時、 『プリティウーマン』や『ゴースト』など1990年の他の大ヒット作に匹敵する莫大な興行収入を記録していたとき、コスナーの監督デビュー作がアカデミー賞の最優秀作品賞と最優秀監督賞に選ばれるのは当然だった。 (同じくノミネートされた『ゴースト』と比べると、アートハウス映画に選ばれたようにさえ見える。)しかし時が経つにつれ、多くの人が『グッドフェローズ』やマーティン・スコセッシを抑えての勝利に憤慨するようになり、アカデミーが『マーティ』に追い上げを提供する15年も前にコスナーがトロフィーを獲得したことに不満を言うのがほとんど決まり文句になった。
その結果、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』は、まあ「過小評価されている」というのは言い過ぎかもしれないが、ある意味では過小評価されている作品となった。もちろん、『グッドフェローズ』には遠く及ばない。そして、後期スコセッシの自己満足的と言われる上映時間を批判する人(マーベリックスファンでもそうでなくても)は、コスナー監督作品ならどれでも見るように命じられるべきだ。彼の3時間は、スコセッシの他の長編映画のようにあっという間に過ぎることはない。しかし、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』のスローさは、その長所の1つだ。監督のコスナーは、俳優のコスナーに、ジョン・ダンバーという役柄に浸る時間を与えている。ダンバーは、遠く離れた軍事基地で単独の仕事を任され、最終的にラコタ族と親しくなる北軍兵士である。これはゆったりとした、筋書きの少ない西部劇であり、意図的に白人男性の視点を中心に据えているとしても、基本的な要素を使って非伝統的で進歩的ですらあることをしようとしていることは確かだ。不完全ではあるものの、この映画は、同じくオスカーを受賞した『許されざる者』と同様に、西部劇の比喩を大胆に検証している。俳優として、コスナーは『ダンス・ウィズ・ウルブズ』に出演したが、それは誰もが羨むほどの好調期の真っ最中だった。この映画の一方では『ノー・ウェイ・アウト』、『アンタッチャブル』、『ブル・ダーラム』、『フィールド・オブ・ドリームス』があり、もう一方では『ロビン・フッド』、『JFK』、『ボディガード』(ひどい映画だが大ヒット)、『パーフェクト・ワールド』(ヒットではないが素晴らしい映画)があった。しかし、ダンバー役で彼が演じる孤独な幻滅と最終的な悟りは、彼が演じてきたカリスマ性のある真面目な役や、より無礼だが内心は誠実な半悪党の役とは明らかに異なる。コスナーは、他の役とは違う役を自らに与えたのだ。
このパターンは『ウルブズ』後の監督作品にも引き継がれているようだ。俳優兼監督としての彼のキャリアは、無愛想な西部劇のヒーローを取り巻く筋書きの仕組みをほぼ真似している。それは、他の誰もやらないから、あるいはむしろ、他の誰もきちんとやっていないから、俳優が自分でやる必要があるという状況から生まれたもので、その仕事に対する彼の男らしい受け入れ方に、健全なエゴが加わっている。
もっと単刀直入に言えば、『ウルブズ』以降の彼のプロジェクトは、彼のキャリアにおける当時の最近の他の転機に対する反応として、様々なレベルの怒りを伴って読むのは簡単だ。例えば、『ポストマン』は、 『ロビン・フッド:プリンス・オブ・シーブス』や『ウォーターワールド』の撮影現場で醸成された不満や対立、そしておそらくそれらの公開を歓迎した過去のロビン・フッドや『マッドマックス』シリーズとの必然的な否定的な比較に対するコスナーの答えのように感じられる。おそらく『プリンス・オブ・シーブス』の問題はコスナーの不十分な英国らしさではなく、物語の不十分な米国らしさであり、おそらく(コスナーが珍しくぶっきらぼうな役を演じる)『ウォーターワールド』はマッドマックス風に意地悪すぎ、希望に欠けすぎていた。少なくとも、それは『ポストマン』のアメリカにおける終末論的な世界観を説明する一つの理論だ。この映画では、崩壊しテクノロジーのない未来のアメリカが、コスナー演じる無名の人物(当初は放浪する俳優として登場する)が米国郵政公社を急遽再起動させることで、再び希望を持ち始める。

それに比べれば『オープン・レンジ』ははるかに控えめな作品で、コスナーとロバート・デュヴァルが牛飼い役を演じ、彼らの放し飼い生活を嫌う冷酷な町長と対決する。また、これはコスナーが『パーフェクトワールド』の前年に西部劇からほぼ引退していたクリント・イーストウッドの下で働いたときには作らなかったような昔ながらの西部劇であり、俳優としての最大の失敗作、具体的には『グレイスランドまで3000マイル』の軽妙で準ヒップな犯罪映画バイオレンス映画の後の軌道修正でもあると解釈するのも簡単だ。最後に、過去10年以上にわたって、コスナーは多くの指導者や父親のような役を演じてきた。そのため、 『ホライゾン』の前半は、誰かが許せば、これらの年配のキャラクターもより強いアクションマンになれると主張する修正版のように感じられる。
実際、『ホライゾン』は、コスナーがさまざまなことを自分の手でやっているように感じられるが、いつもうまくいっているわけではない。約 40 人の主要なセリフを話す役の、その驚くべき (そしてしばしばまったく混乱させる!) アンサンブルは、ストリーミング TV シリーズのショーバイブルとしてすぐに使えるように思われ、まるで彼が『イエローストーン』を上回ろうとしているかのようだ。一方、始まりから中盤、終わりまで独自のストーリーとして独立することをまったく拒否する、狂気の沙汰に近い姿勢は、過去 20 年間のアメリカのスタジオ映画製作の大半を支配してきた映画シリーズのコスナー版のように感じられる。コスナーが自ら監督した他の作品では彼のキャラクターに焦点が当てられる傾向があるが、この作品にははるかに多くのキャラクターとストーリーの筋書きがあり、自己修正の可能性がある。
『ホライゾン:アメリカン・サーガ 第1章』では、ヘイズ・エリソン(コスナー)は、上映時間180分の映画の1時間経過するまで登場せず、他の誰もがそうであるように、映画の壮大で不可解な登場人物の入れ替わりの中で見失われがちである。その寛大な精神により、この空想的な虚栄心のプロジェクトは、コスナーが自らを高貴だが最終的には抗えない寡黙なカウボーイとして演じ、数十年も年下の女性が性的至福へと乗り込んでくる(もちろん、彼の最初の高貴な抵抗にもかかわらず)映画としては、少なくとも可能な限り、彼の最もエゴのない取り組みとなっている。(義務的に取引的なコスナーのセックスは、『ポストマン』にも登場するが、 『ノー・ウェイ・アウト』や『ブル・ダーラム』の純粋な肉欲とは程遠い。)
ホライゾンの最初の章は、コスナーが自分の作品の細部を最もコントロールできていないように思える映画でもある。クロスカッティングはリズムがなく、サブプロットを明確にするどころか混乱を招いている。彼が共同執筆した脚本のセリフには、明らかな時代錯誤がいくつも盛り込まれている(19世紀半ばの入植者が「本当?」や「大丈夫?」といったテレビ用語の創始者でない限り)。そして、上映時間が長いにもかかわらず、ストーリーラインの多くは切り詰められているように感じる。私はいまだに、最も基本的な言葉でさえ、そのプロットをどう要約していいのかよくわからない。 ホライゾンという小さな町があり、安い土地を約束する不気味なチラシで入植者を誘い込んでいる。先住民の一派によって破壊され、いくつかのサブプロット(崩壊した家族の残党が北軍の前哨基地に居を構える、入植者の一団が復讐を企てる)が動き出すが、必ずしも他のサブプロット(幌馬車隊が西に向かう、ヘイズ・エリソンが女性とその友人の幼児を守る)は動かない。まるで、コスナーが、これまでのキャリアでさまざまなタイプの西部劇、トレンド、一貫したテーマに興味を抱き、いくつかの個別の映画を作るのではなく、それらをすべて一度に作ろうと決めたかのようだ。
それでも、『ホライゾン』には、実際の中心や点を見つけるよりもずっと簡単に見つけられる楽しみがまだある。ザック・スナイダーの『レベル・ムーン』の第 1 部のように、この作品には、愛らしく奇妙なキャラクターが尽きることなく登場し、巧みに作られ、よく撮影されたシーンが数多く登場する。個々の葛藤はくすぶっているが、映画全体としてはもがいている。悪い映画ではないが、奇妙で満足のいくものではない。実際、コスナーの監督作品はどれも、少なくともそこそこ面白い。最も悪名高い『ポストマン』でさえそうだ。いや、 『プリンス・オブ・シーブス』や『ウォーターワールド』ほど楽しくはなく、映画スターの救世主的傾向がより露骨になっているが、そのアメリカらしい堅苦しさには魅力がある。同様に、『オープン・レンジ』は彼の最も単純で直接的な西部劇への回帰娯楽作品であるが、140分という長大な上映時間というコスナーの肥大化は避けられない。これには利点もある。例えば、映画のクライマックスの銃撃戦は、『許されざる者』以降の波瀾万丈の西部劇の歴史の中でも優れたシーンのひとつだ。しかし、この映画の1952年版がこれほど長いとは想像しがたいため、懐古的なムードも薄れてしまう。しかし、コスナーの昔ながらの興行師としての本能が、彼の甘ったるい主張と切り離せないものだとすれば、少なくとも彼は、例えばローレンス・カスダンの『ワイアット・アープ』のように退屈な映画で自ら監督したことはない。この3時間の西部劇を見れば、コスナーがこの映画に信念を抱いた理由がわかるし、それに比べれば『オープン・レンジ』があっさりしているように見えるのも当然だ。

同時に、コスナーが自分の最高の演技にあまりこだわっていないことも注目に値する。『ダンス・ウィズ・ウルブズ』はそれに近いが、ダンバー役の演技は繊細で効果的ではあるものの、 『ブル・ダーラム』や『JFK』に比べるとやや見劣りする。彼のフィルモグラフィーの最高傑作のほとんどを含むその時代全体を別としても、ネオウエスタンの『レット・ヒム・ゴー』であれ、まったくの駄作の『クリミナル』であれ、コスナーは他の人が作った多くの映画で、より過激で興味深い演技をしている。『クリミナル』は、最悪の団塊世代の行動でさえもその世代の後継者に打ち勝つという奇妙で入り組んだファンタジーだ。それらの役で必ずしももっと上手くやろうと挑戦することなく、英雄的なカウボーイの偉業に自分を向けるのは、究極のエゴの表れなのだろうか。『ホライゾン』はおそらくそうではないことを示唆している。この映画は、観客が彼のトレードマークであるカウボーイ風の口ひげを一目見ることなく暴動を起こすだろうという想定の下で作られたわけではない
いや、コスナー/コスナーの映画に共通しているのは、スター(や他の俳優たち)を、そうでなければ到達不可能に思えるほど広大な風景の中に没入させようとする献身的な姿勢だ。彼の映画は、昔ながらの105分間の西部劇の展開を夢中で観るようなものではなく、むしろ時間があらゆる方向に広がる長い夢想、終わることのないMeTVマラソンに近い。『ダンス・ウィズ・ウルブズ』は、この壮大さを、他の多くの映画が漫画のような簡潔な表現に変えてしまった先住民と入植者の力関係についての思慮深い瞑想として受け止めることができたかもしれない。しかし、『ホライゾン』に到達する頃には、コスナーのビジョンは扱いにくくなっているが、それでも奇妙に説得力がある。「彼は彼らの過去の記憶を回復させる」と『ポストマン』の予告編は約束している。コスナーのキャラクターが米国郵政公社の伝統を守ることで社会秩序を回復する様子を語っているが、俳優/監督の使命宣言のようにも聞こえる。コスナーは実際の過去を復元しているわけではなく、必ずしも過去をロマンチックに描いているわけでもない(少なくとも、ロマンチックに描いているだけではない)。どんなことがあっても、あの感情を復元しているのだ(現代の問題により深く関わっているネオウエスタン映画をひとつ挙げる)。コスナーのスターとしてのペルソナは、かつては特に、おそらくは戦略的に、ゲイリー・クーパーを彷彿とさせる雰囲気に依存していた。しかし、彼が自ら監督した映画を見ると、その雰囲気だけでは十分ではなかったことがますます明らかになっている。80年代や90年代初期と彼を結びつける、より現代的なものは、邪魔になっていたのかもしれない。ホライゾンは、コスナーが俳優として、また監督として、この仕事は、どれだけ力を注いでも、ますます大きくなる使命だと考えていることを示唆している。