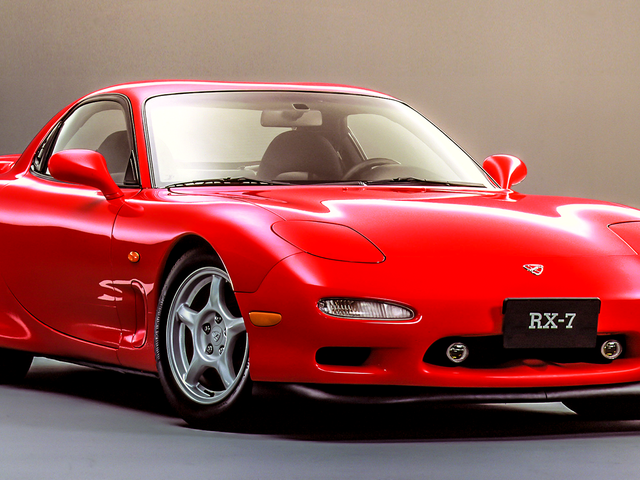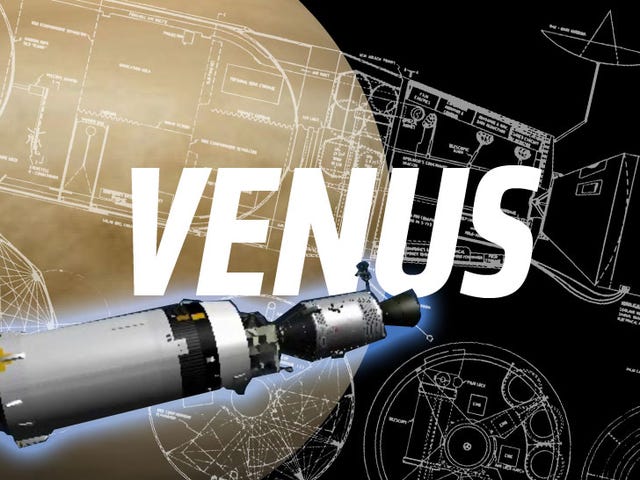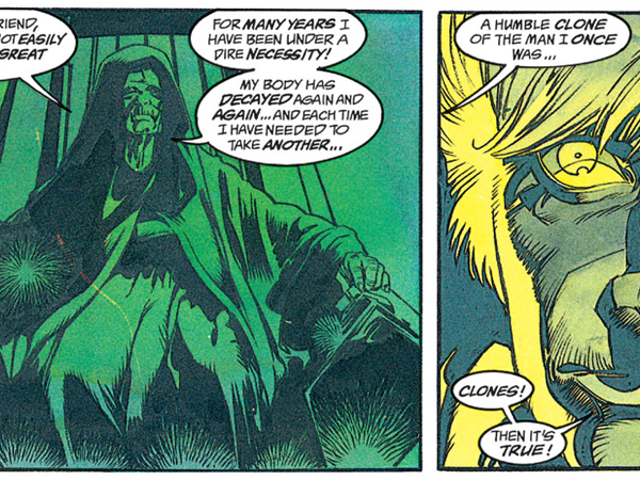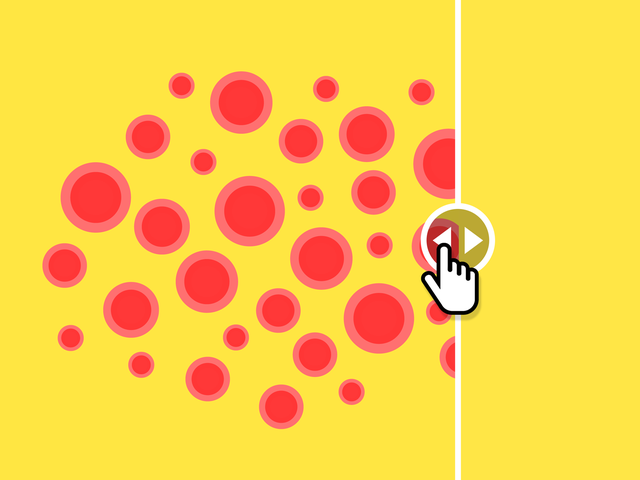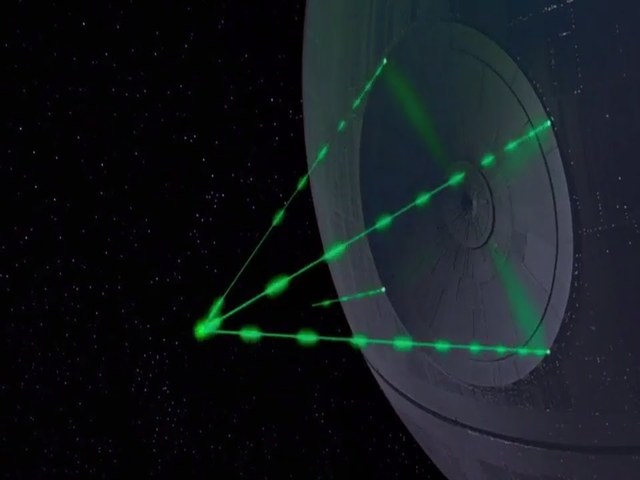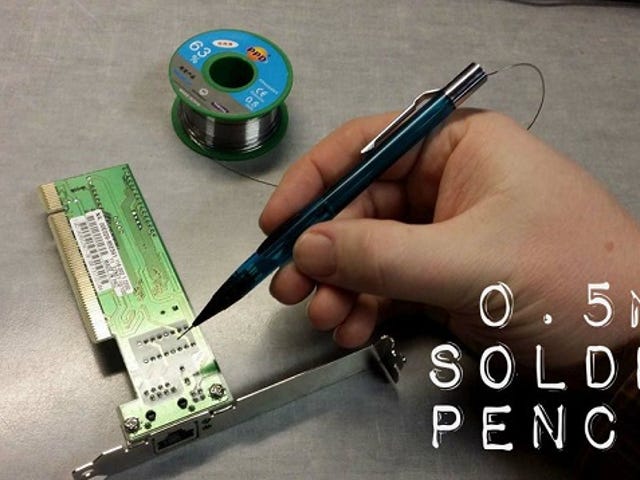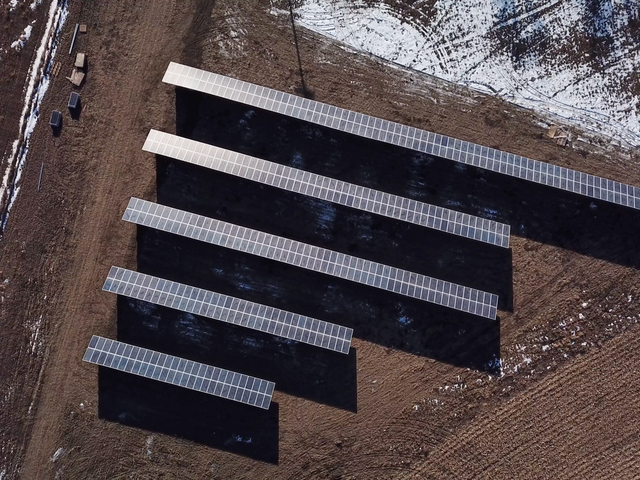『クワイエット・プレイス』初日レビュー:軽いタッチで描かれたニューヨークの悲劇

『クワイエット・プレイス 1 日目』のいたるところで行われているマーケティング キャンペーンは、この映画を説明する上で問題を引き起こしますが、特定のストーリー展開を隠したり明らかにしたりするからではありません。大まかに言えば、厳密にストーリー レベルで言えば、この映画は宣伝どおりです。サム (ルピタ・ニョンゴ) は、おそらく地球上で最も騒々しい場所の称号を争うであろうにぎやかな大都市ニューヨーク市にいます。その惑星は、モダン ホラーの古典『クワイエット プレイス』に出てくる、虫のいる超聴覚を持つモンスターに侵略され (この出来事は、モダン ホラー、ああ、映画『 クワイエット プレイス Part II』 の小さな町での回想で垣間見られます)、彼女は突然の終末を忍び足で進んでいかなければなりません。この前編の広告では、ニョンゴのキャラクターに関する基本的な詳細が明かされていないが、これは驚きを残すためというより、カチカチと鳴るモンスターが襲い掛かろうとする中、カリスマ性があり、おそらくは資格過剰と思われる俳優たちが、恐怖で叫び声をこらえようと自分の口を覆うというシリーズのお決まりのパターンに従うためだろう。
それでも、映画の冒頭数分で明らかになる情報を、潜在的なネタバレとして扱いたくなる気持ちは変わらない。こうした舞台設定の詳細は、『クワイエット・プレイス 1 日目』を興味深いものにしていると同時に、それらを省略した繰り返し再生される予告編というまったくの偶然によって、有能で効率的な続編のようなパート IIからその目新しさを見逃した観客に本物の発見の感覚を生み出す可能性もある。とはいえ、こうした詳細にこだわりすぎると、本質的にはよく練られたジャンルの演習であり、その中心には驚くほど強力なキャラクター主導の親密感がある映画にとって、その重要性を過大評価してしまうことになるかもしれない。
関連性のあるコンテンツ
関連性のあるコンテンツ
では、妥協して、少なくともこの段落の残りの部分では要約レベルにとどめましょう。その後、設定が明らかになります。以下は予告編のみの要点です。避けられないクワイエット・プレイスの特徴にもかかわらず、そして、明らかにテンプレート化されたフランチャイズに、枠内で色を付ける練習として、インディーズセンセーション(この場合は、ピッグの 脚本家兼監督のマイケル・サーノスキー)を持ち込むという決まり文句にもかかわらず、デイ・ワンは独自の(クリック感のある)作品であり、ジョン・クラシンスキーの家族中心の物語2つとは一線を画しながらも、その心の広さに沿っています。これは、徹底的に破壊されるニューヨークの街路を心から評価するニューヨーク災害映画です(ロンドンで撮影されたにもかかわらず)。
これは、麻痺した女性が恐怖に駆られて生きる意志を取り戻すスリラー映画『クワイエット・プレイス 1 日目』が、どのような作品になるかを考えると、なおさら印象的だ。この古臭い比喩の要素が物語を左右する。なぜなら、サムは市外のホスピス介護施設で暮らしており、不特定の末期疾患のため、理論上は余命数ヶ月しかないことが、私たちがかなり早い段階で知るからだ。彼女には近しい家族や友人がいないようだ。彼女は施設への日帰り旅行でマンハッタンに来ており、災害後も、彼女がどこへ行くにも信じられないほどだが愛らしく連れている精神的な支えとなる猫を除いて、彼女の健康を心配するような人は誰もいないようだ。最初の攻撃の後、サムは、救助に来るはずのボートにたどり着こうとする市民たちの熱意を共有していない。それは、ニョンゴがパニックに陥った群衆をかき分けて交通の反対方向に向かう唯一の人物である、印象的(そして非常にニューヨーク的)なショットで示されている。
視聴者の中には、たとえ一瞬でも『メランコリア』を思い浮かべる人もいるかもしれない。この映画では、臨床的に鬱病を患う女性だけが、迫りくる世界の終末に本当に備えていた。サルノスキーはそこまで終末論的な比喩には踏み込まないが、街は9/11のような塵で覆われる。(スピルバーグの『宇宙戦争』は、一世代前の実際の災害映画に、より恐ろしく、より直接的にぞっとするようなオマージュを捧げた。)その代わりに、サムは、逃げ惑う生存者志望者のほとんどとは異なる目標を追求する。それは不条理な(そして死ぬほどかわいらしい)インディーズコメディの題材にもなり得た目標だが、サルノスキーはそれを控えめだがグルメに近い情熱で吹き込んでいる。
やがてサムは、街で同じように孤独に見え、パニック発作、より広範な不安、あるいは、耳の届く範囲で人間を体当たりで致命傷を与える(あるいは飲み込む?忘れがちだが)略奪するエイリアンに対する通常の反応など、何らかの不明の病気を患っているイギリス人のエリック(ジョセフ・クイン)と出会う。それほど重要ではないが、彼女はまた、生き残って『クワイエット・プレイス Part II』を観ることになるアンリ(ジャイモン・フンスー)とも交わる。サスペンスに満ちたセットピースのための休止があり(『Save the Cat』のような文字通りの作品がこれほど比較的自然に感じられるとは誰が想像しただろうか?)、そして、体験的に現実的で、画面上で解析するのが簡単な、今何が起きているのかという混沌を受け入れているサルノスキーから、あるシーケンスが逃げていく。雑用といえば、この批評家のような我慢できないほど細かいことにこだわるニューヨーカーは、この映画がスタート地点からサムの目的地まで、街中を何ブロックも移動していることにも気づくだろう。それでも、この映画は、クローバーフィールドのようなモンスター映画の大混乱の地上レベルの光景を、ぶれたカメラの後ろからうるさく言うことなく届けてくれる。
『クワイエット・プレイス 1 日目』におけるサルノスキーの真の功績は、おしゃべりがないこと、つまり静けさをどう演出するかということである。もちろんクラシンスキーの映画にもこれはあったが、家族間の沈黙の速記は、孤独を実感して苦闘する見知らぬ二人の間のためらいがちなコミュニケーションとはかけ離れている。世界で最も表現力豊かな絶叫クイーンとしても活躍する名女優ニョンゴは、サムの悲しみのニュアンス、受け入れることと生きるために戦うことの間での綱引きを見事に演じている。サルノスキーのカメラは、まだ流れている水を一時的な隠れ場所として使うために小さな噴水の真ん中に賢く必死に陣取った二人の子供たちのような、心に残るイメージに長く留まる。彼は、この類のエイリアンの攻撃がどのようなものなのか心から興味を持っているようで、そこから可能な限りの恐怖を引き出すことに関心があるわけではない。彼は大規模な広告攻勢のために素材を提供し、さらに自分のためにも『Quiet』を残しておいた。