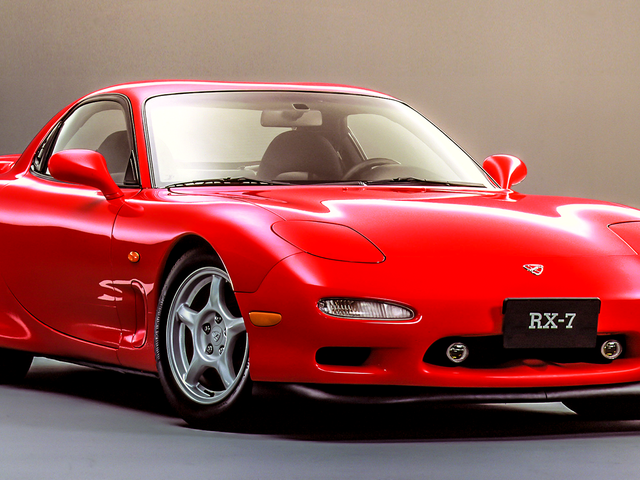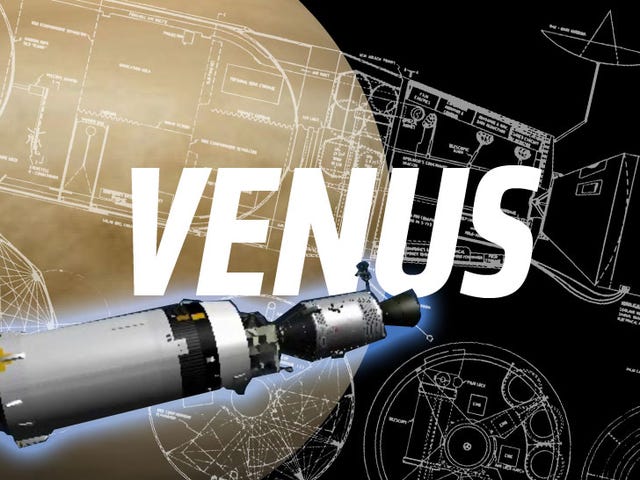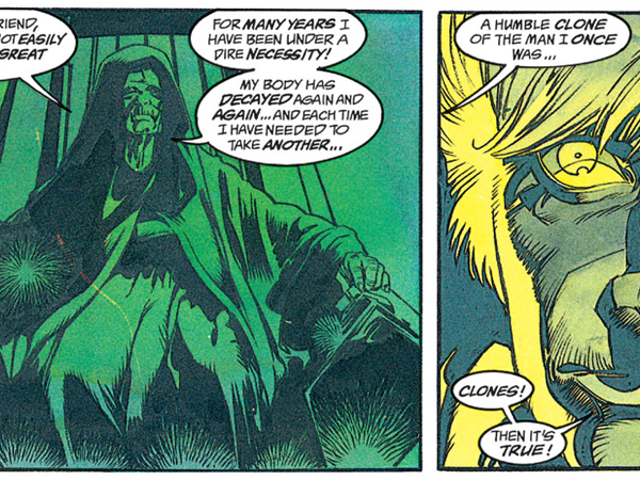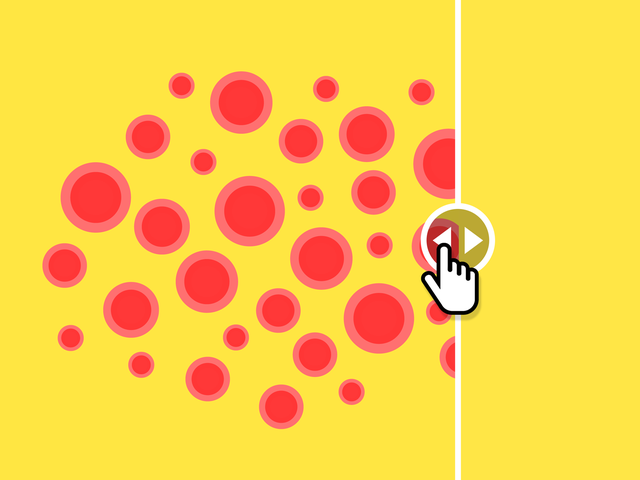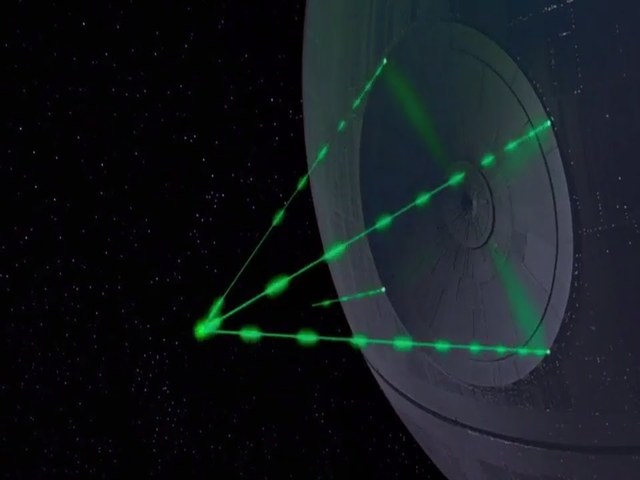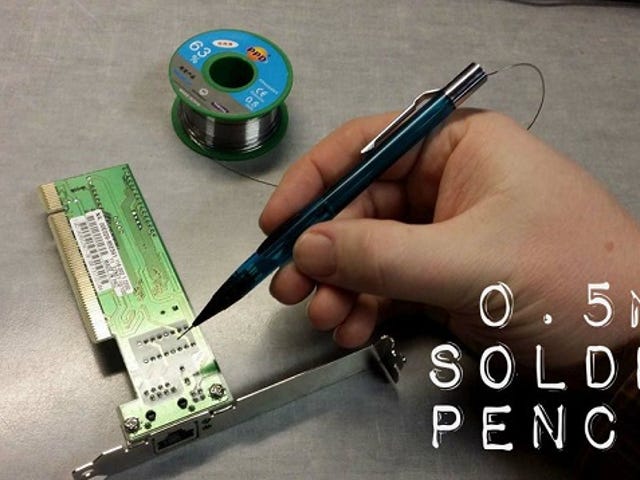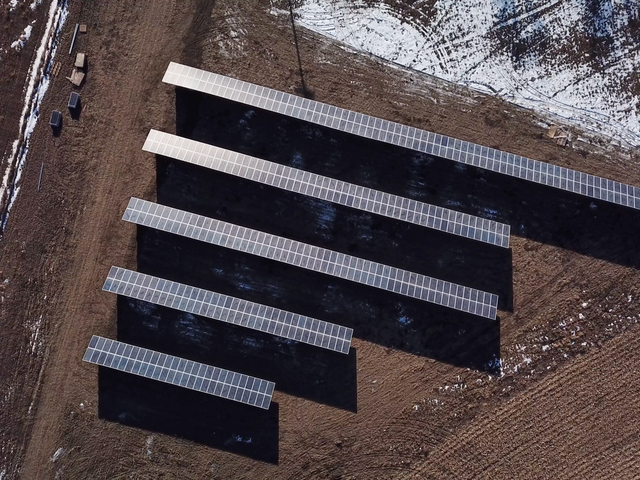マッドマックスの世界は終わりを告げ、登場人物たちは救いへと向かっていく

AV Club は、「Run The Series」で映画シリーズを調査し、新作ごとにどのように変化し進化していくかを研究しています。
関連性のあるコンテンツ
ジョージ・ミラー監督はこれまで二度、カーチェイス映画の最後を飾るカーチェイス映画を製作した。また、前述の映画からどれだけ多くのシーンを切り離し、明確に区別できるかにもよるが、少なくとも四、五回はカーチェイスシーンをすべてのカーチェイスシーンの最後を飾るカーチェイスシーンを製作している。カーチェイス映画とカーチェイスシーンは、もちろん実際には終わることがない。ミラー監督ですら、それらを放っておけない。彼の新作『フュリオサ』は 『マッドマックス』シリーズの第五作にして初の前編であり、マックス・ロカタンスキーが主役でない初の作品でもあるが、前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のようなノンストップの追跡とバトルロワイヤルにはならないことが映画の中でずっと確立されていた後、映画の途中に史上最大級の乗り物のセットピースが挿入されている。実際、『フュリオサ』の大部分は『怒りのデス・ロード』 よりもスローで、陰謀的で、計画的である。しかし、ミラーのワイルドな世界で、エンジンの回転音を中心に展開しない映画を作るのは簡単だ。これらの映画の無数の登場人物、環境、状況は想像力を刺激するものだ。それでも、登場人物は結局、車の中に引き戻される。これは、このシリーズの特徴であり、また、自然な衝動のようにも感じられる。未来は、単に、自らを制御できないのだ。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
過去も現在も『猿の惑星』シリーズが終末を巡り続け、たまにそれを引き起こすにとどまっているのに対し、『マッドマックス』シリーズは終末と終末後の世界の境界線を曖昧にし、広げている。終末後の世界では、社会崩壊の犠牲者はリセットして新しい現状を再構築する機会が決してない。特に2作目と3作目の結末で示唆されているように、登場人物が世界のより良い場所にたどり着くたびに、次の映画が再び荒地に戻る前に、私たちはほんの少しだけその光景を見るか、数行のナレーションを聞くだけだ。なぜなら、地獄のような世界であっても、世界が少しずつ悪化する余地がまだあるからだ。私がオリジナルの『マッドマックス』(1979年)を初めて見たとき、特に続編も見ていた私は、これを崩壊寸前の社会の詳細を捉えた終末期の映画だと捉えていただろう。今では、5 本の映画 (およびさらに 10 年間の現実世界の出来事) が完結したので、そうは思えません。

いや、マッドマックスの世界は、翌年アメリカで『マッドマックス2』 (1981年)の頃ほど無秩序ではない。服装はそれほど奇抜ではなく、放浪する犯罪集団は、より合理的ではないにしても、人生や服装において、目標や野望がやや抑制されているように見える。しかし、ここで描かれる社会は(アメリカの観客が「終末的な狂気か、オーストラリアの奇癖か?」という短いゲームをした後)、最初から本当に不安定な感じがする。たとえ誰もがまだ荒野に絶望して暮らしているわけではないとしても、本物の、認識できる権威の面影はほとんどない。終末は本当に起こっていないのか、それともまだすべての人に平等に及んでいないだけなのか?
こうした状況は、奇妙にも第 1 作の安っぽさの一部を正当化している。猛スピードで進むオープニングとエンディングのシーケンスの合間に、マックスはメイン フォース パトロール隊と一緒にいるには疲れ果てすぎているかどうかについて、なんとなくためらっている (メイン フォース パトロール隊も革の装備を身に着けており、まるで来たるべき終末に屈服する前か、スーパーヒーローが存在感を維持しようと努めるように、自分たちのコスチュームをリブートしているかのようだ)。まるで、妻と幼い子供の悲劇的な死が彼を限界まで追い込み、それが彼が終末計画に同調するきっかけとなるまで、時間をつぶしているかのようであるが、彼は、それがすべて避けられないこと (私たちの中に誰がいるかなど) に気づいていない。『マッドマックス 2』では、別のキャラクターがマックスを「旧世界の死体で生きている」と軽蔑的に表現しているが、それは第 1 作では、誰にも思い浮かばないうちに、より真実味を帯び、より悲劇的に思える。

『マッドマックス2』以降、シリーズはより反復的になる。年代順に言えば、各作品は未来が次第に悪化していく様子を示している。物語的には、どの映画も互いに意味を成すために特に互いを必要としない。『マッドマックス2』は、シリーズで最も明示的な世界情勢の定期的な総括(戦争が燃料不足を引き起こし、それが崩壊につながった)で始まり、そこから、後続の映画を通して以前の時代についての詳細はほとんど明らかにならない。代わりに、私たちは終末的な現在について、あるいは『フュリオサ』では、世界の残りの部分がどれだけ残っているかによって、世界を変えるか非常にローカルな最近の歴史について、より多くを知ることになる。いずれにせよ、すべてが混ざり合っている。後の作品が最初の3作との関係でいつ設定されているのか、誰にも分からない。『フュリオサ』(何年もかけて描かれる)が『マッドマックス サンダードーム』(1985年)と『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015年)の間のギャップを埋めると言うのは簡単だが、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』でのマックスの見かけの年齢に基づくと、 『マッドマックスサンダードーム』はおそらく第4作よりも15年も前に設定されているわけではないだろう。
あるいは、荒野では時間の流れが異なり、シリーズの登場人物や俳優が自由に姿を消したり再登場したりできるのかもしれない。メル・ギブソンが『フューリー・ロード』で当然ながら再演されたこと(タイムライン上の論理的理由と現実世界の実用的理由の両方による)は別としても、このシリーズには、厳密には続編とは言えない奇妙な反響や繰り返しがある。
『007 ロード・ウォリアー』では、ブルース・スペンスは終末後の部族のリーダーとなるジャイロスコープ・パイロットを演じている。『サンダードーム』では、彼は似ているようで違うパイロットとして戻ってきて、マックスの車を盗み、最終的には愛らしい子供たちのグループを自由に飛ばす。これだけで、これは『007 ロード・ウォリアー』の素材を焼き直したサンダードームと片付けられるかもしれないが、大部分でそれはいくつかの新しい方向に進んでいる。さらに、夢のような再キャストは『フューリー・ロード』のモチーフになり、明らかに異なるマックスを登場させ、マッドマックスで悪役のトゥーカッターを演じたヒュー・キース=バーンを、より巨大な水とガスを扱う暴君イモータン・ジョーの体現に再利用している。トム・ハーディ演じるマックスは、前作の終盤のギブソン版よりもさらに悩まされているようで、低くぶつぶつ言うような声(おそらく吹き替え?)は、彼の身をよじらせる肉体から切り離されているように感じられる。その後、 『フューリー・ロード』の主要人物数名が『フュリオサ』で再キャストされ、アニヤ・テイラー=ジョイがタイトルキャラクターの若い頃を演じ、レイチー・ハルムがイモータン・ジョーを演じている。(キース=バーンは『フュリオサ』の製作前に亡くなっているが、それでもこの再キャストはミラーの美学に合っている。)
この文脈では、トゥーカッター、フュリオサ、ドゥーフ・ウォリアー、アンティ・エンティティ、ロード・ヒューマンガス、ピス・ボーイ、ディメンタスなど、それら派手なキャラクター名は、単なるダークな気まぐれの飛翔のようには感じられない。ウェイストランドの誰もが、比喩的に言えば、必要に迫られて自力で成功した男であり、時には戦略的なブランド変更を伴う。たとえそれが自分自身のグロテスクな部分を受け入れることも意味するとしても。『マッドマックス サンダードーム』で、文字通り「豚殺し」の烙印を押された男(ロバート・グラブ)を見てみよう。それは恥の烙印であり、豚を殺した後、彼が一生糞をすくい続けるしかなかった理由を説明している。豚の、その豚の排泄物は、過密で埃っぽいが(マッドマックスの基準では)比較的安定したバータータウンの燃料となっている。しかし、マックスが彼に会う頃には、ピッグ・キラーは新しいあだ名を誇りにしていた。彼は家族を養うために豚を殺したのだから、どうでもいい、彼はピッグ・キラーなのだ。

サンダードームでは、終末後の世界で生き残るためのこの方法に特に注意を払い、共感している。マスター・ブラスター(それぞれアンジェロ・ロシットとポール・ラーソン)は、ロード・ヒューマンガスやイモータン・ジョーのようなタイプに聞こえるが、真実は、彼らはそれぞれの腕力と頭脳を結集して身を守ろうとしている2人である。(マックスもこれを理解しているようで、サンダードームでブラスターを殺すことを拒否している。)そうすると、適応と静止の組み合わせにより、キャラクターがシリーズを通して外見を変えたり、別の姿で再登場したりするのは理にかなっている。サンダードームは、この慣習を加速させ、物語に取り入れたことについて十分な評価を受けていないだろう(時折ぐずぐずする最初の映画と同様に、一部のファンを悩ませる柔らかく子供向けのトーンは許されるかもしれない)。
もちろん、長く続いているシリーズで必要に応じて俳優を交代することは珍しいことではないが、ミラー監督は、必要な譲歩と受け取られかねないそうした配慮を、優雅な弾力性を持って拡大したり縮小したりするシリーズ全体の美学に取り入れてきた。『マッドマックス』は2つの派手なアクションシーンで始まり、終わる。 『007 ロード・ウォリアー』の30分間の見事なクライマックスでミラー監督が再び道路に出る場面では、その範囲(と予算)の拡大が見て取れる。 『ビヨンド・サンダードーム』では、バータータウンという特定の場所がさらに詳しく描かれ、『フューリー・ロード』の冒頭では、シタデルの場所についても同様に描かれるかに見えたが、最初の1時間の大半は実際には継続中の超大型追跡シーンであることが明らかになり、映画は中間点で休憩を取り、その後意図的に『007ロード・ウォリアー』の流れを汲むクライマックスの大爆発へと戻る。
『フュリオサ:マッドマックス サーガ』(2024年) は、おそらくシリーズ史上最も劇的なテンポの変化を表しており、そのため、『フューリー・ロード』での熱狂よりも、 『サンダードーム』での賛否両論で受け止められるだろう。世界観、キャラクター設定、テーマの多くをチェイスの枠組みに集中させるのではなく、外に広がり、若いフュリオサ(テイラー=ジョイと、最年少の頃はアリラ・ブラウン)が『フューリー・ロード』時代のフュリオサ(シャーリーズ・セロン)になったという小説的なストーリーの中で、戦略的にいくつかのキラーアクションシーケンスを配置し、マックスをほぼ完全に避けている。フュリオサとセロンの描写は、『フューリー・ロード』を最高のマックス映画として最高のものにしている大きな要素であるため、このキャラクターに彼女自身の映画を与えることは論理的であると同時に無謀なことでもある。そして、前述したように、セロンの冷酷な存在感なしに。しかし、『フューリー・ロード』がおなじみの『マッドマックス』の題材を新たな調子でリフレインしたように感じられるのと同じように、 『フュリオサ』は前作のサーカスのようなショーマンシップの全範囲を再現しようとはせず、その代わりにその範囲をカーチェイスの合間の荒野での生活に適用している(少なくとも時々は)。
『フュリオサ』は表面上は復讐映画であり、家族の復讐を企む『マッドマックス』の最終章を彷彿とさせながら、多くの同様のテーマのジャンル映画が喚起したくても喚起できない考えをうまく喚起している。大きなネタバレを避けながら言うと、フュリオサと宿敵で、成り上がり志望のイモータン・ジョーのようなディメンタス(クリス・ヘムズワース)との最後の対立は、主要キャラクターがアクションの間ずっと目立って沈黙していることが多いシリーズから予想されるよりもはるかに小さく、会話中心のシーンで頂点に達する。(テイラー=ジョイは、フュリオサの確立された象徴と相まって、彼女の表情豊かな目を最大限に活用し、映画全体で約30のセリフを持っていると言われている。)このシーンは依然として論争的で暴力的だが、これらのキャラクターの未解決の痛みを、彼らの世界、そしておそらく私たちの世界にも当てはまるような方法で明らかにしている。ミラー監督が映画の主題となる問いを最初に述べさせていることを考えると、この音量の低下は驚くべきことではない。「世界が崩壊していく中で、私たちはその残酷さにどう立ち向かうべきか?」これはタイミングの良い問いであり、フュリオサを主人公としたシリーズでフェミニスト的な方向転換が進んだことや、環境に対するメッセージが今日ますます切迫したものになっていることと合致している。
ということで、排気ガスを吹き出すカーチェイスの話に戻るが、比喩的には他のすべてのカーチェイスを終わらせるが、もっと文字通りには際限なく続く。特に『フューリー・ロード』は、 『ロード・ウォリアー』の驚異的な30分のエンディングを長編リミックスで上回る実験のように感じられる。『ロード・ウォリアー』が『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』や『クローンの攻撃』のような映画のノンストップアクションのジェットコースターのようなクライマックスに直接影響を与えたかどうかはともかく、アドレナリン全開で巧みに練られた執拗さの基準を一定レベル設定したことは確かであり、ミラーが『フューリー・ロード』でその基準を上回る時間を多く費やしたのは驚くべきことだ。さらに言えば、『サンダードーム』の最後の列車、車、飛行機のクライマックスは、シリーズの文脈ではあまり語られず、3作目の映画のもう一つの大きな利点であるが、それでもおそらく、あの愛すべきワイルド・スピードのシーケンスのいくつかにインスピレーションを与えたように感じられる。

このシリーズには、サンダードームでの戦闘や、フューリー・ロードでのマックスとフュリオサの戦闘など、他にも優れたアクションシーンがあるが、映画が50年目に突入した今でも、車の魅力は変わりない。たとえば、フュリオサでは、フュリオサが戦闘車両の下部に隠れようとしている間に追跡と戦闘が繰り広げられる15分間のシーンを簡単に盛り込むことはできなかっただろうが、ミラー監督がフューリー・ロードの観客に対する義務を感じたのか、それとも永遠のテーマへのこだわりを感じたのかはわからないが、そのシーンは存在している。映画はすべてオーストラリアが舞台だが、アメリカ人の視聴者としては、アメリカの自動車文化が世界を蝕んでいる未来を舞台にしていると考えずにはいられない。おそらくそれは、ミラー監督がジョージ・ルーカス のような派手なスペクタクルへの愛着と、より偏見に満ちた風刺的な視点を融合させているからだろう。あるいは、より明るい表情のカーズシリーズ (そして、そのきっかけとなったであろう終末についての終わりのないジョーク)がディズニーの定番となったからだろう。いずれにせよ、これまでに作られた最高のエンジン音を立てる乗り物大騒ぎのシーンの多くには、本質的にはエンジン音を立てるのに必要な貴重なガソリン(または「ガゾレン」)の追求を中心に展開する、メタ的な何かがある。それはまるで、最後のバナナクリームを誰が手に入れるかを決める大規模なパイファイトを繰り広げているようなものだ。
奇妙なことに、マッドマックスの周期的で絶望的な性質のおかげで、何十年経っても飽きられずに済んでいる。(それと、登場人物の突飛で独創的な名前だけが、彼らについて本当に突飛なことなのかもしれないという認識が芽生えてきた。)少なくとも3回、主人公の何人かが主人公に別れを告げ、より新しく、より希望に満ちた社会を築くという結末を迎える他のシリーズは、安っぽい感傷、あるいは少なくとも繰り返しで怒りを買うかもしれない。しかし、フュリオサの冒頭のその疑問は、破滅感を回避したり過度に満たしたりすることなく、非常に面白いつまらないものを提供するミラーの天才性を要約している。彼のキャラクターは、愛からではなく必要に迫られて、自動車文化にしがみつくことで、世界の残酷さに立ち向かっている。これは完璧な永久運動型大ヒットシリーズであり、不正に得た破壊的な感覚が、依然として何らかの形の救済をもたらすことができる。
最終順位:
1.マッドマックス 怒りのデス・ロード(2015)
2.マッドマックス2(1981)
3.フュリオサ: マッドマックス サーガ(2024)
4.マッドマックス サンダードーム(1985)
5.マッドマックス(1979)