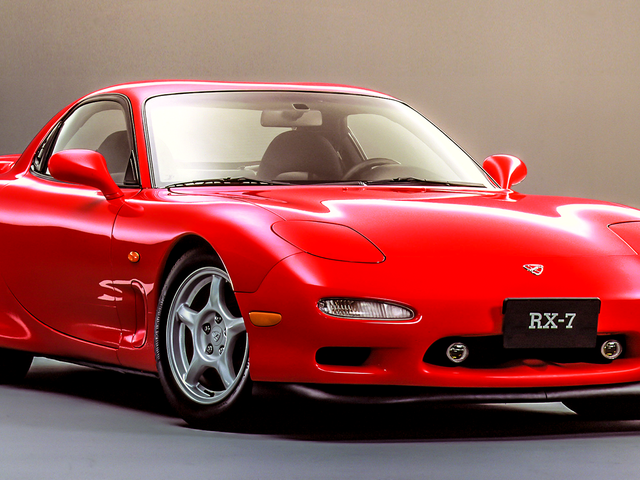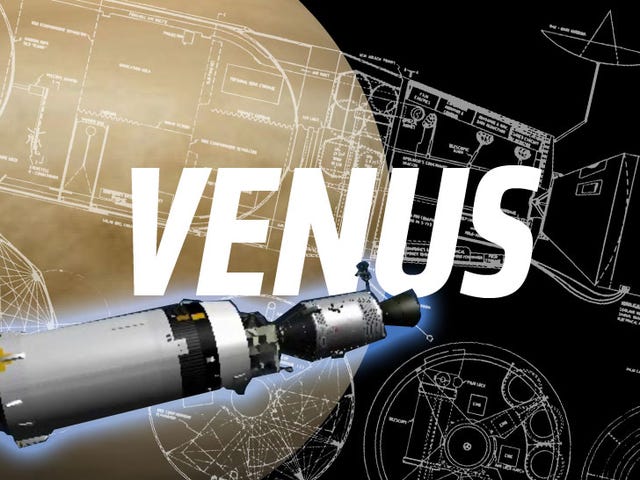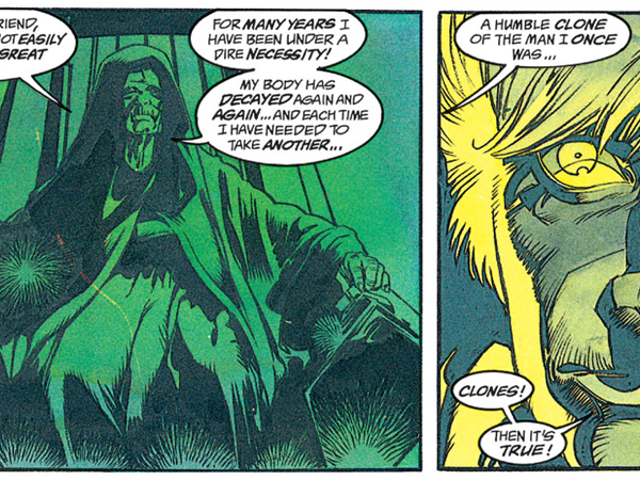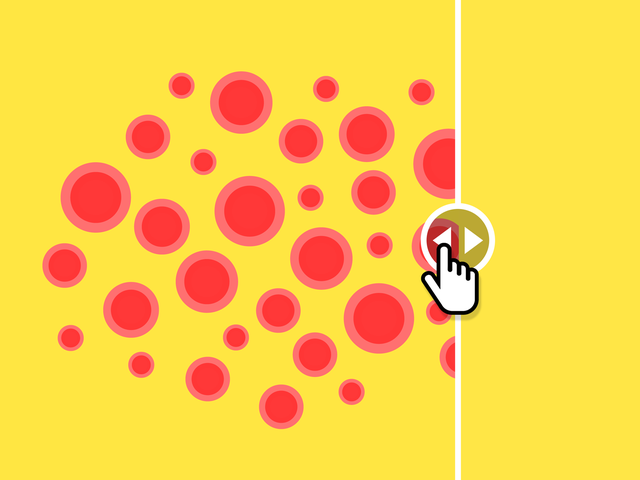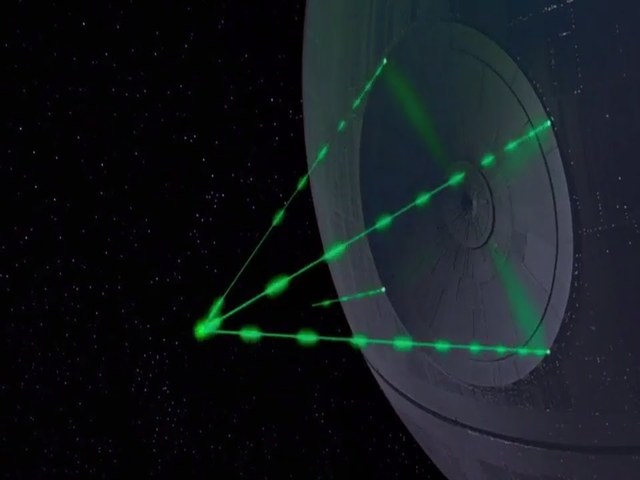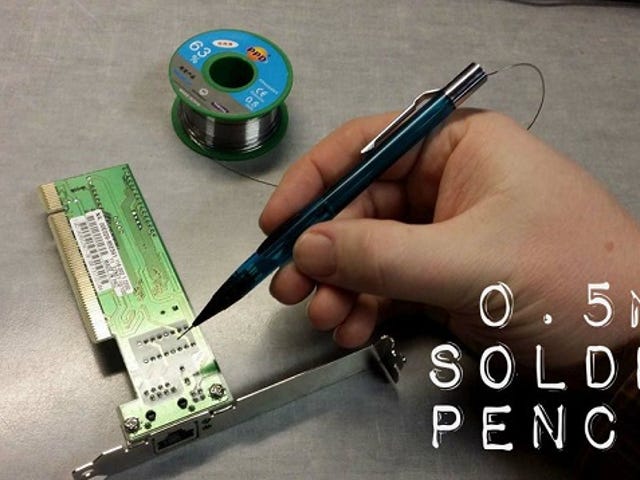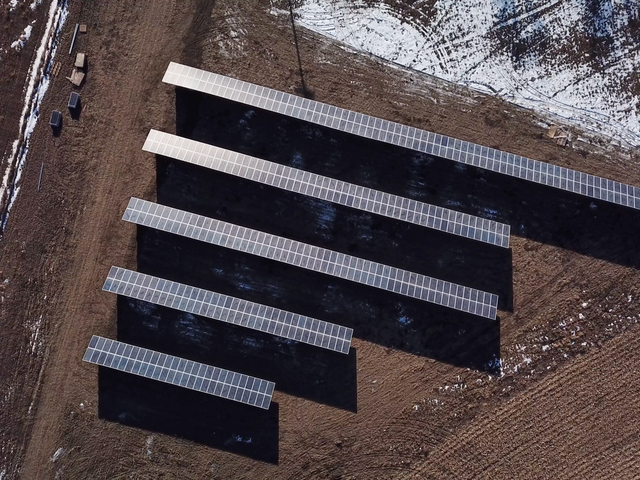フランシス・フォード・コッポラの晩年の三部作は、情熱を取り戻すアーティストの姿を映し出す

『ユース・ウィズアウト・ユース』、『テトロ』、『ツイクスト』など、フランシス・フォード・コッポラ監督のこれらの映画のタイトルを耳にしない日が何年も続くかもしれない。デジタル撮影され、クラシックな要素が盛り込まれたこれらの「後期」映画は、21世紀の観客を等しく興奮させ、当惑させ、苛立たせたが、映画製作者にとっては不作の2つとして簡単に片付けられてしまう。
関連性のあるコンテンツ
超予算の『メガロポリス』公開前夜(1億2000万ドルはどんなプロジェクトでも賭けるには大金だが、まだ配給が決まっていないものならなおさらだ)に、こうした小規模な「個人プロジェクト」は、定番の名作よりもコッポラの原動力を解き放つかもしれない。これらは、遺産の仕組み、記憶の魔法、野心の棘をあぶり出す映画であり、それらの説明が示唆する誠実で強引なエネルギーで扱われている。これらは、コッポラが映画を作る必要がなく、他の何かをすることもできたときに(おそらくワイン関連で)作った映画だが、彼自身を等しく刺激し、打ちのめした芸術形式に立ち戻ったのだ。これらの映画が古いテーマと新しいスタイルを結び付けて、ユニークで不均一で、しばしば驚くべき結果を生み出す方法は、彼の長期にわたる『メガロポリス』を理解する上でまず挙げられるだろう。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
アカデミー賞を5回受賞したコッポラが、2000年代半ばに『宇宙戦争』や『ディパーテッド』ほどの予算を獲得できなかった理由を知らない人のために言っておくと、ニューハリウッドの波の卒業生で、商業が芸術に課す制約をコッポラほど理解している人はおそらくいないだろう。彼は、巨大な作品で自らを追い越すことに疲れ果てて1980年代に入り、心のこもったミュージカルの失敗作で金銭的に破綻し、 取り残された。映画史上最もハイパー資本主義的な10年の始まりとしては、決して良い状況ではなかった。
コッポラは、自身の制作会社アメリカン・ゾエトロープが『ワン・フロム・ザ・ハート』で被った損失の返済に何年も費やした。動機が純粋に想像力からか皮肉からかはわからないが、70年代以降の作品はバロック調の表現主義的な若さ、情熱、野望のビジョンで優れていることが多かったが、1997年にジョン・グリシャムが原作を映画化した『レインメーカー』で、飾り気のないシンプルな作品として消え去った。その間ずっと、『メガロポリス』の厄介で実現されなかった夢は消えずにいた。
『メガロポリス』での惨めさのどん底にあったコッポラ監督に貸与されたルーマニアの短編小説を映画化した『ユース・ウィズアウト・ユース』が、商業的に仕事をしていたときに彼を悩ませていたものに対する解毒剤のように感じられるのも不思議ではない。自殺願望のある高齢の学者ドミニク・マテイ(ティム・ロス)が雷に打たれて30歳若返るという波乱に満ちたファンタジーであるこの物語に対する彼の関心を、ハリウッドの役人たちに売り込む必要はなかった。ヨーロッパの共同プロデューサーが支援する小規模で自費制作のこの作品で、コッポラ監督は作家ミルチャ・エリアーデのテキストの奇妙さに対する情熱をほとんど妥協しなかった。「私の年齢と当時の状況を考えると」とコッポラはブックフォーラムに語った。「私はただ立ち去って、作っていることさえ誰にも言わずに済む機会に恵まれたのです」
プライベートでストーリーテリングの世界へ足を踏み入れるというアイデアは、スタジオでの苦労に悩む人にとって魅力的であるだけでなく、この映画に見られる親密な雰囲気と共鳴する。『ユース・ウィズアウト・ユース』のデジタル画像の質感は、確かにコッポラのキャリアにおける映像の最高峰に比べるとシンプルだが(それでもブロッキングとリズムに関しては専門家の目で撮影されている)、ドミニクが若さの機会と1930年代のヨーロッパにおける医学上の驚異としての地位(つまりナチスの標的になる)を受け止める時、目を引く構図や色彩がないことで、宇宙における自分の立場について静かに打ち砕かれ再構築されるドミニクと同じ空間を共有しているという明白な感覚が私たちに与えられる。
物語は、その本来の文学的性質をほとんど犠牲にしていない。ドミニクは、霊的に映し出された分身に悩まされ、ヴェロニカ(アレクサンドラ・マリア・ララ)と恋に落ちる。ヴェロニカも、雷に打たれて過去に飛ばされた、ドミニクの失恋した恋人の分身である。そして、映画から洗練された映像の輝き(必ずしも技術的な技巧ではない)を剥ぎ取ったことで、『青春の夜明け』は、2つの世界の間に立つ映画のように感じる。それは、散文と映画、過去の後悔と未来の約束、古典映画と現代映画の間である。これらの両極の間の緊張は、ドミニクが映画のほとんどを費やす部分である。コッポラは、自分も同じ立場にいると考えていたのだろうか?
ドミニクが超能力を得て、独自の言語を発明し、ヴェロニカがどんどん古い言語で話し始める理由を解明するにつれ(ドミニクの書かれざる作品はすべての言語の起源についてである)、コッポラはドミニクを悩ませているテーマに、監督自身がそのテーマにどれほど強い思い入れを持っているかを示す率直な切迫感をもってアプローチする。なぜ私たちは自分の言語を使って自分の本質を表現できないのか?私たちが切望する余分な時間を与えられるとはどういうことなのか、それは私たちの欲望をどのように変えるのか?芸術と愛する人は、どちらかを選べないことで両方とも苦しむことになるのか?『ユース・ウィズアウト・ユース』は、見過ごされがちな大ヒット作というよりも、コッポラの独特な概念実証、映画監督としての柔軟性と信念の論文、そして新たに受け入れた地平の宣言のように感じられる。
2年後に公開された『テトロ』は、ファンタジーの要素がないわけではないが、私たちが素手でつかむことができるもの、つまり、疎遠になった2人の兄弟が耐えられる以上の重荷を背負った崩壊した家族の緊張、祖先の故郷であるブエノスアイレスでの表現の仕方が分からない真実に直面するという、より力強く掘り下げている。明るい目を持つクルーズ船の従業員ベニー(赤ん坊のオールデン・エアエンライク)は、気まぐれな年上のアンジェロ(ヴィンセント・ギャロ)を追跡する。アンジェロは現在「テトロ」と呼ばれ、アルゼンチンの精神病院でテトロの看護師だったミランダ(マリベル・ベルドゥ)と一緒に暮らしている。
アンジェロは数年前に家族を捨て、ベニーは兄の代わりに別の名前を持つ気難しい無愛想な男を見つけた。その男はベニーを新しい生活に招き入れることを渋り、アパートの奥に隠した大量の走り書きの紙につらい子供時代を分類していた。ベニーは、テトロの未完成の素晴らしい劇を発見する。その劇は、浮気好きで横暴な指揮者の父 (クラウス・マリア・ブランダウアー) と、母親を死なせた自動車事故に対する罪悪感について描かれている。ベニー自身が事故に遭うと、彼はテトロの劇の完成版を地域のフェスティバルで上演することを決意し、兄はこれまで守ろうと闘ってきた分裂と向き合い、それを受け入れることを余儀なくされる。
鮮明な白黒で撮影され、陰鬱な戦後イタリアの家族メロドラマをデジタルで現代風にアレンジした『テトロ』は、愛らしい感情の揺れ動きを誇らしげに表現しており、コッポラの鋭く芸術的な1983年の失敗作『ランブルフィッシュ』を彷彿とさせる。コッポラは、あえて個人的な映画を作ることの曖昧な境界線について率直に語ってきた。彼の父と叔父は指揮者で、彼は兄のオーガストを羨み、真似しながら育った。彼の映画に自伝的な解釈を投影しても許されるだろうか?しかし、多くの優れた個人的芸術作品と同様に、『テトロ』は抽象化の結果であり、直接的な再現ではない。芸術家ではない人が本能的に秘密にしておく不安や思索に芸術家が表した結果である。もし物事が違っていたら、決断をせずに別の道を選んでいたらどうなっていただろうとテトロは振り返る。
「個人的な映画を作るのは、おそらく自分が完全に理解していないから選んだテーマを扱うことになるので、より困難です」とコッポラ監督はシアトル・メット紙に語った。「自分の本能について問いかけているのです。答えを知る唯一の方法は、実際にその世界に足を踏み入れて、実際に動かしてみることです。これは痛みを伴うだけでなく、まるで検死解剖のようなものです。ある意味、生きている間にそれを行っているのです。」
『Youth Without Youth』が拡張、つまり無限に知的な範囲を広げることに関する作品だとすれば、 『Tetro』は内向きになり、家族という体制によって作られた感情的な境界に閉じ込められる。確かに内省的だが、運命の引力もあり、そして何よりも、死に対する強い意識がある。私たち全員が問い、答えを出す時間は刻々と過ぎているのだ。
死は、コッポラの最新にして最も実現していない「後期」プロジェクトであるゴシック ゴースト ストーリー「ツイクスト」にもつきまとう。夢から生まれ監督の邸宅で撮影された「ツイクスト」は、書店もないほど小さな町々を回って最新の魔女スリラーを執筆中の下手な作家、ホール ボルティモア (ヴァル キルマー) に焦点を当てており、彼は金物店の裏に折りたたみ式のテーブルを出して隔離されている。彼の唯一の地元ファンである保安官ボビー ラグランジ (ブルース ダーン) が最近殺害された被害者を見せて彼の想像力を刺激し、やがてホールは幽霊と記憶の森の夢の世界に迷い込む。ここで、殺害された少女ヴァージニア (エラ ファニング) とエドガー アラン ポー (ベン チャップリン) が、湖の向こうに吸血鬼が住んでいると確信した牧師による歴史的な女生徒虐殺について彼に最新情報を伝える。
明らかに『ツイクスト』は非常にリラックスした制作で、のんびりとした野心のない超自然的な物語は、コッポラが潜在意識の思索と同じくらい魅惑的で面白いと思うものからインスピレーションを得ているように感じられる。最高の瞬間には、映画は質素な田舎町の不気味さと魅力的な模倣のミックスを捉えており、その相反する雰囲気は、洗練されていないデジタルのビジュアルパレットによって強調されている。この効果は、 『ツイン・ピークス リターン』 でより見事に捉えられている。俳優たちは、探偵の厳粛さの裏に明らかに哀れな心を隠している素晴らしいキルマーを筆頭に、意欲的であり、ファニング、チャップリン、そして(フランス語を話す放浪者としての)オールデン・エアエンライクは、幽霊の存在の安っぽい側面を決して大げさに演じ過ぎない。
しかし、トゥイクストが喚起したいものと、完成した映画が実際に達成したものとの間には、明らかな隔たりがある。コッポラの単純な CG 要素と背景を使った実験は、監督が新しい技術に手を出すのに適切なプロジェクトを選んだものの、それをしっかりと把握していないことの結果であり、不快なものだ。ところどころで、大林宣彦の反戦三部作の技術的に流動的な高みを思い起こさせられる。また、最近のニール・ブリーン映画の平坦な風景を一度か二度思い出す。
トゥイクストは、 1986年に息子のジャン=カルロを死なせたボート事故に対するコッポラの悲しみと罪悪感を物語に取り入れるというカタルシス的な選択をしているが、この映画は、彼の他の2つのデジタル撮影映画に流れるテーマを統合したものとして最も共感を呼んでいる。3作品とも、素晴らしい作品を生み出す寸前でありながら、自分自身のこだわりや不十分さに足を引っ張られている作家たちについて描かれている。ホールは、几帳面で学問的なドミニクに比べると商業的な下手くそかもしれないが、彼らは失敗を内面化していることを同じように自覚しており、素晴らしい作品を生み出す前に自分たちの精神を解きほぐす幻想的な出会いによって解放される。
テトロの未完成の作品は、もしそれが真実のまま完成すれば人生が一変するであろう兄によって彼の手から取り上げられる。ドミニクは、ベロニカが彼の研究の原語を伝達しようとすればするほど、彼の存在が彼女を傷つけることに気づく。野心は、私たちが愛する人々を少しずつ傷つける諸刃の剣だが、創造性を追求することは、より親密になる必要のある人々の人生をより良くすることができる。
そして、ツイクストの遊び心のある結末では、物語の不気味な出来事が、ホールの復帰原稿の筋書きの展開だったことが明らかになる。これは未解決の苦痛についての映画だが、物語を語ることの商業的な誘惑にコッポラがウィンクしたのは、そもそも私たちがどのようにしてこれらの自費プロジェクトに至ったかを成熟した形で反映しているように感じられる。物語は、苦痛に立ち向かうだけでなく、想像力を刺激し、感情を刺激するのにも役立つ。つまり、娯楽を生み出し、観客をだますことができるのだ。そうでなければ、そもそもなぜ私たちは物語を語るのだろうか?
このあまり愛されていない三部作で、コッポラは麻痺状態から抜け出すこと、暗闇から大胆で刺激的なものを生み出すこと、そして物語を通してそれを行うことで得られる自己認識、親密さ、喜びについて抽象的で相互に絡み合った物語を語っています。彼がまさにこのような映画を作っていなければ、『メガロポリス』は決して作られなかったでしょう。これらの映画は単に非常に個人的なだけでなく、物語を語ることで私たちの内面世界がどのように変化するか、そして痛みを伴うものを魅力的で楽しいものに変えることがいかに感動的であるかを突きつけています。それらはすべて、一度に、ハリウッドの古い決まり文句「1つは私のために、1つはあなたのために」を体現しています。