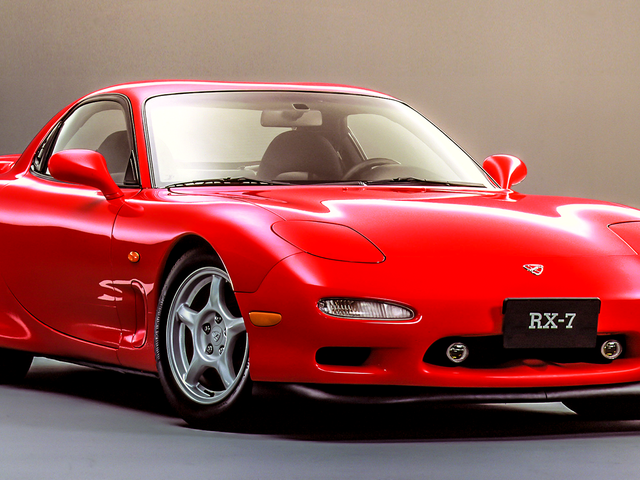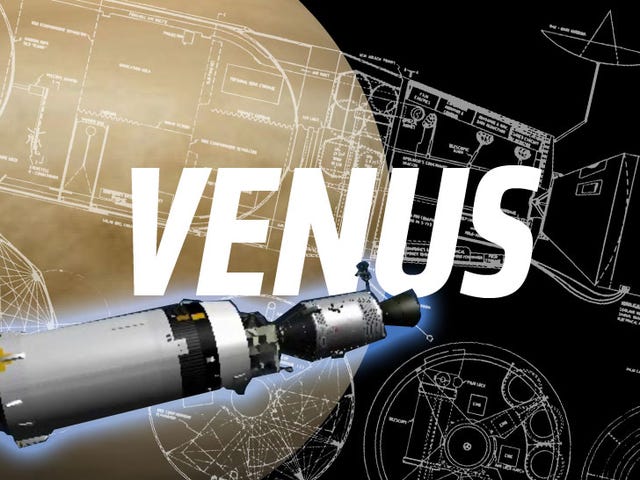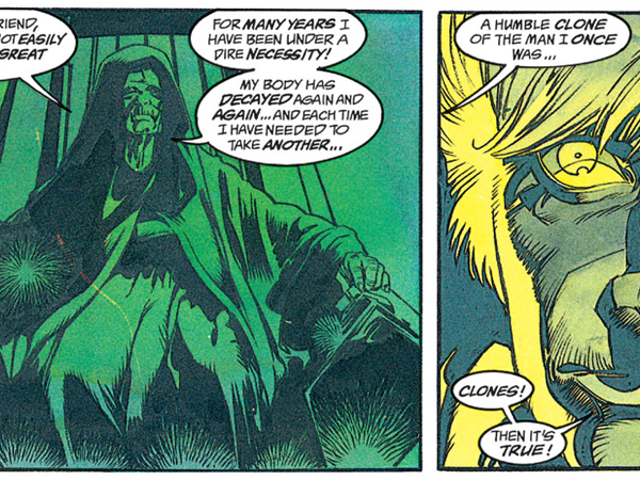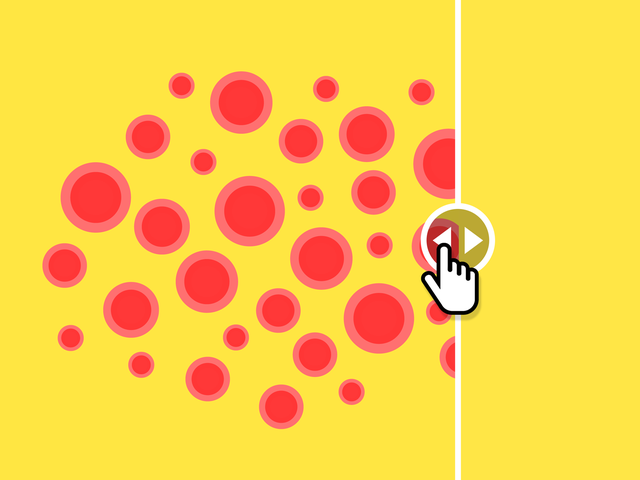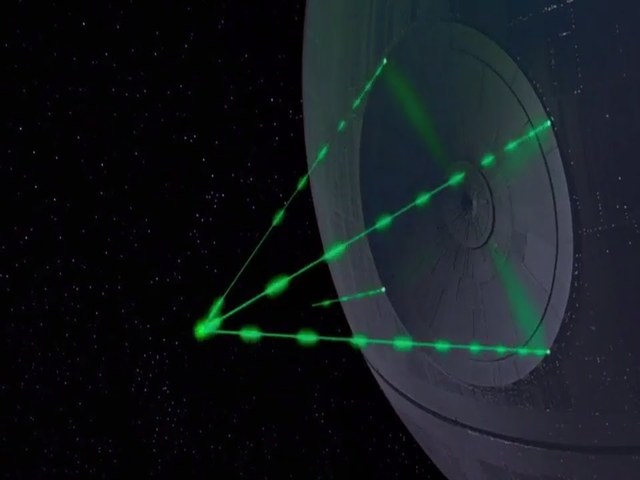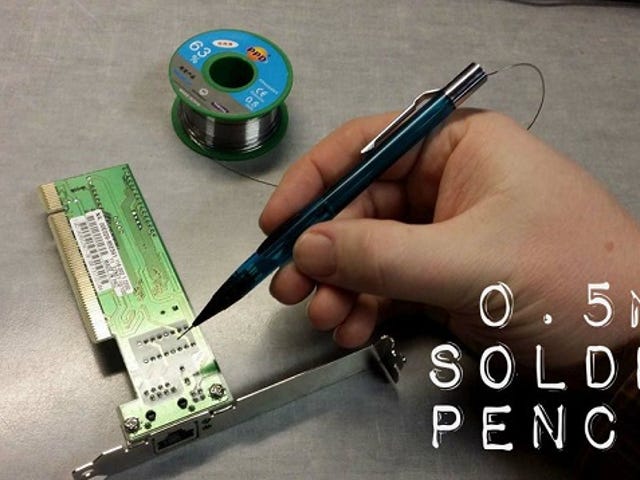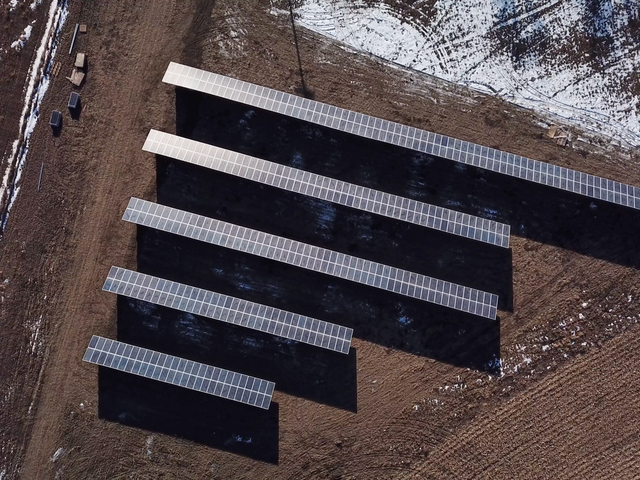リブートされた『猿の惑星』シリーズは不確かな未来を常に見据えている

AV Club は、「Run The Series」で映画シリーズを調査し、新作ごとにどのように変化し進化していくかを研究しています。
関連性のあるコンテンツ
20世紀フォックスはもう存在しない。ハリウッドの大手スタジオの一つとして何十年もの間存在していたこの組織は、現在ではディズニーの一部門に過ぎず、ディズニーは2019年にフォックスの映画会社を買収し、それ以来、20世紀スタジオと改名されたレーベルを使用して、Huluに直接送信される一部の映画をブランド化し、時折、ジャンル映画を劇場で公開している。偶然にも、ディズニーの2024年の夏のラインナップは、フォックスの残党に大きく依存しており、新しいエイリアン映画、おそらくフォックスのX-MEN映画のカーテンコールとなるデッドプールの続編、そして猿の惑星シリーズの新作がある。ボブ・アイガーは最近、フォックスがディズニーの将来の公開スケジュールで必ずしもそれほど大きな役割を果たすわけではないと投資家に保証した。心配することはない、とアイガーは言っているようだった。我々は、前世紀のハリウッドの主要プレーヤーの 1 つを、時折掘り出せる IP の源泉に過ぎないと見ており、ミュージカル、西部劇、ノワール、オリジナル ホラーといったフォックスの豊かな過去の歴史を愚かにも引き継ぐ危険はない (まあ、Hulu ではそうかもしれない。そこで何が起きるかは誰にもわからないが)。この文脈で、『猿の惑星: キングダム』はフォックスの過去へのワームホールのように見える。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
オリジナルの『猿の惑星』映画は、スターウォーズ映画の配給に先駆けて、フォックスがSFの本拠地としての地位を確立するのに役立ち、シリーズは減少する予算と名声のレベルを利用して挑発的なSFのアイデア をこっそり持ち込み、劇場とテレビで5本立てのマラソンにより、猿が驚くほど手ごわい文化的足跡を残すことを保証しました。したがって、スターウォーズ、エイリアン、プレデター、およびさまざまなジェームズキャメロンプロジェクトに続いて、スタジオがフランチャイズを復活させたいと思うのは当然のことでした。さまざまな俳優と映画製作者が何年もの間、さまざまな猿の惑星のプロジェクトに出たり入ったりして、行き詰まり、最終的にスクリーンに登場しました。ティムバートンによる2001年の再制作は莫大な利益を上げましたが、続編を正当化するほど観客を満足させませんでした。 (「大金を稼いだが続編の制作にはつながらなかった」という言葉は、今では独自のSFブランドのように聞こえる。)
しかし、10年後、フォックスは同作品を危機から救い、リブート版シリーズは現在4作目まで製作され、5作目も製作される見込みで、オリジナル作品を上回る可能性も見えてきた(少なくとも数に関しては)。ディズニー支配下での最初の作品である『猿の惑星: 王国』では、猿たちは今や親会社の崩壊後の遺跡をさまよっている。フォックスが今でも『エイリアン』や『プレデター』、そして『猿』を製作しているのを見るのは心強いが、これが勝利と言えるのかどうかは分からない。
確かに『猿の惑星: 王国』は豪華なスペクタクルで、一見本物のように見える場所と、主にモーションキャプチャーで制作されたアニメキャラクターで構成されたキャストが組み合わさっており、150分間の上映中は顎が落ちるのを忘れてしまうほどの迫力がある。言い換えれば、 2011年の映画『猿の惑星: 創世記』からは程遠い。同作はシリーズを最もよく知られたどんでん返しなしで再開した作品だ。1968年のオリジナル版の最後で、チャールトン・ヘルトンが演じる宇宙飛行士のキャラクターは、自分が遠い惑星に不時着したのではなく、人類が物事を徹底的に破壊し、超知能霊長類に取って代わられた後の遠い未来の地球に不時着したことに気づく。 (負けじと、この映画のどういうわけかG指定の続編は、地球をさらに破壊することに成功している。)『キングダム』は、その不快な押し引きの一部、つまり、猿に対する人間の徐々に進む社会的敗北が不自然で、どういうわけか不公平であるとして彼らを悩ませている様子さえも取り上げている。

バートン監督の映画でもタイムトラベルを題材にしており、あまり論理的ではないが見事なまでにあっけにとられる最後のどんでん返しを繰り広げたが、ほとんどの人はそれを嫌った(少なくとも非常に困惑した)ようだ。では、かわいそうな『猿の惑星:創世記』に残された選択肢は一体何だったのか。しかも舞台は現代だ。脚本家のアマンダ・シルバーとリック・ジャッファは、監督のルパート・ワイアットとともに、旧シリーズの素晴らしい第4作『猿の惑星: 征服』からヒントを得て、同作の出来事の一部を、より現実的なアプローチで再解釈した。これはおそらく、より費用対効果の高いものだっただろう。11年前のフォックスの最初のX-メン映画と同様に、 『猿の惑星: 創世記』は2時間をはるかに下回る(長いエンドクレジットを除くと90分近く)ため、当時は親会社に不安を抱かせたようだ。 (こうしたことは、映画評論家のぼんやりとした記憶に留められることが多いが、『猿の惑星: 創世記』のプレス試写会は、公開の約 48 時間前に行われることが多く、通常は自信の表れとは言えない。) これらの制約は、『X-MEN』の最初の映画と同様に、『猿の惑星: 創世記』に、他の類似の映画とは一線を画す緊迫感を与えている。
ルパート・ワイアットは『ゼロから始める異世界生活』以来、それほどファンボーイ的な地位を獲得していないが、彼の猿の映画は本当に感動的だ。手持ちカメラワークは派手な揺れにならずに即時性があり、場所や時代は素早い溶解で切り替わり、彼のアクションスリラー映画製作と同様の流動性があり、映画を人間の物語から猿の物語へ、科学ドラマから脱獄から街中の暴動へと導いている。人間から猿への移行は、オリジナル映画のトリックを彷彿とさせる意外な刺激がある。物語は、認知症の父親(ジョン・リスゴー、この映画には幸運な展開があった)の治療法を開発しようとする化学者(ジェームズ・フランコ、当惑した表情を浮かべる以外に何をしていいのかわからない様子)を追いかけるところから始まる。その治療法には、シーザー(モーションキャプチャーのアンディ・サーキス)という名の実験用チンパンジーを密かに救出し、シーザーをハイブリッドなペットと息子として育てることが含まれる。シーザーは家族から引き離され、監禁された後、脱出方法を考案する。ちょうど猿の知能を高めるサルインフルエンザが人類を襲った頃である。
『猿の惑星:創世記』は、人類を、私たちの世界に似た世界から、パンデミック災害の瀬戸際にある10年後の、まさに私たちの世界に導く。その間、シーザーと彼の仲間の猿数名は(ほとんど)セリフのないキャラクターとして描かれている。ワイアットは、シーザーの猿のシェルターの生息地の偽物が映画のサウンドステージを彷彿とさせるなど、スタイリッシュなタッチを加える時間も見つけており、シーザーが屋根を突き破って夜に飛び出すシーンでは、さらに興奮が盛り上がる。『猿の惑星』を安っぽく「現実的」にするのではなく、この映画は、その「まあまあの」現実感を利用して、その飛躍をより重厚で重大なものにしている。シーザーが初めて喉から「NO!」と叫んだとき (これは以前のシリーズでよく言及された出来事です)、それはシーザーと他の類人猿が長々とおしゃべりする続編が何度もあった後でも、いまだにぞっとするような瞬間です。
X-メンとの類似点を続けると、マット・リーヴス監督の威厳と美貌を誇る猿の直後の続編は、あの勢いを取り戻すのに少々苦労しており、時にはその重苦しい上品さのせいで沈みそうになる。(まあ、上品さの部分はX-メンの特徴ではないが、あの最初のX映画には、より印象的な続編 にはない魅力がある。) フォックスが愛したカナダの森のロケ地の使用は確かに印象的で、放浪するX-メン:ファイナル ディシジョンよりも、憂鬱なウルヴァリンに似ているが、猿がサンフランシスコを即席の戦場に変えるのを見るほど楽しいものではない。古いシリーズは、制作が進むにつれて予算が減ったのかもしれないが、3作目では、同時代のサンフランシスコに数匹の猿を持ち込むことでコストを節約している(そして、前作のような行き詰まりを回避している)。しかし、例えば『猿の惑星 征服』は、メイクや特殊効果を省いているにもかかわらず、遠いSF社会を舞台としている。キアヌ・リーブス監督後の新作『キングダム』は、その異世界感に少し近づいており、CGの質は低下していないが、それでも野原や木々はたくさんある。

これは単に美的欠点というだけではない。『猿の惑星: 新世紀』と『猿の惑星: 聖戦記』はどちらも、ジェームズ・ボンドからスタートレック、そしてもちろん再びX-メンまで、2010年代の多くのシリーズを悩ませてきた終わりのない前日譚のせいで少々苦しんでいる。これらの映画のほとんどは、それ自体は面白くてよくできているが、全体としては、最近の映画ツイッターミームのように感じられ始め、うんざりするほど「私たちは戻ってきた」と繰り返しながら、映画の最後には、ついに、待ち望んでいたジェームズ・ボンド/USSエンタープライズ/スーパーチーム/超知能猿の惑星がここにあると約束している。
不可解なことに、冗長な前編としては最悪の『ドーン』が、新シリーズの中ではベストの選択だという意見が一致しているようだ。しかし、実際に何が起こるのだろう?もちろん、いくつか重要なことが起こる。虐待を受け怒り狂った実験用猿のコバとシーザーの間にさらなる亀裂が生じる。コバは策略によって人間と猿の派閥間の脆弱な平和を破壊する。シーザーは最終的にコバを殺すことで争いを鎮めようとするが、それがシーザーを悩ませることになり、特に『猿の惑星:聖戦記』での虐殺を最終的に止めることができなかったため、特に悩まされることになる。シーザーがコバになるという考えに悩まされているという考え以外に、ドーンの想定される下地なしに『猿の惑星:聖戦記』で起こることの何かが本当に意味をなさないのだろうか? (最も奇妙なのは、猿たちの会話を控えるという映画製作者の決定である。この決定は『ライズ』では大きなドラマチックな利益をもたらしているが、すでに存在する超知能猿の軍隊を描いた映画でははるかに少ない利益をもたらしている。)

ロジスティックスはさておき、 『猿の惑星:聖戦記』は、はっきり言って、魅力的な出来映えで、素晴らしい視覚効果もある映画だが、新シリーズの中で最も閉鎖的で、SF的な疑問を提起することに最も関心がないように感じる。これは、退屈な人間のキャラクターにかなりのスクリーンタイムが与えられ、猿のキャラクターは抑制されすぎているという、非常に不均衡な状況にあるからかもしれない。4作品の中で最も純粋に美しい『猿の惑星:聖戦記』は、オリジナルシリーズの折衷主義をよりよく思い起こさせ、それが今度は、自己前日譚的で、キャラクターの動機付けにこだわった袋小路から抜け出すきっかけとなっている。映画の前半は西部劇の雰囲気があり、シーザーをクリント・イーストウッドのような人物として位置づけ、猿の小さな集団(と口のきけない人間の子供1人)を率いて(シーザーの妻と長男を殺した大佐に対して)復讐の任務に就き、それが大義のための救出へと変わるというストーリーである。北米の風景は新たな荒廃した辺境地となり、シーザーは(言葉には出さずに)自分が成し遂げた驚くべき進化の飛躍が結局は無駄になり、他の人間と同じように簡単に文明化されてしまうのではないかと考えているようだ。

『コンクエスト』の反乱ほど挑発的なものはなく、 『猿の惑星: 聖戦』の結末ほど曖昧なものはないが、それでもリーブスの映画は、人類の弱さと、それを克服しようとする類人猿の闘いの中に哀愁の美しさを見出している。サーキスとアニメーターたちは、『ウォー』でシーザー役を演じ、おそらく最高の演技を見せ、写真のようにリアルな類人猿の顔を通してイーストウッド風の冷笑をうまく演出している。一方、シーザーの長年の右腕である類人猿のモーリス(カリン・コノヴァル)と新人のバッド・エイプ(スティーブ・ザーン、こちらも愛らしい帽子とダウンジャケットの組み合わせ)は、シリーズで最も集中したアンサンブルを形成している。
『猿の惑星: 王国』には、頼りになるようなおなじみの CG の顔はない。その代わりに、シリーズは『猿の惑星:聖戦』の終わりにシーザーが静かに死んでから「何世代も」後の未来へと、遅ればせながらジャンプする。ノア (オーウェン・ティーグ) は仲間の猿たちとともに、鳥の訓練に重点を置いた平和な集落で暮らしているが、人間のメイ (フレイヤ・アーラン) の出現によって新しい世界が開ける。そこには、突然変異したサルインフルエンザの犠牲者のように野生化していないかもしれない人間の世界だけでなく、プロキシマス・シーザー (ケヴィン・デュランド) が率いる、より攻撃的で人口密度の高い猿の一族の世界もある。シーザーは自由の闘士のイメージと評判を自分の目的のために利用している。本質的に、私たちはまだ『猿の惑星: 聖戦』の領域を巡回しているのだ。 (確かに、この時点で「Beneath」または「Escape」のいずれかを実行するには、フランチャイズ映画製作者であれば契約上外科手術で除去することが求められるレベルの厚かましさが求められるだろう。)
『キングダム』は猿の映画の拡大版という感じで、監督のウェス・ボールは猿たちが走ったり、身をかがめたり、互いの武器をかわしたりするシーンに『メイズ・ランナー』の続編のような躍動感を少し取り入れているが、明らかにリーブス版のシリーズにいくらか影響を受けている。印象的なのは、武力衝突の激しいシーンがあった以前の三部作よりも、本作はアクションが少ないということだ。この作品にもそういったシーンはいくつかあるが、最高のシーンの多くは、ノアが巨大な望遠鏡を発見する短い無言のシーンや、孤独な猿のラカ(ピーター・メイコン)がシーザーの「本当の」教えをノアに伝えようとするシーンなど、単純な探索に関するものだ。地球の新しい現状に慣れていくと、ノアの世界が広がるのを見るのはワクワクする。そして、その世界が視覚効果によってどれほど作られているかということに驚嘆するのは、相変わらず感動的だ。俳優とアニメーターのハイブリッドな演技は、視覚効果が単なるスペクタクルの域を超えられるかどうかの最前線に立っている。フォックスのアバターシリーズほど突飛ではないかもしれないが、この時点で、スクリーンに映る人間の数はおそらく減っているだろう。
現代のシリーズの基準からすると、『猿の惑星: キングダム』は、多くのデジタルファースト大ヒット作に見られるぼやけた背景や曇り空があるとはいえ、夏映画の大成功だ。それなのに、予算や上映時間が、それほど有名ではない 1970 年代の先駆者たちほどには減っていないにもかかわらず、このシリーズには何かが欠けているように感じることがあるのはなぜだろうか。
最新作では、猿と、もちろん数人の人間が、地球の軌道について、そして映画に登場するグループのいずれかが猿の遺産を公正に受け取ることができるかどうかについて、繰り返し議論しているが、そこに手がかりがあるかもしれない。そうではないと考える登場人物の一人は、「二度と戻れない過去」への憧れに等しいと意見を述べるが、これは私たちが現在直面している永遠のフランチャイズ状況全体を簡潔に描写しているだけでなく、特に新作が、純粋なSF想像力よりも、永久運動や続編の種となるプロットに興味があるように感じることがある理由の説明にもなっている。13年前に公開された『マイレージ、ゼロ』は、現在のパンデミック時代と偶然に重なっているが、一方で『キングダム』では、信念をどのように伝えるか、平和的共存が可能かどうかについて、曖昧(まあ、当然だ)と曖昧(フランチャイズ、ベイビー!)の間のどこかに落ち着く。
実のところ、過去を再現するのはほぼ不可能だ ― たとえそれが比較的最近のことであっても。現在の猿シリーズはディズニーが参入するずっと前から製作が始まっているが、『猿の惑星』が新しい親会社のために昔の20世紀フォックスを模倣することを意図した代表的なフランチャイズになることには、常に何か代用品があるのかもしれない。同時に、これほど名高い組織を手放すのは簡単ではない、そうだろう? 『猿の惑星』は、どの作品もヒット率が高い。最初の5作品の中で最も弱い作品でも、大きな変化があるが、新しい4作品は丁寧に作られている。(バートンの1回限りの作品は、まあ、その下のメイクと演技のおかげで、見ごたえのある失敗作になっている。) 『キングダム』は、新しいシリーズが古い映画のようなクレイジーなコーナーに自らを描くことをまだ望んでいないように感じられても、さらなる可能性の世界を設定している。作品は、激しいトーンの変化や時間のループによる狂気を避けており、シリーズ 4 作目としては驚くほどの規律性を示しています。この規律性は、猿の映画が少なくとも、これまでのところ、不確かな未来を常に楽しみにしているという礼儀を私たちに与えていることも意味しています。私たちと同じように。
最終順位:
1.猿の惑星: 創世記(2011)
2.猿の惑星: 聖戦記(2017)
3.猿の惑星: 王国(2024)
4.猿の惑星: 新世紀(2014)