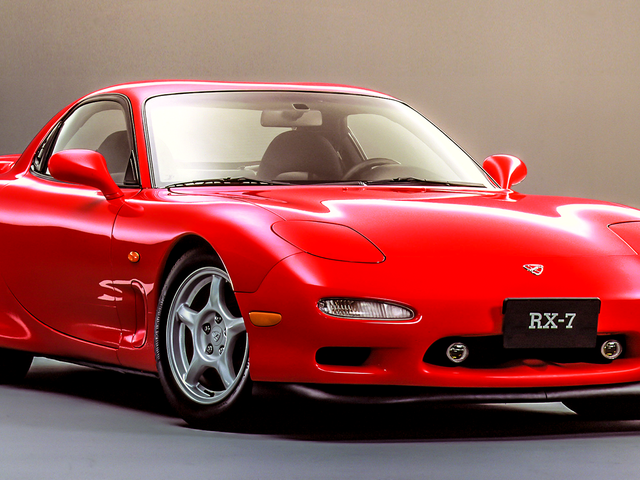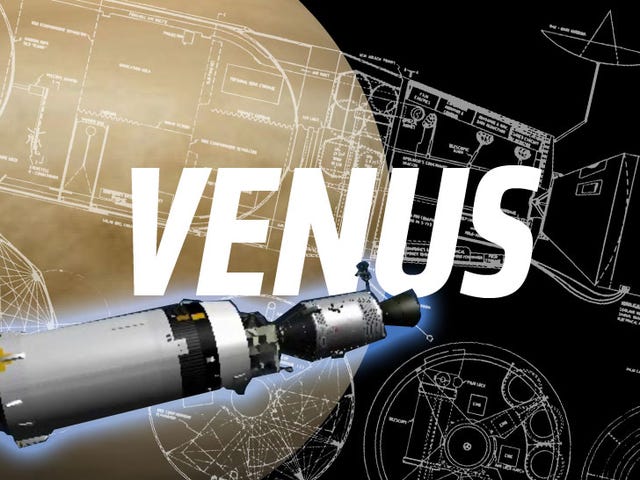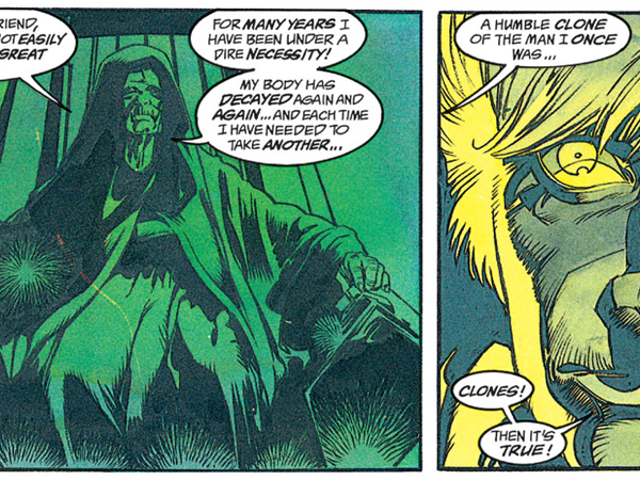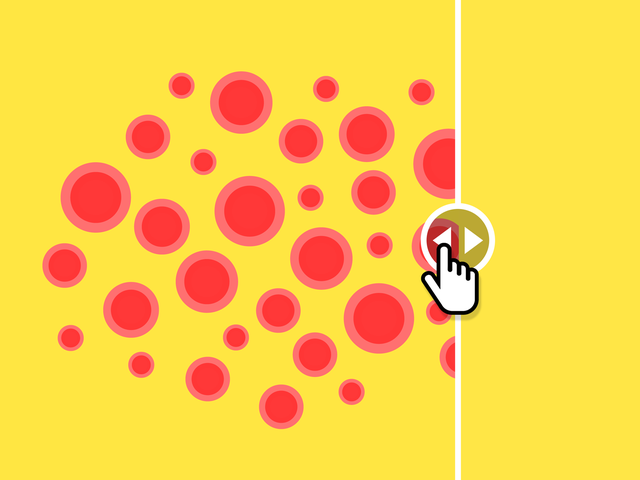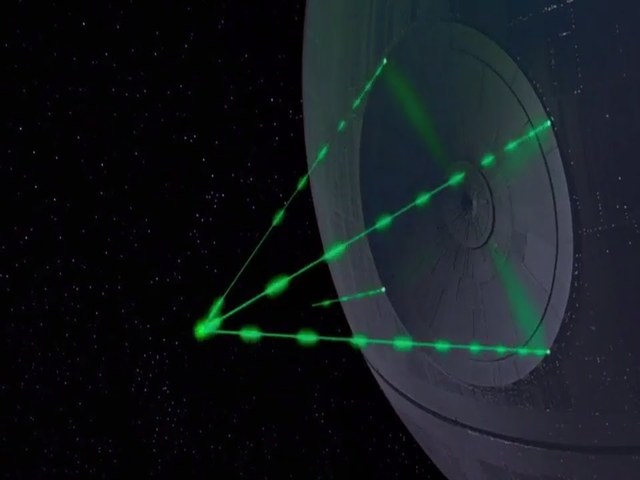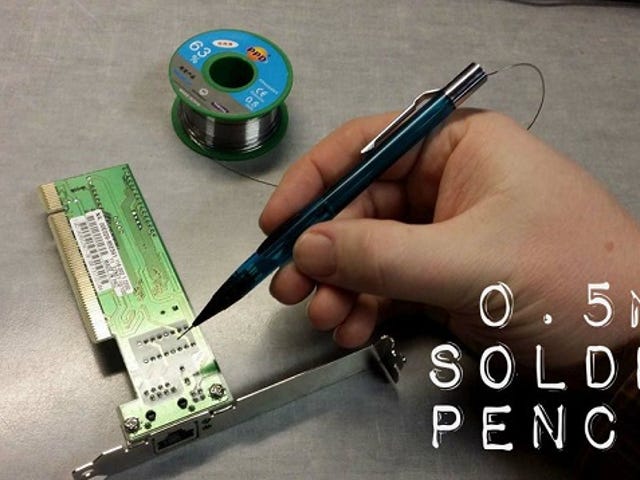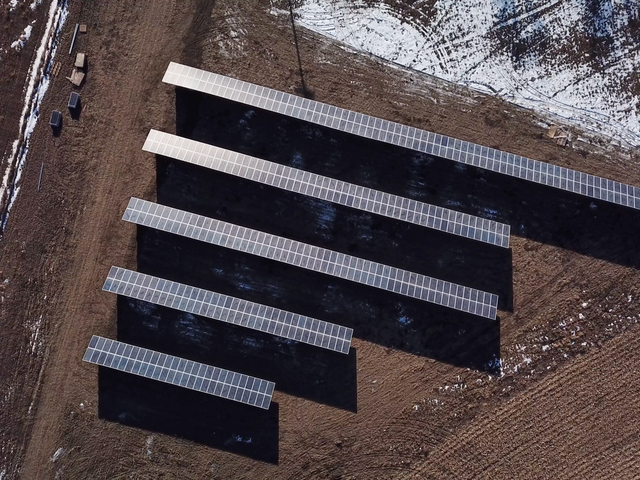『バック・トゥ・ブラック』レビュー:金儲けを狙った伝記映画は、偽装に気を配らない

2018年にクイーンの映画『ボヘミアン・ラプソディ』 が大ヒットして以来、ハリウッドでは音楽の伝記映画のゴールドラッシュが起こっている。その結果生まれた映画の中には、アーティスト本人、あるいは多くの場合は遺産管理団体の参加を得て作られたものもあり、本物の創造力を発揮する余地を見出したものもある(『ロケットマン 』 、『エルビス 』)。一方、独創性に欠ける作品の方が多い(『リスペクト 』 、『ホイットニー・ヒューストン 踊ろうよ! 』 、『ボブ・マーリー ワン・ラブ 』)。映画製作者たちは、間違いなく、決まり切った伝記映画の形式と、音楽の権利保有者が開発プロセスに関与するという二重の制約に縛られていた(アーティストの本当のありのままの肖像を描こうとする公式に認可された伝記映画は稀だ)。サム・テイラー=ジョンソン監督がエイミー・ワインハウスの物語を描いた『バック・トゥ・ブラック』は、『ボヘミアン・ラプソディ』以降のハリウッドの伝記映画の中で、これまでで最も質の悪いものかもしれない。
関連性のあるコンテンツ
先見性や活力に欠ける『バック・トゥ・ブラック』は、亡くなったアーティストの名前を利用して金儲けをするのが主な目的で、そのブランドを掘り起こすことで興行収入やレコードなどの付随的な売り上げを狙っているのではないかという疑念を拭えない。その点では最近の音楽伝記映画の多くと変わらないが、『バック・トゥ・ブラック』の問題は、関係者のほとんどがそれを隠そうと努力できないことだ。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
テイラー=ジョンソン監督の映画は、2002年、ワインハウスが18歳だったロンドンの労働者階級の街カムデン・タウンで始まる。平板な説明的なセリフで物語が展開され、エイミー(マリサ・アベラ)と祖母のシンシア(レスリー・マンヴィル)は、エイミーが反抗的な精神とジャズ好きを持つミュージシャン志望だと説明する。「私はスパイス・ガールズじゃないわ」とエイミーはレコード会社の重役たちに言い、彼らは後に彼女と契約し、スターにすることを約束する。しかし、彼女は、これまで数え切れないほどのミュージシャンに適用されてきたのと同じ、型にはまった盛衰の伝記映画の物語を経験することになる。『バック・トゥ・ブラック』のエイミーは、大成功を収めた後に大失敗に終わり、「マリファナを吸うのは紅茶を飲むのと同じよ」や「あなたは不良少年が好きなのね、エイミー・ワインハウス」などのセリフに彼女の問題が暗示されている。
ワインハウスの物語はごく最近のものであり、生前に徹底的に報道されていたため、『バック・トゥ・ブラック』が自らの存在を正当化するのは常に困難だった。より深い真実を掘り起こしたり、おなじみの物語に新たな角度を見いだすことができれば、どんな映画でも「時期尚早」ということはない。しかし、『バック・トゥ・ブラック』はそのどちらも行っていない。脚本は、難解なジャンルで注目すべき勝利を収めた2007年のイアン・カーティス伝記映画『コントロール』の脚本家マット・グリーンハルによるものだが、出来事の把握はウィキペディア以下のレベルで、さらに悪いことに、ワインハウスという人物についての洞察はほとんどない。
基本的な箇条書きの詳細は関連している。パートナー(そして後に夫となる)ブレイク・フィールダー=シヴィル(ジャック・オコンネル)はワインハウスに異常なほどの愛情を抱いていた。2人は公然と薬物中毒に陥った。エイミーの父ミッチ(エディ・マーサン)は、いくぶん無能ではあったが誇り高い親だった。(最後の点は、亡き娘の財産管理人となった実在のミッチ・ワインハウスの承認を得て作られた映画では十分に強調されていないと感じる人もいるかもしれない。)しかし、物語にはほとんど活気がない。テイラー=ジョンソンのほとんどが堅苦しい演出は、音楽さえも売り込むことができず、エイミー役のアベラがヒット曲を演奏するシーンでは、ワインハウスの皮肉なネオソウルのダークな魅力はほとんど表現されていない。
ワインハウスの悪名高い2008年のグラストンベリーでのパフォーマンスの再現はインパクトがあり、テイラー=ジョンソンのカメラは、酔っ払ったエイミーが叫び声を上げる観客と交流しようとしながら「ミー・アンド・ミスター・ジョーンズ」のパフォーマンスに苦戦している様子を捉えている。残念ながら、このようにワインハウスの心境を私たちに感じさせ、絶頂期のワインハウスがメディアの嵐の中心にいることがどのようなものであったかを伝えようとするシーンはほとんどない。何がこのような独特で個人的な音楽にインスピレーションを与えたのか、どのような心理的要因がワインハウスを依存症や有害な関係に導いたのか、あるいは彼女を悩ませていると思われる多くの悪魔のどれかを何が説明するのかについては、『バック・トゥ・ブラック』にはほとんど興味が示されていない。
『ボヘミアン・ラプソディ』やフレディ・マーキュリー、そして最近の音楽伝記映画とその主題の多くと同様に、『バック・トゥ・ブラック』はアイコンの背後にある人間を明らかにしようとはしていない。その代わりに、この映画はワインハウスをほとんど聖人のように描いている。『バック・トゥ・ブラック』のエイミー・ワインハウスには残酷さが垣間見えるが、映画は最終的に彼女を名声によって悲劇的に破滅した殉教者として、またその技巧が私たちにとって謎に包まれた天才として描いており、アイコンのイメージはますます骨化しているだけである。
これにより、アベラに与えられる役柄は少なくなり、映画の大部分でこの業界スターは漂流したままになる。一貫して信頼できるマルサンとマンヴィルも、それぞれの役柄に個性を見出すことができず、脚本では父と祖母を漠然とした庶民のタイプとしてしか描いていない。常に活気のあるオコンネルだけがその役柄に脈動を見いだし、悪者扱いされているブレイクは、俳優による少年らしい魅力、さらには汚らしい哀愁さえも与えた。オコンネルは『バック・トゥ・ブラック』にとって恵みであり、エイミーとブレイクが激しく別れ、仲直りし、ドラッグを摂取し、また激しく別れるという、映画の最も退屈な部分で歓迎すべき生き生きとした存在である。一方、映画はこうしたことに対する視点をほとんど持たないため、結局は呆然とする以上のことは何もしない。
『バック・トゥ・ブラック』に言いたいことがあるとすれば、あるいは何らかの視点があるとすれば、それは、依存症やこの歌手が抱えていた他の問題ではなく、メディアが最終的にエイミー・ワインハウスの生命力を奪ったということだ。効果的なシーンの 1 つは、安食堂でエイミーとミッチが静かなひとときを過ごしている場面で、窓の外で待ち構えるパパラッチの容赦ないカメラのフラッシュに 2 人の顔がチラチラしている。これは皮肉のかけらもなく語られている主張で、この映画はエイミー・ワインハウスを理解しようと最小限の努力しかしていない。彼女の動機、いや、実際、何が彼女を偉大にしたのかさえも。その一方で、この映画の主な目的と思われること、つまり、今は亡き偉大なミュージシャンを搾取する資産として扱うことを遂行している。