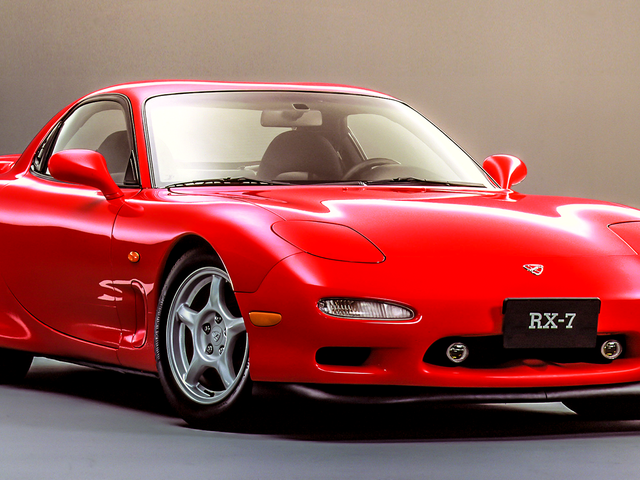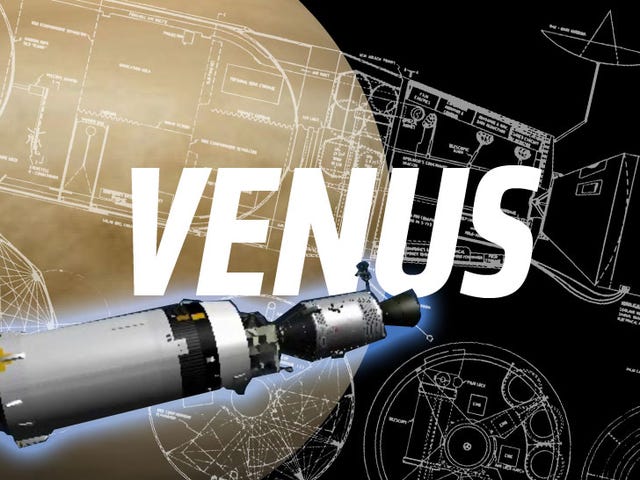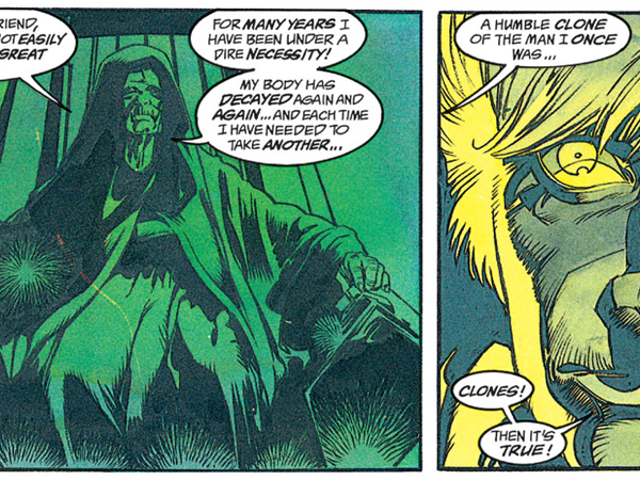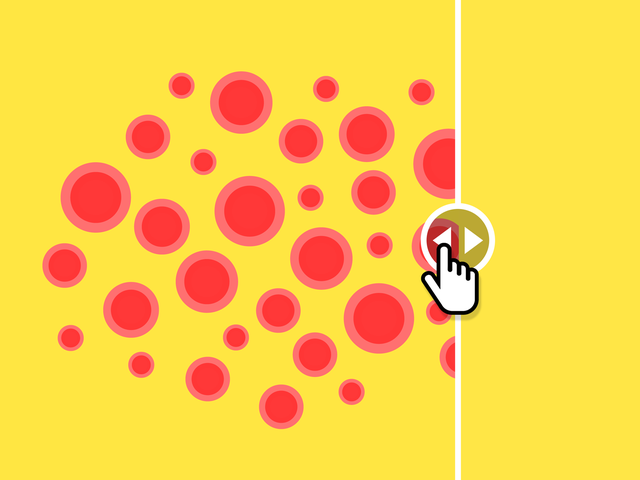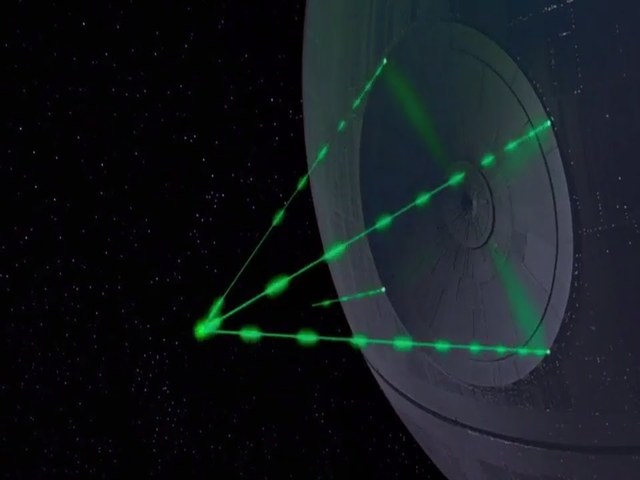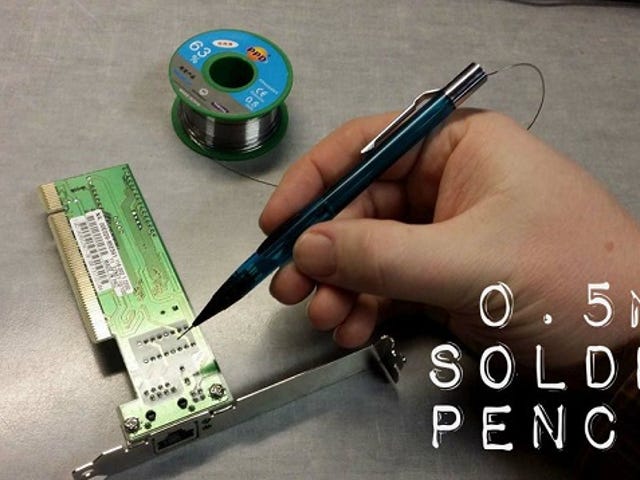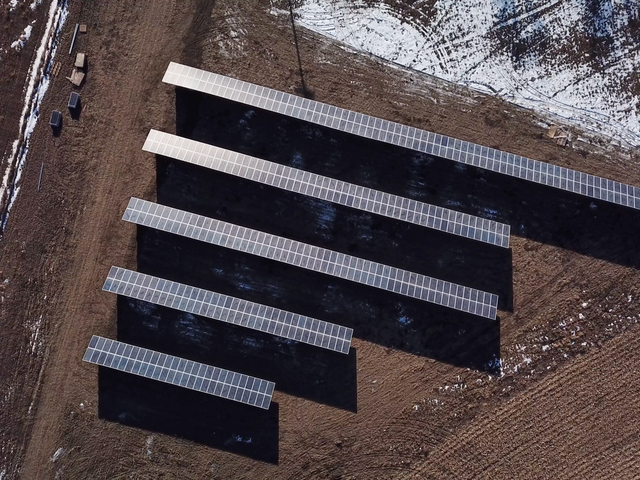映画『ガーフィールド』レビュー:アイデンティティのない映画化はガーフィールド抜きのガーフィールド

知的財産のリサイクルがますます冷笑的になっているこの時代に、 『ガーフィールド』の新たな映画化が実現しても、おそらく驚くことではないだろう。特に、原作のコミックが、あらゆるオンライン世代が再発見するミームの材料として永遠に存在し続けていることを考えると。しかし、『ガーフィールド ザ・ムービー』で最も驚くべきなのは、この映画の冒険が、バイラル文化を完全に無視し、ジム・デイビスの日常生活を描いた漫画を鑑賞するだけの読解力のない子供たちをターゲットにしているという点だ。これは創造的な選択だが、この映画はそもそも誰に向けたものなのかという陳腐な疑問が湧いてくる。『ガーフィールド』のファンは、この映画に懐かしさを感じるようなものはあまり見つからないだろうし、この映画が好きな子供たちは、過去20年間の数多くの一般的なアニメ映画の中に、より近いものを見つけるだろう。
関連性のあるコンテンツ
自分のキャラクターをクリス・プラットそっくりにしたいときに雇う俳優、クリス・プラットが声を担当。オレンジ色のぶち猫のこの化身は、映画の冒頭で観客に直接、自分の出自を語る。野良の父親に捨てられ、操りやすいジョン・アーバックル(ニコラス・ホルト)の腕の中にたどり着く。今では、口のきけない相棒の犬のオディ(ハーヴェイ・ギーエンが声を担当し、世間知らずのバカというよりは不承不承の研修生として描かれている)と一緒に成長した猫となったガーフィールドは、猫のジンクス(ハンナ・ワディンガム)に誘拐されてしまう。ジンクスの怒りから逃れるため、ガーフィールド、オディ、ヴィックは協力して、企業の農場を強盗し、牛乳の積荷を盗む方法を学ばなければならない。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
Aside from an opening montage showcasing how Garfield always gets his lazy, food-grubbing way, there’s not much to distinguish the character by more than his marketable design, while the story mostly adheres to the obvious motions: establishing the divide between Garfield and Vic before having them inevitably reconcile as father and son. That’s not a bad template to follow, given that the target demographic will have barely started school, but The Garfield Movie never has the confidence needed to convey its narrative with a consistent tone. At its best, the action is sub-Looney Tunes slapstick: nothing to write home about, but sufficiently amusing if you don’t want your cartoon characters to look like they’re getting hurt too badly. But then the pacing will grind to a halt as soft, melancholic piano music underpins moments of emotional growth, an apparent bid to appeal to parents’ sense of maturity that unnecessarily drags out the experience. Faced with the choice of boring either kids or their parents, The Garfield Movie can’t even fully commit to being a key-jangling distraction.
It certainly doesn’t help that The Garfield Movie has, appropriately enough, an extremely lazy sense of humor. Director Mark Dindal (The Emperor’s New Groove, Chicken Little) fails to pace the visual gags with the appropriate amount of punch, letting theoretically funny visuals, like a failed lasagna cooking experiment, linger without framing them to provoke a laugh. Garfield’s fourth-wall-breaking quips are generally one step removed from boilerplate observations found in any hack screenplay, and there’s a bizarre fixation on Tom Cruise pastiches, directly referencing both Mission: Impossible and Top Gun in extended sequences that feel like product placement for adults. Ving Rhames is even cast as a heist-coordinating bull version of Luther Stickell, just to really hammer the non-joke home.
In fact, the farther Garfield’s journey deviates from the comforts of Jon Arbuckle’s home, the less it feels like it has any identity at all. The milk heist, complete with Rube Goldberg factory machinations, reads like a reworked Chicken Run spin-off, complete with human character designs that look less like Jim Davis creations than Aardman rejects. Rhames’ character and his kidnapped love interest feel like undeveloped creations of turn-of-the-millennium Disney. Jon’s entire B-plot is spent literally waiting on hold, while Nermal makes a brief, voiceless cameo. These aren’t the grumblings of a Garfield superfan, just the confused musings of someone hoping for any sort of creative vision to shine through.
しかし、ここで重要なのはクリエイティブなビジョンではない。ガーフィールドは単に売れるキャラクターなので、日曜版の漫画のユーモア感覚をスクリーン上で機能するものに適応させる方法を見つけることに誰が関心を持つだろうか。ガーフィールドの笑顔の顔を別の T シャツに貼り付ける口実が他にもある限り、ぜひとも新世代のファンを獲得し続けよう。しかし、ブランドの永続化がこれほど魂のない、弱々しいものであるなら、新しいファンを生み出すことはまずありそうにない。