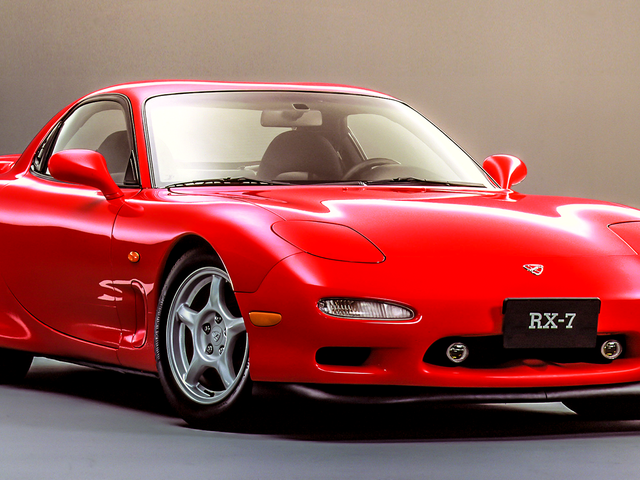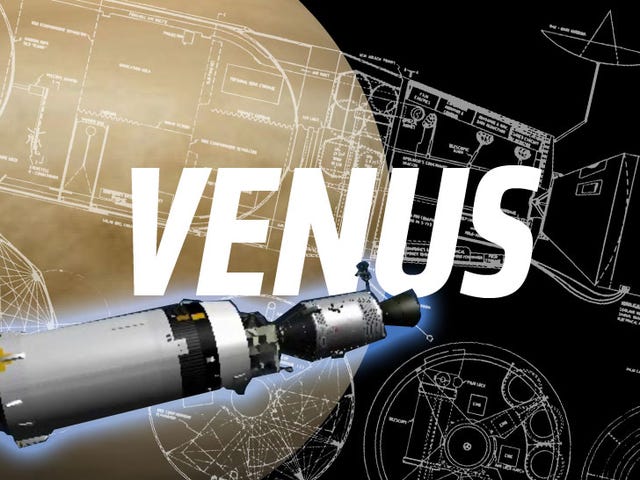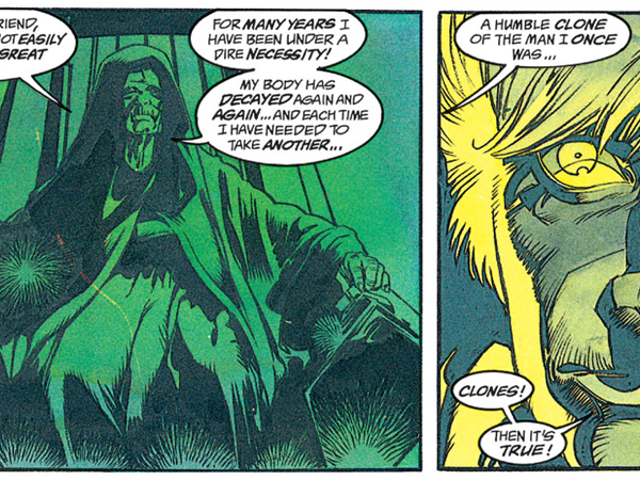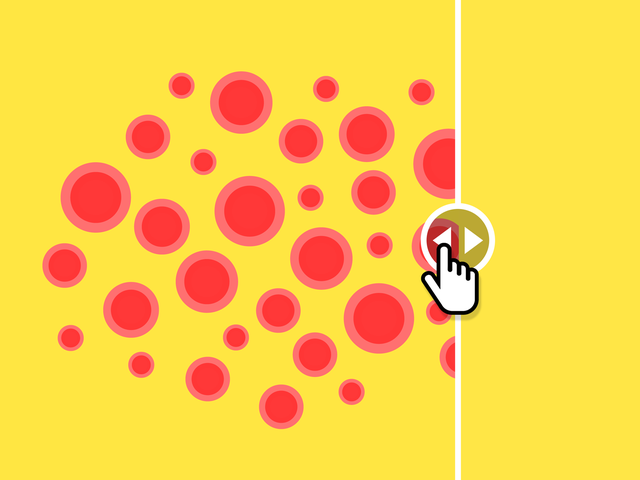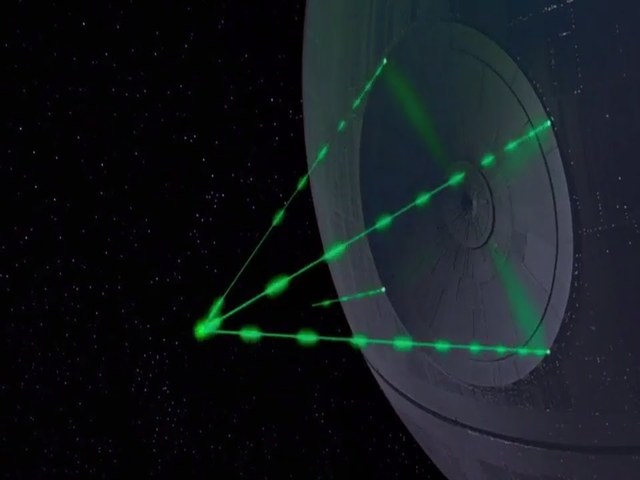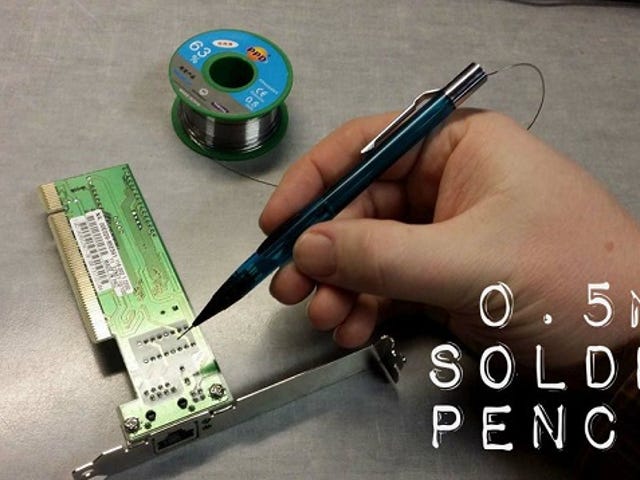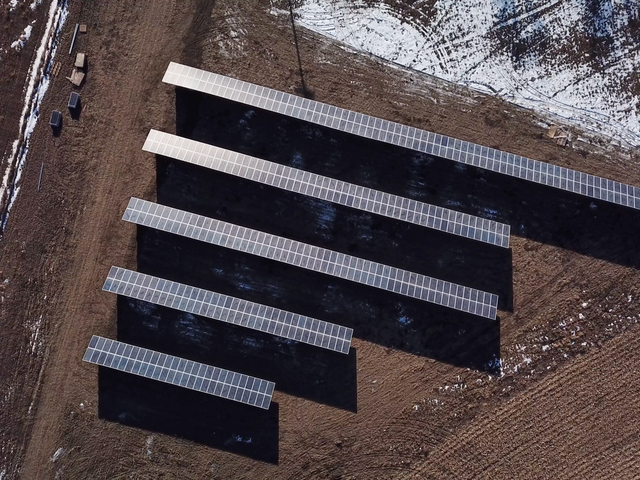MaXXXine レビュー: セックスと暴力の三部作は衝撃なく終わる

80 年代は過剰な時代という評判があり、MaXXXine はそれを過度に受け入れている。Ti West のゆるやかにつながったスラッシャー風ホラー映画三部作の 3 作目は、パーティーでアイディアをぶちまけるコカイン中毒のプロデューサーのような、的を絞らない熱意に満ちている。これは、ビデオ店、実写効果、ポルノ、犯罪ドキュメンタリー、ハリウッド、ジャッロ、ビデオ ナスティ、ユニバーサル バックロット、いわゆる「映画の魔法」という概念に対する一種のダーク ミラー テイクなど、多くのものに対する「ラブレター」と表現でき、おそらくそう表現されるだろう。そして、もちろん、これらの要素はすべてこの映画に存在している。しかし、どれか 1 つに対する関心を示すほど長く続いたり、深く掘り下げたりはしていない。
勇敢でタフなヒロイン(再びミア・ゴスが演じ、プロデューサーも兼任)が妄想の運命に向かって、破片だらけの名声の階段を登り続ける中、多くの出来事があり、ほとんど何も起こらない。冒頭シーンでは、彼女は物議を醸す女性監督エリザベス・ベンダー(エリザベス・デビッキ)のホラー映画のオーディションを受けるために、自信満々にサウンドステージに足を踏み入れる。物議を醸すような冗談を交わした後、マキシンはカメラを見つめ、涙ぐみ、震える独白を披露し、自分が「映画の中でセックスをする」だけの人間ではないことを証明する。彼女は役を獲得する。
関連性のあるコンテンツ
関連性のあるコンテンツ
その後、彼女のハリウッドでの結末は、匿名の脅迫者によって脅かされるが、その脅迫者は実は私立探偵のジョン・ラバット(ケヴィン・ベーコン)であることが判明する。大金持ちの男がラバットを雇い、新聞の切り抜きで「テキサスポルノスター虐殺」(別名X 事件)と呼ばれている事件における彼女の役割をマキシンに思い出させるように仕向ける。彼女がその件について刑事のトーレス(ボビー・カナヴェイル)とウィリアムズ(ミシェル・モナハン)に話すのを長く拒めば拒むほど、彼女の周囲の人々がどんどん死んでいくことになる。この大金持ちの男は、映画「マルホランド・ドライブ」風の強力な変質者のネットワークともつながっており、これは後にマキシンと彼女の「エージェント」テディ・ナイト(愛らしくてひどいかつらをかぶったジャンカルロ・エスポジート)が独自の調査を開始するときに関係してくる。
マキシンのスキャンダラスな職業は、ウェストに、少なくとも部分的にはアメリカで最もみだらな通りを舞台にした映画に、粘着質なコーティングを施す機会を与えている。(それはハリウッド大通りで、観光客を誘う店と下品な快楽主義が混ざり合った独特の雰囲気が、典型的な巧妙なモンタージュで捉えられている) そして、彼はそれを 2 つのシーンで適用している。1 つはポルノ スタジオの舞台裏、もう 1 つはクルージングとハードコアに敬意を表したのぞき見ショーのブースのセットである。しかし、ウェストはその後、刺激的で美的に美しい 80 年代のアダルト エンターテイメントの世界を後ろに減らして、先へ進む。
パスティッシュはウェストの得意技であり、彼はそれを巧みにこなすこともある。『悪魔の館』は70年代後半から80年代前半のホラーの雰囲気を完璧に捉えており、『X』はトビー・フーパーの汚らしい南部風の波長を的確かつ正確に捉え、楽しめる作品に仕上がっている。それに比べると、『MaXXXine』の80年代中盤へのオマージュは洗練されていない。ある場面では、ミア・ゴスがケヴィン・ベーコンを殴り倒し、サウンドトラックで「セント・エルモス・ファイア」が流れる。それは、VHSテープに血が飛び散るのと同じくらい明白で、この映画に実際に登場した別の画像でもある。
また、「ナイト ストーカー」のリチャード ラミレスに関する一連のニュース放送も、文字通りまたはテーマ的にマキシンの物語とつながっているはずなのに、まったくそこにたどり着いていない。アート ディレクションは都会の汚れを真似しているが、それを完全には捉えていない。4:3 VHS フレーミングとデジタル アナログのぼやけた感じの適用は、予想以上に場当たり的だ。マキシンが浅薄なのは、マキシンが生まれた地産の荒々しさと比べると、ハリウッドの粗野さと人工性を意図的に呼び起こしているのかもしれないが、それはひどく宇宙的な解釈だ。もっと単純な説明は、それがこのフランチャイズ、そしてスタジオ A24 全体の主流化を反映しているということだ。
この映画で唯一、その技術が絶妙なのは、実際の血みどろの演出だ。マックスシーンの大半は、馴染みのある顔や懐かしいヒットシーンが心地よく映し出される中を過ぎていく。しかし、例えば、車の破砕機の底から血が流れ出たり、切断された手足が詰まったスーツケースが階段から落ちたりしている場面にカメラが留まると、時間が止まってしまう。息を呑むほど陰惨なこれらのショットは、ウェストの残忍さがまだ残っていることを証明しているため、苛立たしい。ただ、どこへ向かうのか、なぜなのかがわからない、まとまりのないアイデアや影響の寄せ集めの中に埋もれてしまっているのである。マックスシーンに付き従う抗議者たちでさえ、自分たちが何に怒っているのか正確にはわかっておらず、ゴスのひたむきな執念が映画を前に進めるのを妨げている。
『MaXXXine 』の多くの要素のいくつかは楽しいが、それ以上のものではない。マキシンの大ブレイク作『ピューリタン2 』で挑発的な映画監督を演じたデビッキの横暴な演技を例に挙げよう。映画の途中で、デビッキがリリー・コリンズの口に血を塗りつけ、ゴスと握手するシーンがある。その瞬間はエロチックであるべきだと感じられる。しかし、俳優たちはそこに立ち、ためらいながら、研究はされているが感じられない欲望のジオラマの人形のようなポーズを取っている。
主演女優がもっとも情熱的に狂った自分を演じきったときに最高の瞬間が訪れる映画シリーズにとって、空虚さは残念な結末だ。汚いものや卑猥なものを讃えるこれらの映画はすべて、抑制されていない本物というよりは、制御された模倣だ。物事が混乱するのは、誰かが頭を爆発させたときだけであり、それがつながりを生み出す瞬間だ。おそらく、MaXXXineの 80 年代という設定の巧妙さが、このシリーズにこの質をもたらしたのか、それとも最初からそこにあったのか。いずれにせよ、がっかりだ。