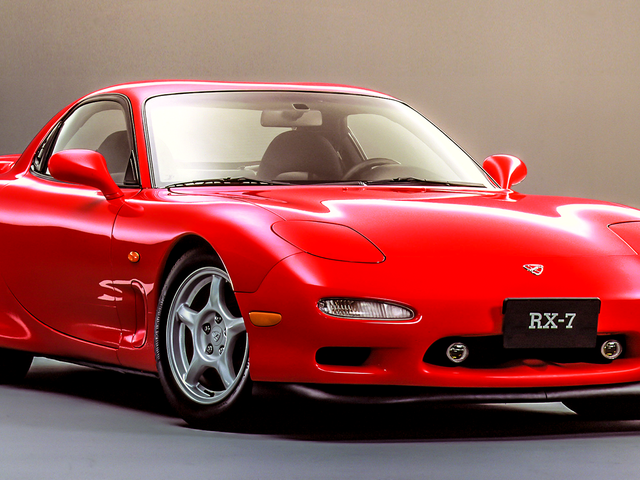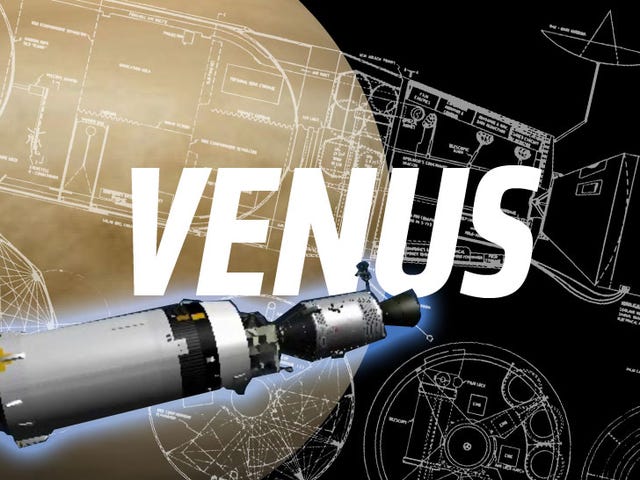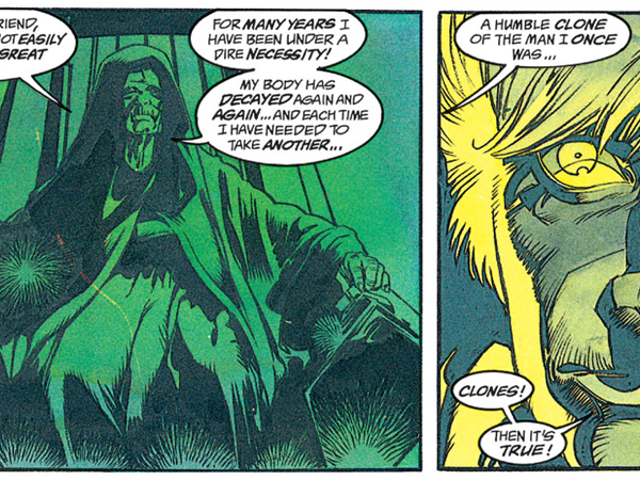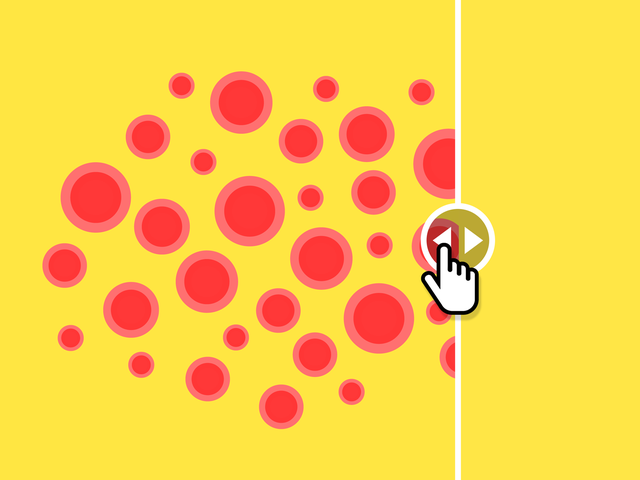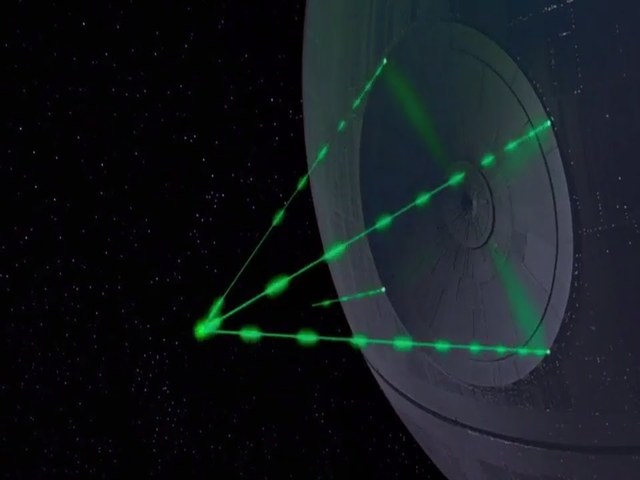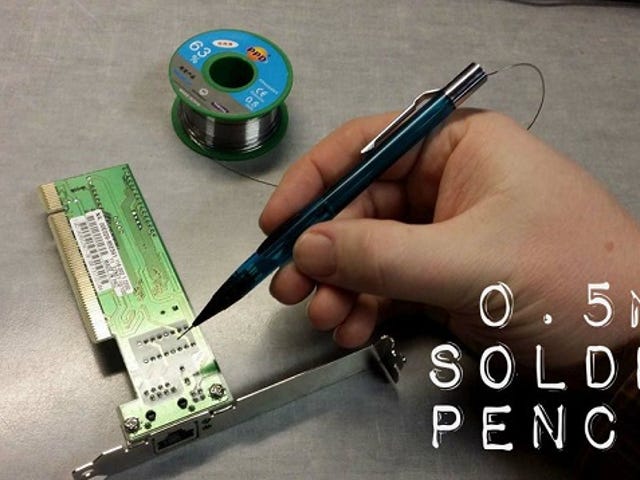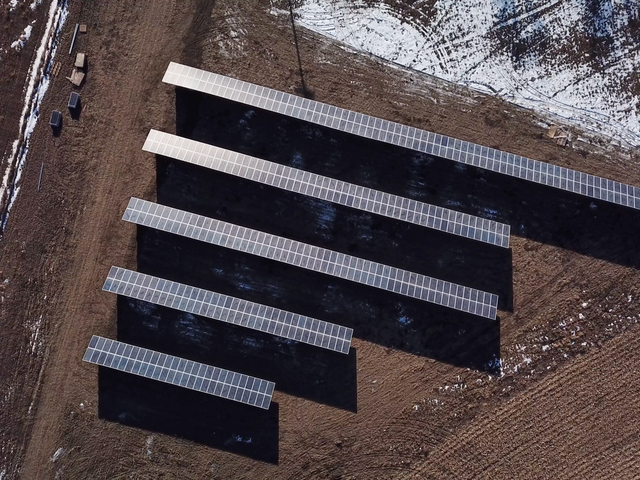『シュラウド』レビュー:デヴィッド・クローネンバーグは失われた愛から目を背けない

デヴィッド・クローネンバーグ の最新作『シュラウド』に関しては、映画祭期間中に特に珍しい体験をした。カナダ映画で、今年カンヌで初公開された数本の映画のうちの 1 本なので、フランスに飛ぶ数日前に観ることができた。そのため、私は 2 週間ほどかけて作品の骨組みを落ち着かせ、私たちの専門である評価に通常必要な瞬時さではなく、完全に反応する前にそのイメージとアイデアをじっくりと眺めることができた。
関連性のあるコンテンツ
過ぎ去ったことを落ち着かせ、反省の対象にするという概念が『聖骸布』の構想の中心にあるのは、皮肉なことだ。『ラビッド』の過激な無秩序さや『蠅い』の低俗な誘惑、あるいは『ヒストリー・オブ・バイオレンス』や『イースタン・プロミス』のような卑猥でありながら崇高な人物研究への完全な回帰を 期待していた人たちは、失望するかもしれない。彼の最後の映画『未来への犯罪』は、彼の「赤い」時代への回帰であり、彼の初期の映画の多くを特徴づけたテーマと色彩を再び強調した。『マップ・トゥ・ザ・スターズ』や『コスモポリス』のような作品は、彼の「青い」時代の一部であり、より冷たく、より知的で、より感情的に距離を置いて形式主義的で、反応的というよりは反省的である。『聖骸布』は間違いなく青いのだ。
関連性のあるコンテンツ
- オフ
- 英語
Since Crimes Of The Future was a dusted-off earlier script, it’s easy to see how it more fitfully conforms to an earlier aesthetic, regardless of whether its conceit worked for you. The Shrouds, meanwhile, is not only a newly written work, it has two unique aspects that help explain both its impact and some of its stylistic quirks: It is highly autobiographical, dealing overtly with the death of Cronenberg’s wife in 2017, and it was originally going to be a two-part show for Netflix, only to be reclaimed and reconstructed for feature-length film.
The truncation isn’t overt, but it’s clear there are more elements packed in here than may be first apprehended, and other slightly underbaked tangents that could have benefited from the larger canvas of a multi-episode journey. The Shrouds is the story of Karsh (Vincent Cassel, coiffed in Cronenberg’s slicked-back gray hairstyle), a businessman who runs a restaurant and a high-tech internment facility, GraveTech, where the surrounding grounds are occupied by a series of tombstones that have video screens embedded in the stones. Each marker is wired for connection through a secure app, allowing authorized users to witness their loved ones as they decay six feet under either on the tombstone itself, or on their mobile devices at their leisure.
This is accomplished in part by the technology that gives the film its title, a Turin-like covering of gray, future-fashion material that serves as a kind of enrobed MRI, presenting both on the app and the stones themselves a fully realized, real-time look at the bodies as they rot.
It’s a redolent metaphor, unsurprising for the sly auteur. The widescreen image and voyeuristic espying of the act of decay on a literal screen is a perfectly metaphoric match for a man whose cinematic output spans biographies of Freud to tales of sociopathic twin gynecologists to telepathic terror that literally leaves heads exploding.
When Karsh starts noticing anomalies on the bones of his late wife Becca’s corpse, he reaches out to his sister-in-law Terry to solicit some answers. Both Becca (in flashback) and Terry are played by Diane Kruger, and while Cassel has been a welcome part of the Cronenberg troupe before, Kruger’s chilly yet engaging air perfectly inhabits this world. The same can not be said for the relatively thankless role that Guy Pearce is given, and his twitchy performance as the aggrieved techie/ex-partner of Terry feels the least dimensional of the leads.
Despite the opening discomfiting scene in a dentist’s office, where Karsh’s teeth cleaning takes on an ominousness that reminds of the torturous equipment in Dead Ringers, The Shrouds settles into an almost gentle mode of paranoia paired with grief. Terry and Karsh explore the meanings of these markers on Becca’s bones, so desperate to find a greater narrative to explain their loss rather than simply accepting the actualities of mortality.
It’s easy to read Karsh and Becca’s connection as a twist on a form of necrophilia, making the GraveTech images akin to the most morbid of slow-moving strip shows, where the final reveal is as unclothed as one could possibly be. We see how Becca’s own battles resulted in a ravaging of her body, losing limbs and cracking bones, so that in life she was transformed into something approaching monstrous. Yet in death, she rests peacefully. There’s only the calm of her unmoving, wide-mouth visage, resulting in a rictus that silently smiles bemusedly at the outside world from her entombment, freed from the quotidian need for meaning that plagues the living.
Cronenberg’s films always ask us to dig deeper, and The Shrouds is no exception. Should we read into Karsh’s moniker the famed Canadian portrait photographer Yousuf Karsh, who captured some of the world’s great leaders and artists and immortalized them in their prime? Or, as a friend and colleague posited, perhaps it’s a sly homophonic twist on Crash, Ballard’s psychosexual tale involving the erotic drive of death by automobile? Perhaps the allusions to Fat Pasha and United Bakers Dairy Restaurant, beloved midtown institutions in the film’s Toronto setting, are ways of further emphasizing Karsh’s commitment to the culture of his late wife, or maybe they’re simply the director’s way of ensuring he gets the best table by name-checking them in a Cannes competition film.
And yet, I saw in the toppled graves visions of Prague, where the stones of Jews from hundreds of years ago were purposely knocked over or repurposed as paving stones. I saw the need for finding succor in conspiracy and ignoring the cold fact of meaningless death particularly disturbing in this world of carefully siloed news, where falsehoods once considered fringe are now parroted by millions. There’s a direct line between dismissing the moon landing and believing Shoah was a sham, just as this film’s insistence on a Chinese conspiracy inevitably resonates for those that tried desperately to shift blame for a pandemic onto an entire people.
私たちは物語を使って無意味なものを理解します。悲しみの不安な性質ほど、この探求をより邪悪なものに変え、私たちを生と死のサイクルの単なる歯車以上のものにしようと、事実の核心をこれまで以上に激しく掴み取ろうとする強力な動機はありません。しかし、私たちを人間にしているのは、まさにこの意味の探求です。そして、カーシュが覆いのように身を包んでいるユダヤ文化の基盤となっているのは、この数千年にわたる処理プロセス、つまりタルムード的に言葉についての言葉、意味についての意味を解き明かすプロセスです。
これが『聖骸布』の核心にあるパラドックスです。意味を解き明かし、私たちの存在の骨をほじくり返すプロセスは、私たちが、どういうわけか、より大きな秘密を暴く難解な答えに実際にアクセスできると確信しているにもかかわらず、毒されています。よく見れば見るほど、より多くのものを見つけます。映画評論家としての役割をこれ以上うまく表現することはできませんが、これはイブからハムレット、そして現代に至るまで、謙虚さを欠いたわずかな知識が悲惨な結果につながる可能性があるという教訓的な物語であることを示すことができます。
私の最初の感想は、クローネンバーグ監督のフィルモグラフィーに『ザ・シュラウド』が加わったことは魅力的だが、期待外れだということだ。クローネンバーグ監督の初期の作品の輝きがまだ少し欠けているし、ダグラス・コックのレンズの描写は監督の要望通りだと確信しているが、ピーター・サシツキーが最後に見せた『危険なメソッド』のような映画的な広がりがまだ欠けている。カッセルとクルーガーは輝いているが、その他の演技は古臭いか大げさすぎる。ストーリーの一部は気取った感じがし、テンポの一部は支離滅裂で洗練されていない。
しかし、私がそれをじっくりと味わったり、あるいは脳内で腐らせたりするにつれ、『シュラウド』のより豊かな側面が明らかになった。おそらく私は意味を見つけようと必死で、自分自身を縛り付け、これは驚異的な映画作品群の中の小さな一章に過ぎないという当初の考えを尊重するほど謙虚になれていないのだろう。しかし、私の最初の考えもその後の考えもどちらも真実かもしれない。なぜなら、クローネンバーグのマイナーな映画であっても、どんな基準で見ても大作であり、簡単に、あるいは熱心に却下する前に、間違いなく熟考する価値があるからだ。もう少し深く見れば、暗闇から見つめ返してくるものを恐れずにいられる。