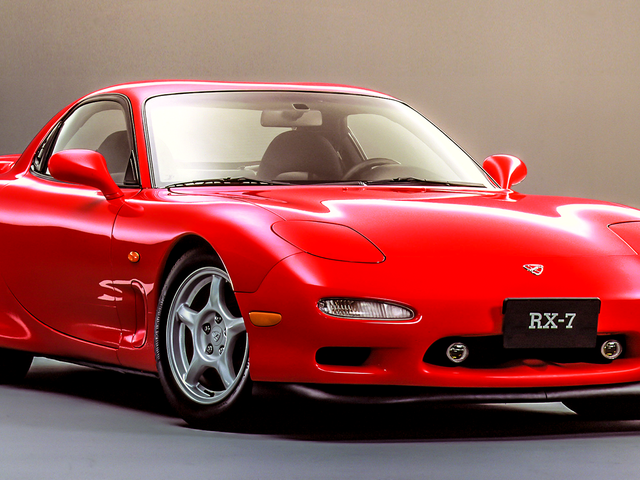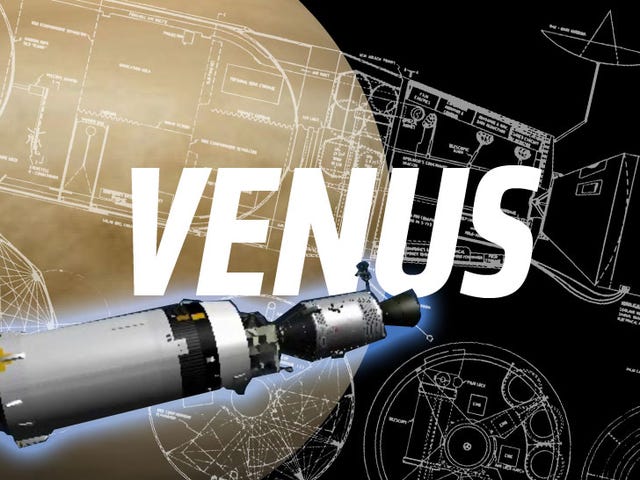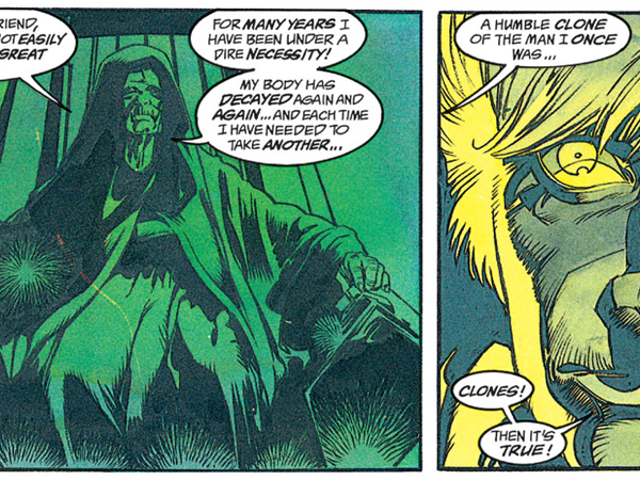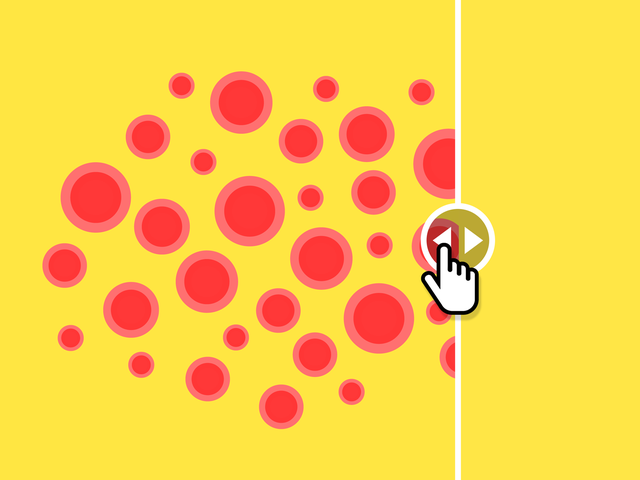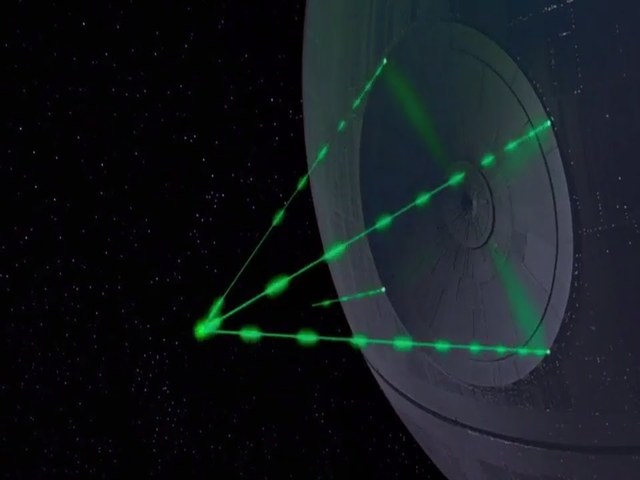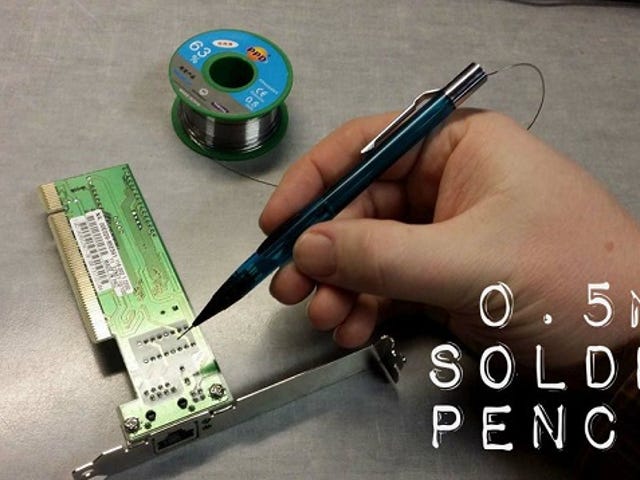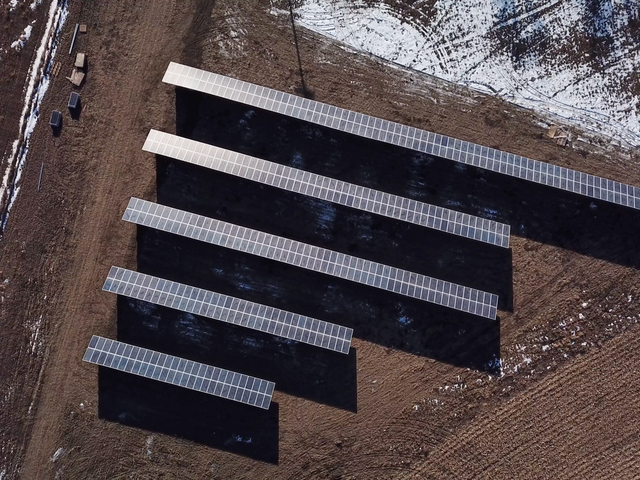オードリー・ヘプバーンとスタンリー・ドーネンは古典的なハリウッドを現代へと押し上げた

「僕たちもあんなふうだったらいいなと思う?」コメディ・スリラー映画『シャレード』の半分を少し過ぎたあたりで、レジーナ・ランパート(オードリー・ヘプバーン)は、後にブライアン・クルックシャンク(ケーリー・グラント)として知られる男に、パリのセーヌ川沿いを歩きながら尋ねる。ブライアンは困惑する。彼らは殺人容疑者について話しているはずなのに、レジーナは予告なしに話題をジーン・ケリーに切り替えたからだ。「 『巴里のアメリカ人』で、彼がここの川辺で、何の心配もなく踊っていたのを覚えてる?」と彼女は詳しく説明する。これはある種、面白い脈絡のない話であり、ある種、気の利いた内輪のジョークであり、もしあなたが『パリの』のスター、ジーン・ケリーと『シャレード』の監督スタンリー・ドーネンの壊れた関係を知っているなら、もしかしたら、皮肉な苦々しい表現でもあるのかもしれない。『シャレード』の陽気で明るい雰囲気にもかかわらず、ヘプバーンとグラントは「そんな感じ」ではない。なぜなら、1963年になっても、彼らはスタンリー・ドーネンと繰り返し仕事をしているからだ。
俳優と監督が何度もコラボレーションしてきたが、その仕事に誇りを持ちながらも、ほとんど瞬時に、あるいは時間をかけて徐々に、お互いに嫌悪感を抱くようになった人はたくさんいる。そうは言っても、ドネンとケリーが一緒にやった作品ほど、緊張した創作関係でありながら、コンセンサスを得て史上最高の作品に仕上がった例は他には思いつかない。ミュージカルを嫌う馬蹄理論のグループや、『巴里のアメリカ人』や『バンド・ワゴン』のほうが優れていると主張する人たちを除けば、 『雨に唄えば』を本当に気に入らない人がいるだろうか?
関連性のあるコンテンツ
関連性のあるコンテンツ
『雨に唄えば』はスタンリー・ドーネンとジーン・ケリーが共同監督し、ケリーが主演した2作目の映画であり、彼らの最初の映画は『オン・ザ・タウン』で、それ自体がジャンルの先駆者となった。その後、ドーネンとケリーの関係は、皮肉にも『いつも晴れ』というタイトルの3作目の映画で険悪なまま終わり、その後それぞれの生涯を通じて、2人(および/または伝記作家)は定期的にお互いについて不平を言い続けた。
このコラボレーションには、解明すべき点がたくさんあるだろう。しかし、ある意味では、ドーネンのキャリアは、史上最高のアメリカミュージカルの共同監督を務めてからずっと、より興味深いものになった。彼はミュージカルや他のジャンルの技術的限界に挑戦し続け、彼の最も成功した実験のいくつかは、共同監督ではない別の俳優、時にはダンスも披露するオードリー・ヘプバーンとの共演だった。3本の映画を通じて、2人は50年代から60年代へとスムーズに移行し、変化する映画界を見事なスタイルで乗り切った。
振り返ってみると、オードリー・ヘプバーンはこの時代を代表するスターだった。1960年代末に完全に引退したわけではないが、最も有名な作品のほとんどを1952年から1967年までの15年間に手がけている。まるで、自分がフルカラーのワイドスクリーンのスペクタクルに十分対応できるほど現代的であったものの、1967年までに幕を開けたニューハリウッドには必ずしも適していないことを認めているかのようだった。その時期に彼女は、『ボニーとクライド』の数か月前にドーネンの『二人で』を公開し、その数か月後には『暗くなるまで待って』に主演したが、その後ほぼ10年間映画界から姿を消し、再び本格的に復帰することはなかった。絶頂期のヘプバーンは、グラント(25歳年上)、グレゴリー・ペック(13歳年上)、ウィリアム・ホールデン(11歳年上)、ハンフリー・ボガート(30歳年上)、ゲイリー・クーパー(28歳年上)といった俳優たちと共演し、自分より先に出演したアメリカのスタジオ映画に片足を踏み入れているように思えた。ドーネンのミュージカル『ファニー・フェイス』で、ボガートより7か月年上のフレッド・アステアと共演したときほど、この年齢差が明らかになったことはめったになかった。
しかし、年齢差に関するありきたりの議論だけでは、この話のすべてを語ることはできない。伝えられるところによると、ヘプバーンはアステアとの仕事にこだわったが、(それぞれのキャリアのこの時点では)全盛期を過ぎたアステアが30歳も年下の共演者を主張するよりも、結果が出そうな要求のように思える。(もちろん、前代未聞のことではない。とはいえ、1957年のフレッド・アステアは、1997年のジャック・ニコルソンとはまったく同じではなかった)。さらに、アステアとヘプバーンは『ファニー・フェイス』で燃えるような相性を見せたとは言えないが、彼が映画の中にいるおかげで、新旧の考え方の衝突を(軽くではあるが)明確に扱った映画にふさわしい、昔ながらの心地よさが映画にもたらされている。アステアはファッション写真家のディック・エイヴリーを演じ、クチュールよりも哲学に興味を持つ書店主のジョー・ストックトン(ヘプバーン)に新たなミューズを見出す。ディックは、クオリティ誌の撮影のために知性と美貌を融合させたいと願い、ジョーをパリへ連れて行きます。街を見るチャンスに彼女は魅了され、二人は自然に歌い、踊り、恋に落ちます。
20世紀のアイコン、オードリー・ヘプバーンが、あり得ないファッションモデルを演じるというのは、もちろん馬鹿げているし、ジョーの興味をパロディ化した映画は、アステアの『バンド・ワゴン』と似たような反知性主義に耽っている(ミュージカル史上最も不快な非ブラックフェイスのミュージカルナンバーで、スターたちが赤ん坊のように着飾るミュージカルでは、なぜその傾向が許容されることが多いのかは謎のままだが)。しかし、 『ファニー・フェイス』の形式は、十分に現代的であり、ドーネンは、このミュージカルを堅苦しいプレゼンテーションではなく、より映画的な方向に推し進め続けている。
オープニングナンバー「Think Pink!」は、バービーにインスピレーションを与えたのかもしれないが、そのリズムは、華麗な歌やダンスよりも、編集、色彩、イメージの中に見出されている。後にドーネンは、映画のタイトルソングの舞台として赤色に照らされた暗室を使用している。ヘプバーンが「変な顔」をしているというアイデアは受け入れがたいものだが、照明によって少なくとも一時的に彼女の美しさがぼやけている(その後、ディックが映画の中で作成した、彼女の顔の特徴の極端なクローズアップのプリントによって、その美しさは再明確化され、抽象化される)。

しかし、この映画の本当のハイライトは、訓練を受けたバレリーナ、ヘプバーンによる映画の途中のダンス ナンバーです。ただし、彼女はバレエの精密さを捨て、自由でビートニク風の爆発的な動きを披露しています。彼女は、あまりスタイリッシュではないミュージカルと比べて立体的に感じられる鮮やかさで、アンダーグラウンド クラブの濃い赤、緑、青の照明の中を疾走します。「堅苦しくしたり、かわいらしくする必要はありません」とジョーは言い、ダンスを自己表現として推奨し、その直後に元気いっぱいのナンバーを披露します。
ヘプバーンは、ドーネンのミュージカルに対するますます洗練されたアプローチと解釈できるものを表現している。だからといって、彼のミュージカルの演出が形式的に印象的ではないということではない。あるいは、広い意味でキュートでもないということでもない。というのも、ヘプバーンとアステアはどちらもさまざまなミュージカルシーンで本当に愛らしいからだ。しかし、この映画は登場人物を動かすためにキュートな言い訳を探してはいない。カメラが別の現実を作り出し、歌とダンスを提供するという、より純粋な可能性の感覚によって活気づけられている。それは、『オン・ザ・タウン』や『雨に唄えば』、そして『七人の花嫁』のような極めて退行的な作品にも見られる。 『七人兄弟の七人の花嫁』では、色彩、動き、独創的な構図の乱舞によって、集団ストックホルム症候群に基づくロマンスがほとんど不明瞭になっている。『ファニー・フェイス』ではドーネンの手法がさらに前面に押し出され、アステアも勇敢にそれを手助けしているが、それを完全に体現しているのはヘバーンである。
『ファニー・フェイス』はドーネン最後のミュージカルではなかったし、ヘプバーンの最後のミュージカルでもなかった。彼女は『マイ・フェア・レディ』で歌声なしで主演していたことで悪名高かったからだ。しかし、このジャンルの文化的重要性が低下していたことを考えると、最後のミュージカルだったと言ってもいいだろう。6年後、2人は『シャレード』で再会した。この作品は、舞台(パリ)が似ており、ヘプバーンとクラシックハリウッド(今回はケーリー・グラントが体現)を結びつける年齢差のある組み合わせ、色彩構成(明るい)、娯楽性(極めて高い)があるにもかかわらず、スタイルはいくぶん先進的ではないように感じられる。ヘプバーン/ドーネンの他の2作品と比べると、一流の素材を使ってはいるものの、どちらかといえばパスティッシュに近い。ヒッチコック風の冒険に、時々スクリューボール風のひねりを加えた会話が盛り込まれている。ヘプバーン演じるレジーナは、離婚間近の夫が死亡し、魅力的な男性(グラント)が生きていて、色っぽくて謎めいていることから、盗まれたお金を探すミステリアスで命の危険もある捜査に巻き込まれる。

ヘプバーンはアルフレッド・ヒッチコックと映画を作ったことはないが、この作品と『暗くなるまで待って』を見る限り、少なくとも理論上は、彼の楽しい作品に出たいと思っていたようだ。そういえば、ドーネンも、ある意味そうしたのかもしれない。ヒッチコックの『汚名』から12年後、 『シャレード』の5年前に、ドーネンはグラントとイングリッド・バーグマンを再びタッグに組み、薄っぺらいロマンティック・コメディ『無分別』を製作した。この映画は、その洒落たアニメーションのクレジットやヘンリー・マンシーニの音楽から想像されるほど大胆に様式化されているわけではないが、『シャレード』は『無分別』よりも盛り上がっている。言い換えれば、バーグマンの冷静なバージョンよりも、ヘプバーンの疲れ切った優雅さを反映しているのだ。ヘプバーンが昔のハリウッドスターたちとヨーロッパを旅したという点では、『シャレード』は『ローマの休日』ほどロマンチックでもなければ、『ファニー・フェイス』ほど目を引く構成でもない。この映画は、ヘプバーンとグラントの掛け合いを避けたいように感じられることがあるが、それは当然だ。視覚的なレベルでは、映画の後半でドネンがグラントとヘプバーンの間をスピードを上げて行き来する徒歩追跡シーンなど、緊張感を高める重要な編集が最も魅力的である。彼らの次の、そして最後の共演作では、再びヘプバーンがヨーロッパを旅することになり、ドネンの編集の選択がさらに強調される。
ドーネンとヘプバーンはともに1967年を多忙な年とした。彼は人気コメディ『めまいがするほど美しい』 、彼女は前述の『暗くなるまで待って』を手掛け、さらに2人は『二人で道へ』でもう一度共演。この作品ではドーネンの形式ばった遊び心と『ファニー・フェイス』や『シャレード』では決して見られなかった荒涼とした雰囲気が融合している。ドーネン作品で初めてヘプバーンはほぼ同世代の人物と共演している。アルバート・フィニーは共演者とほぼ同い年を演じるが、実際はヘプバーンより7歳年下である。このタイムスリップドラマでは、マーク(フィニー)とジョアンナ(ヘプバーン)は若い旅行者として出会い、やがて13年間の結婚生活を送ることになるが、私たちはその様子を車での旅行を通してのみ見ることができ、一連の非線形シーンとして編集されている(タイムラインを整理すると、合計5回の旅行と、マーク一人の短い寄り道がある)。

ドーネンは、これらの物語を、あまり明白なシグナルなしに織り交ぜている。字幕も、ゆっくりとフェードアウトもせず、過去と現在を融合させる視覚的なトリックもいくつかある。たとえば、異なるタイムラインのカップルの複数のバージョンが、彼らの乗り物を通して同じフレームを占めているように見えるなどだ。彼のミュージカルと同様に、しかしまったく異なる目的で、ドーネンの手法は、私たちが時系列をごちゃ混ぜの自由連想記憶として体験する別の現実を作り出す。皮肉な韻を踏んでいるもの(何年も離れたビーチについての異なる不満)もあれば、ただ単に不快なだけのもの(深刻な夫婦ドラマと、マークとジョアンナが別の非常に不快なカップルと一緒に旅行するときの茶番劇の幕間が並置されている)もある。
この野心的な取り組みを通じて、ヘプバーンは観客の目印となっている。彼女のエレガントなスタイルに気を配る人なら、髪型や衣装が頻繁に変わることに気づくだろう。それが時の目印となり、映画スターのキャリアの進化を観ているような体験をシミュレートしている(ただし、彼女のいつもの衣装デザイナーが『トゥー・フォー・ザ・ロード』では働いていなかったことは特筆に値する)。映画がマークとジョアンナの1954年で始まるのはおそらく偶然かストーリー上の都合か、あるいはその両方だろう。ヘプバーンが主演女優としてのキャリアを始めたばかりの頃だ(『ローマの休日』は1953年、『麗しのサブリナ』は1954年公開)。しかし、主演女優の中心的なフィルモグラフィーとほぼ同じ時期を描いた映画を観ると、やはり回想の感慨深さを感じる。実際、ヘプバーンが『トゥー・フォー・ザ・ロード』に持ち込んだ重荷は、この映画に計り知れないほど役立っている。フィニーの好演のせいではない。脚本では、彼の演じるマークは、不満を言い、うぬぼれ、オードリー・ヘプバーン演じるキャラクターに会えたことにまったく感謝していないかのように、過度に抗議しているように描かれている。おそらくそれが、ヘプバーンのずっと年上の共演者たちが、本来あるべきほど不快ではない理由だろう。たとえ彼らのキャラクターがふざけて少し見下すような態度をとったとしても、彼らのほとんどは、自分たちが(特に面白くはないが)顔を見つめているのがどんな存在なのかを本質的に理解しているように見える。
ドーネンもそのことを理解しているようだ。ヘプバーンの存在によって、ミュージカル、スリラー、恋愛ドラマなど、ハリウッドのおなじみの定石にバリエーションを持たせる余裕が生まれるのだ。ヘプバーンがドーネンの実験を同じ程度に必要としていたと主張するのは難しい。ドーネンが実験をしなかったとしても、『ローマの休日』、『麗しのサブリナ』、『ティファニーで朝食を』などがある。それでも、それらの映画は、ドーネンと共演した映画と比べると伝統に縛られているように感じる。ドーネンと共演した映画では、奇妙な角度から彼女にアプローチする傾向が強く、時には文字通り、例えば『ファニー・フェイス』で本棚の反対側からいちゃつくショットや、 『トゥー・フォー・ザ・ロード』で彼がカップルを眺める時には極端な視点からアプローチしている。彼女はエレガントな映画スターであることに変わりはないが、『ファニー・フェイス』での文字通りの柔軟性(明らかにすでに持っていた)は彼女の中に残り、観客がオードリー・ヘプバーンらしさをだいたい理解したと思った後でも、新たな発見の感覚を与えてくれるのだ。
「面白い表情をしましょうか?」と、ジョアンナは『トゥー・フォー・ザ・ロード』でマークに尋ねる。これは意識的かどうかはわからないが、ヘプバーンとドーネンの最初の共演映画へのオマージュである。答えはイエスではないようだ。しかし、二人は一緒に、その方向に進んでいく。他のダンサーは必要ない。