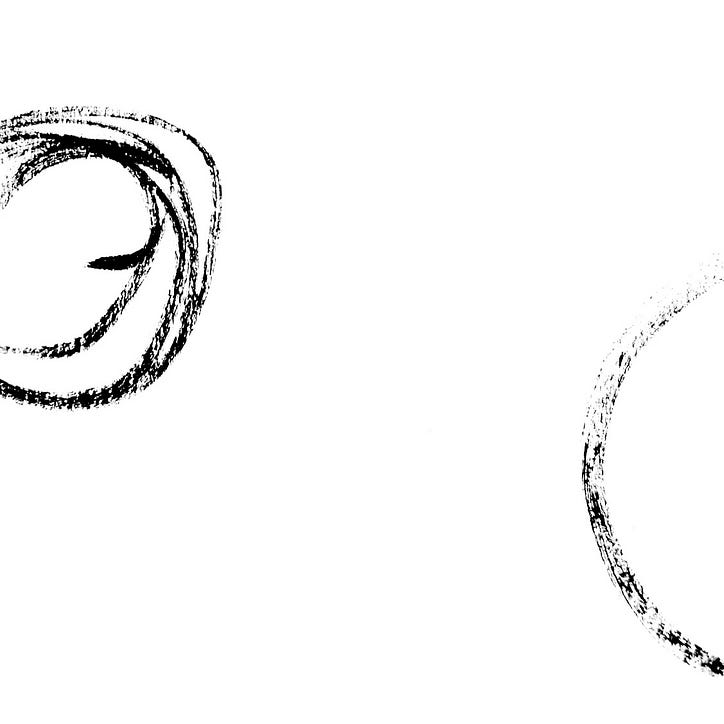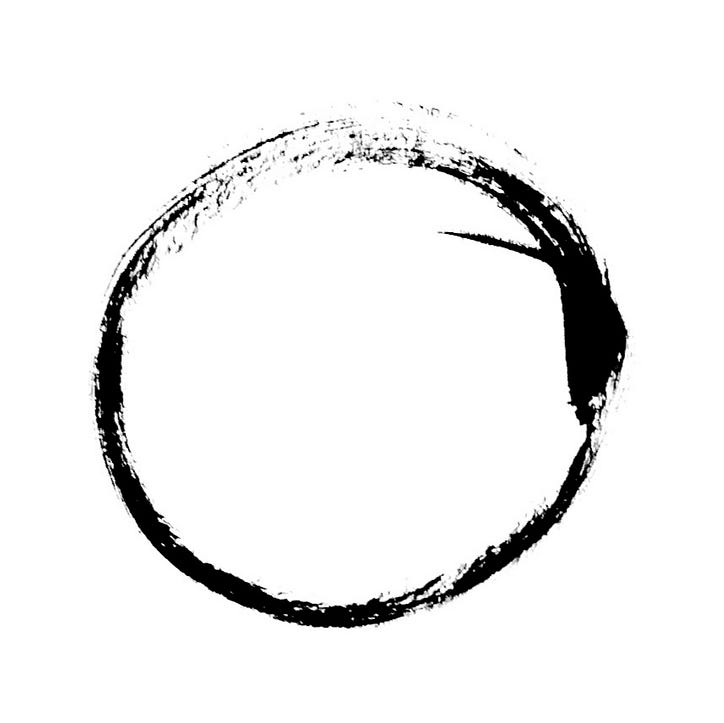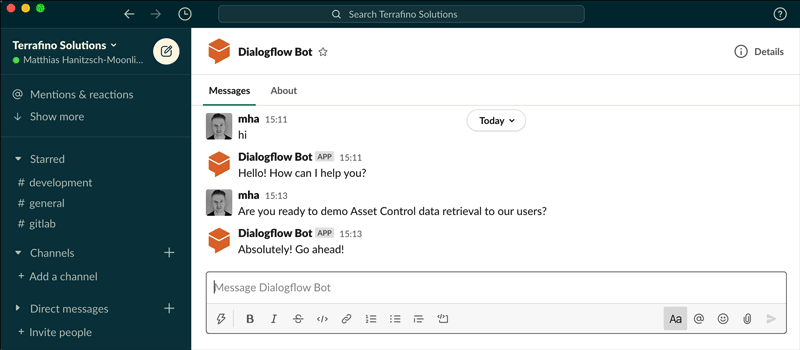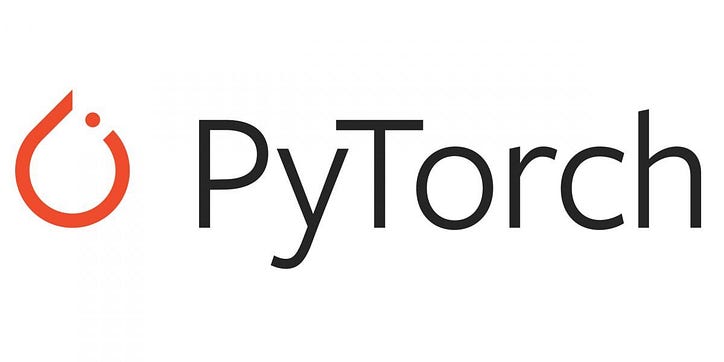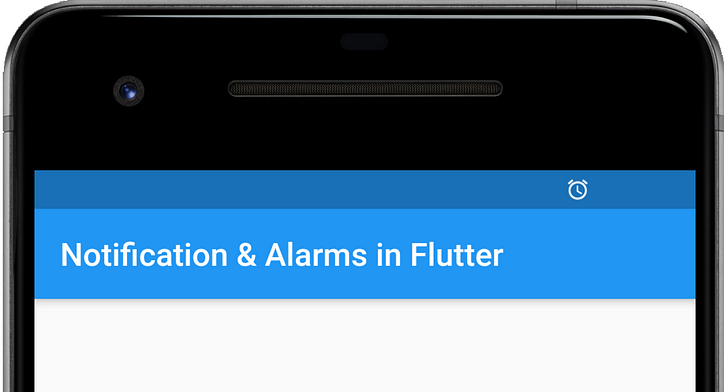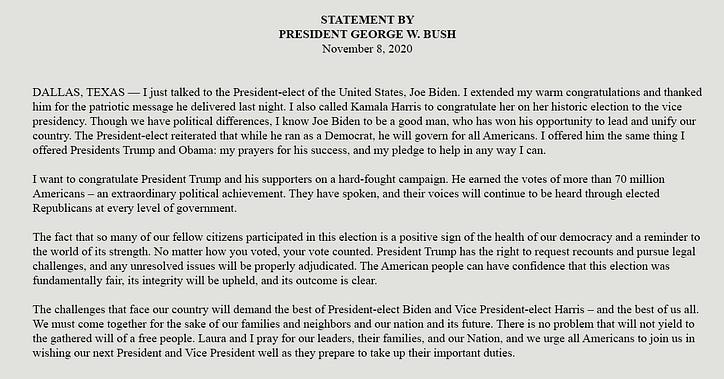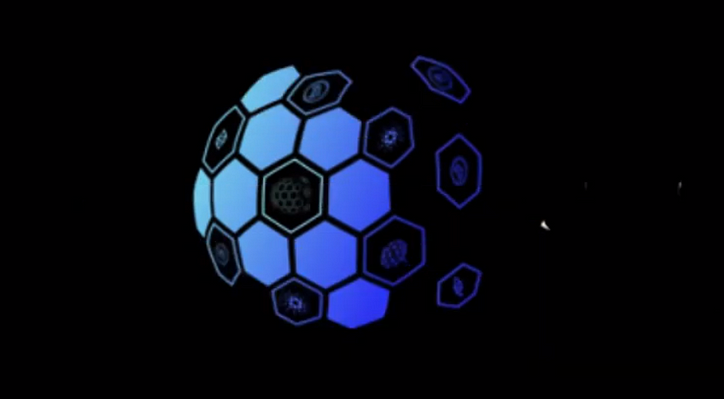漬け物
彼は、天井の天窓から差し込む太陽を受け止める千一の瓶の中で生きているのが発見されました。ほとんどの瓶には蓋がなく、中身を詰めるよう求められていました。彼らを収容していた部屋は小さく、泥室とキッチンの間に奇妙な位置にあり、木の床は数十年の湿気で柔らかくなり、忘れられた雑誌の表紙が理由も理由もなく壁に貼り付けられていました。夏にはコオロギの音が聞こえました。彼はそれを使ってゲームを作り、彼らが歌っている瓶を見つけ、その中にピンポン玉を落とし込もうとした。しかし、ある蒸し暑い夜、特に不快な鳴き声が聞こえたので調査に行くと、サルサの瓶の底でコオロギが半分潰れているのを発見した。彼は瓶を外に運び、障害を負った虫を手に放り込み、堅い拳でそれに慈悲を与えました。

マニオクは――そうです、彼の両親はお気に入りの塊茎にちなんで彼に名前を付けたのです――その部屋には、瓶に囲まれた小さな薄汚い肘掛け椅子を置くのに十分なスペースを空けていました。今ではその布地は、丸いお尻、飛び跳ねる犬、棚に並べられるのを何週間も椅子に座ったままの瓶の入った重い箱に囲まれた生活によって、ぺしゃんこになってしまいました。その椅子はロッカーになっており、揺れるたびにうめき声を上げた。マニオクは、リクライニング機構を修理する必要があることをいつものように忘れて、右側のレバーに手を伸ばしてリクライニングチェアを立てました。フットレストが故障しました。それを修正するのではなく、彼は単に体を横に回転させてぎこちなく腕の上に足を掛け、腰から上をひねって体重を椅子の背もたれに預けました。
時間の経過により、想像できるほぼすべての種類の瓶がマニオクの在庫に収まるようになりました。早い段階で、彼はそれらを整理するいくつかの方法を試みました:身長別、パン秤を使用したグラム重量別、一般的な形状別(背が高いか幅が広いか、一般的な円形か特製ジャムの八角形か)。あるインドの夏、彼は図書館のような十進法を試し、瓶の底にチョークマーカーで書きましたが、コレクションがある程度の扱いやすいサイズを超えたとき、彼は単に空きがあればどこにでも瓶を置き始めました。かつてハラペーニョのピクルスが入っていた瓶の中に、ベビーマスタード瓶(ホリデー用の肉セットに含まれる10セント硬貨ほどの小さなナゲット)が押し込まれていた。巨大なマヨネーズ瓶は、人々がプランターとして使用したりテラリウムを作るために販売できたかもしれません。パンデミックの急増で残ったメイソンジャー。
妻が戻ってきたとき、彼は半分寝ていた。彼女はコーヒーと卵のパックを取りに外に出た。彼女は27年間、電子レンジで12時間と1分間、13日と1分間行方不明になっていました。それでも、彼女が家に入っていくとき、彼は彼女の足取りに気づいた――とぼとぼと足早に。風雨にさらされ、枠が金網で留められた網戸が、彼女の後ろでシューシューと音を立ててカチッと閉まった。彼女はキッチンのテーブルにショルダーバッグを置き、ため息をつき、探検を始めた。変化のない壁に沿って指で軽くなぞり、戸口を通過するときにダンサーのようにくるくると回った。
「リリアナ」マニオクがつぶやいた。"ここに。"
彼女は彼の声の細流を追って、瓶の部屋に出てきました。太陽はますます強くなり、天窓から降り注いで、夫の周りのすべてが輝いていました。リリアナは立ち止まり、その光景を眺めた。コオロギが鳴き始めると、彼女はマニオクが身をかがめて瓶を村から持ち上げ、唇に指を当てて、長くそよ風でシャッシャッという音を立てて盗聴器を静かにするのを眺めた。
"あなたは変わりました。" 彼女は両手を握りこぶしにし、いつものように高い位置にある腰骨の上に置き、着ていた特大のシーフォームTシャツとサスペンダーストラップ付きのデニムショートパンツから突き出させた。彼女の足には、毛羽立った縞模様のくるぶしまでの高さの靴下があり、その上には一致する金のアンクレットが取り付けられていました。彼女の髪は、皮膚に触れる頭の左側を除いて、肩まで緩やかなウェーブを描きました。空き地には花束が描かれていました。
"もちろん。あなたもそうでしょう」とマニオクは椅子の背にもたれかかりながら答えた。「あなたの耳の周りにあるのはシャーピーですか?」
彼女は手を伸ばして、絵に沿って指をなぞりました。「アーティストと私はいくつかのアイデアを検討しています。どう思いますか?"
マニオクは頭を向け、中型の瓶のコレクションに目を向けた。そこにはドライトマトが入っていたと記憶している。「背景にツタを使ってもいいと思います。」彼は深く息を吸い、目を閉じて6つ数えた。雲が一瞬の思いのように太陽の前を通り過ぎ、部屋が瞬きした。
「出発したと言ってください。」リリアナは一度にいくつかの瓶をハサミのように指で掴み、脇に置き、ナイトスタンドに座るスペースを作りました。彼女は膝を胴体に抱き寄せた。「少なくとも一度は辞めたことがあると教えてください。」
「もう行ってしまった」と彼は息を吐きながら、半開きの目で妻を見つめた。「確かに、出発しました。」
"あなたはどこにいってしまったのですか?"
「ああ、どこにでも少しずつね。」彼は薄汚れた肘掛け椅子の上で前方に回転し、手を伸ばし、再びレバーを踏んでフットレストをとろうとした。リリアナは何も出来ない様子を見つめていた。マニオクはそれをガタガタと動かし、ハンドルの磨かれた木と内部の壊れたバネの針金のような音に突然怒り始めた。取っ手が折れたとき、彼は長い顔でそれを見つめ、背の高い円筒形の瓶の中に立てて突っ込んだ。それは、10年前にブラックヒルズの町の近所のバーで1ドルで購入した卵のピクルスの容器だった。"食料品店。映画。ビーチです。」
リリアナは眉をひそめた。「ビーチ?どこのビーチ?」
「オレゴン州の海岸までロードトリップしました。素晴らしかったです。」
「あなたは手紙の中でそのことについて何も言っていませんでした。」
「手紙には言えなかったことがたくさんある。」
外の風が強くなり、家の躯体を叩く音が聞こえた。乾いた人工物――木の葉、根こそぎにされた背の高い草、地球の反対側に立つホットドッグの脂っこいナプキン――は、サイアノタイプのように見えて、天窓を横切って飛び回った。「うちの犬はどうなったの?」リリアナが尋ねた。「ボンゴ?」
「何が起こったと思いますか、リリー?何年ぶりですか?彼は死んだ。" 妻の顔に不安の表情がよぎったとき、マニオクさんは助けようとした。「平和的に」と彼は付け加えた。「一晩中眠っています。」
「もう一匹犬を飼ったんですか?」
「ああ、確かに、確かに。次にブレアがやって来た。彼女に与えられたのはわずか 1 年でした。彼女はフェデックスのトラックに近づきすぎて踊りました。その後にヴィニーがやって来た。彼を子犬から上の天国まで育てました。」
「そんなに長い間行ってなかったんだ。」
マニオクはうなずき、しばらく彼女と目を合わせることを避けた。"はい。あなたはちょうど今まで〜だった。"
リリアナは瓶をつかみ、手の中でひっくり返し、底にチョークが残っていることに気づきました。復活した太陽に彼女は目を細めた。「ご存知のとおり、私も手紙では言えなかったことがたくさんあります。」
マニオクは思わず笑みを浮かべた。"そんなこと知ってる。" 彼は紙の汚れを見ていた――彼女が何かを書こうとしてボールペンのペン先をセットしたところ、ペンが止まっている間にインクが外側に染み出し、にじんでしまった彼女の手紙の跡だ。「もしかしたら、私たちはそれほど変わっていないのかもしれない。あまり。"
「何もアイデアが浮かばない」リリアナはナイトスタンドから飛び降りて部屋から姿を消し、再び壁に沿って指をなぞり、家や空気を読み取った。彼女のパートナーが侵食されていく速度。どちらかと言えば、彼らの愛情が残ったもの。
マニオクは若い頃、実際は賢い 17 歳の少年で、森を楽しんでいた。彼の家族は、コロンビアのアンデス山脈にある質素な3部屋の住宅に住んでいたが、その敷地は、国の色とりどりの鳥たちが飛び交い、さえずりながら飛び交う深い松の木立に隠されていた。夕方になると、彼は木々の中に迷い込み、時には数キロメートル離れたところに行きました。彼の両親はヒッピーではありませんでしたが、非常に他人に干渉せず、神が子供たちを家に送り届けてくれると信じていました。神は彼らの失踪や死を正当な理由がある場合にのみ許可すると考えられていました。
彼らは村の跡地から歩いて10分のところにあり、歩道上で1ペニーほどの大きさの集落でした。彼らが送った人生は美しいものでしたが、簡単ではありませんでした。バスルームの配管やその後の携帯電話の通信範囲などの現代的な快適なものは、彼らに届くまでに時間がかかりました。インターネット会社が町にやって来たとき、電線やモデムなどが、3 台のガタガタのあずき色のランドクルーザーの荷台に積まれていました。コミュニティ全体がポーチに座って、赤ちゃんを膝の上で上下させながら、作戦が進行するのを眺めていました。彼らは額に汗を流しながら辛抱強く待った。事実上の市長であるヘラルドは、初めて Web ブラウザを開いた人でした。町の人々は彼の背中をたたいて、彼がいかにリーダーであるかを思い出させました。一瞬、彼らは世界に見られ、その起源が何山も離れているにもかかわらず、彼らを巻き込む壮大な計画につながっていると感じました。
Manioc watched all these happenings from afar — first, through his father’s legs as a toddler, his arms gripped around the knees as if to steady himself, and then always from a distance as he grew older. He’d perch upon a roof fifty yards off or find a window in an abandoned home on the main strip of the village — the closest thing to an urban center they’d known — quietly eating an arepa while he watched the town enter a frenzy about the latest cultural or technological arrival from afar. On the rarest occasions a politician would pass through, or at least a vehicle representing them. The candidate’s face beamed from a cloth banner strung along its sides, and diesel fumes curled in the air with the megaphone promises. Manioc learned early on to shake his head and ignore the displays, sensing an inherent emptiness in it. He didn’t hold the village accountable for the attention they paid; they knew their trades and their worth, and they knew their own hope. They certainly knew joy. Manioc kept himself aloof so as not to take that from them, consciously or not.
彼は、そのよそよそしさがこれほど近くまで自分を追ってくるとは思っていなかった。アメリカに移住するとき、彼は家族に、医学の学位という金波に乗り、家を建て替えるための富を持って戻るか、家族を取り戻してアメリカに連れて帰って一緒に暮らすと約束した。彼は彼らがいなくなるともっと寂しくなるだろうと予想していた。しかし、距離が離れたことで、彼の中に新たな利己主義が芽生えた。学校の友人たち、特にアメリカ人だけでなく、北京出身のユー・フェやマラケシュ出身のイスラム教徒たちも、それは正義の利己主義だと言った。「自分が確立するまでは、家族に自分が与えたいものを与えることはできない」と彼らは訴えた。「しばらくは心配しても大丈夫です。」
最初、彼はその議論に同意できなかった。マニオクは家庭についての不安を抱えていたにもかかわらず、家族に対する粘着質なこだわりや、恥ずかしがることのない献身的な態度を気に入っていた。すべての質問に答えてもらうのは、すべての答えが気に入らないということを受け入れることができる限り、理にかなっています。しかし、数カ月後、彼は飲みに出かけることが増え、町の外へ旅行するようになった。彼は、ユ・フェとイスラムがキャッツキル山脈で時間を過ごせるように、キャンプ用品を大量に購入した。彼は安い車を購入し、その後、その安い車の代わりにもう少し良い車を購入しました。彼は少しずつ人生を築き上げましたが、その一つ一つがこことあそこの間のくさびでした。彼は家に手紙を書きました。最初は月に2回、その後は毎月、そして季節の変わり目にも手紙を書きました。家族は返答の中で、お金を本国に送金する計画やお金を取りに来る計画について最新情報を尋ねることはなかった。ヨークの新しい生活、どうですか? エスタモス・ウン・ポコ・セローソス。ジャジャ。テ・アマモス。
彼は秋のキャンプ旅行の直後にリリアナに出会った。彼、ユ・フェ、そしてイスラムは町に戻ってきて、パブで夕食をとるために車を止めた。彼らはジャケットとパンツにキャンプファイヤーの匂いを焼き付けながら店に入り、バーに座った。バーテンダーは眉を上げて強い香りを認め、ビールのボトルの蓋を外した。マニオクさんの左側には、ビールの入ったグラスが泡立っており、その上にはコースターが置かれていて、場所を確保していた。
「さすがです」リリアナはバスルームから戻りながら言いました。「キャンプをしていたと思います。そうでなければ、あなたはカルトと毎週のたき火から逃れてきたばかりだと思います。」彼女はレッド・ウィング社のレザー製のハイブーツを履いており、ネイビーのコーデュロイのオーバーオールを履き、金色の長いイヤリングを鎖かたびらのようなもので首筋に当てていた。彼女は両肘を大きく広げてバーの曲面に寄りかかり、ビールからコースターを外し、ゆっくりと飲んだ。「みんなどこに行ってたの?」
「ウッドランド・バレー」とマニオクは答え、自分のビールを飲む前に立ち止まって彼女に微笑みかけた。“スライドマウンテンの近く。”
"美しい。" 彼女は頭をうなずき、彼の向こうにあるバーを見下ろすために身をかがめました。「これがあなたの友達ですか?」
彼は、ビールを上げあごを傾けてからテレビのサッカーの試合に注意を戻すユ・フェとイスラムを紹介した。「私たちはここの学校に通っています。」
"貴重。ねえ、私たちはいつも学校にいると思わない?」リリアナは、ちょっとしたことで哲学的になる傾向がありました。それはマニオクの不意を突いた。「中退しましたが、たくさんのことを学んでいます。これまで以上に。"
「うーん。もっと言って。" 彼はオーバーオールについてもっと考えながら、これに合わせて遊びました。むしろ、ファッションとしてオーバーオールを着る勇気のある人についてそれが何を言っているのかを考えました。彼女のブーツのつま先は擦り切れた。何から?そして彼女は香水ではなく、クローブとコショウの入ったスパイシーなオーデコロンをつけていました。
「この1年、私は手だけしか見たことのない短編映画のために、風景を描いたり、帆を縫ったり、花を持ったりしてきました。つい先週、妹が私にスティックの運転を教えてくれました。」彼女はビールを飲み干し、バーテンダーに別のビールを注ぐよう合図した。「しばらくワイナリーでブドウを潰していましたが、確かに、それだけではワインに飽きてしまいました。」
「あなたは――英語で何と言うか――貿易商ですか?」
「あらゆる商売において。 もしかしたら、少なくとも少しはそうかもしれない。それは公正です。" 彼女は長く考え込んで息を吐き出した。「あなたの訛りが気になったのですが」と彼女は笑いながら言った。「ごめんなさい、想像したくなかったのです。ここには、どのくらいの期間いますか?"
"3年。私の名前はマニオクです。コロンビア出身です。」
リリアナは、注ぎたてのビールで冷たい汗をかいた手を伸ばした。しかし、彼女の握力は昨夜の火のように暖かかったとマニオクは気づいた。「リリアナ。もともとアイオワ州出身です。」
「アイオワ?それはどこですか?"
彼女は目を丸くしてビールの方を振り返った。「国の真ん中にある。大丈夫、それは誰にも分からない。それはあまり問題ではありません。」彼女はバースツールにもたれて足を組み、太ももに指をピアノのように当てて弾いた。「私たちは今ここにいるんですよね?」
他の部屋を歩き回りながら、リリアナは状況に気づきました。ベッドは洗濯されているように見えましたが、整えられておらず、シーツがタンブルウィードのように片側に束ねられていました。バスルームのトイレを流すと、露出した配管がシャッターを閉めてしまいました。マニオクは小さな2番目の寝室を客室からオフィスに改造し、ツインベッドの代わりに長くて美しいクルミ材の机を置き、その上に数枚の法定パッド、数本のペン、そしてコーヒーで汚れた『モンテ・クリスト伯』のコピーを置いた。彼女は机の上を指でなぞり、その仕上がりに感嘆した。彼女は息を吹きかけて爪の下の埃を吹き飛ばした。
このような手がかりをどう考えるべきか、彼女は心の中で考えました。
彼女が瓶の部屋に戻ると、マニオクは起き上がって、棚の間をあてもなく瓶を移動させ、目立った利益もなく場所を交換していた。天窓が暗くなった。脱穀された羊毛のように、夕方の雨のために雲が集まってきました。
「なぜ彼らが来たのか分かりません。」マニオクは、エンボス加工された会社のロゴが外側を向くように瓶を回転させました。
リリアナは親指でサスペンダーを引っ張り、ショーツのポケットに手を突っ込んだ。「瓶のことですか?」
「いいえ、ガチョウ。雲。" 彼は天井を指差し、部屋中をランダムに指を振りました。「足元にあるジャム瓶に至るまで、これらすべてがどこから来たのか知っています。」彼らは床に置かれた古い果物箱を一緒に眺めました。そこにはまだステッカーが貼られたままの瓶がびっしりと詰め込まれていました。ボイセンベリー、カプリオットファームズ、砂糖を加えていないイチゴのジャム、ウェルチズ、マンゴーチリサプライズ。
「あなたの寝室に飾ってある写真を見ました。海の写真です。あれはオレゴン州だったのか?」
「そうでしたね。」
「あなたに手を振っていたのは誰ですか?
マニオクは眉間にしわを寄せ、振り向いて、ついに彼女と目を合わせた。「私に手を振ってますか?」
「彼らは水の数メートルのところに立っていて、膝から上は濡れていました。彼らはぶかぶかのTシャツを着ていて、大きな黒い髪をしていました。彼らは振り向いて、まるであなたのことを知っているかのように手を振っていました。」
マニオクは首を振った。「フォトボマー」。彼は下唇を噛み、妻に向かって歩き、ちょうど1フィート離れて向かい合って立ちました。リリアナはポケットの内側をぎゅっと握りこぶしにした。ゆっくりと、優しく、マニオクは外側から彼女の拳に手を置き、彼女の骨の関節が彼の手のひらを突いた。彼は息を吸い、そしてまた息を吸い、それから猿ぐつわを噛んで鳴き声を上げました。それは良い、重い叫び声の始まりでした。羊毛状の雲が上空に集まり続け、天窓に降り注ぎ始め、ドーム型のプラスチックの上ではその水滴は聞こえなかった。
"何してたの?" マニオクはなんとか尋ねた。"あなたはどこにいた?"
「場所はたくさんあるよ、マニー」リリアナは暗く冷静だった。ストイックでもある。彼女はパートナーをまっすぐに見つめた。「さあ、聞いてください、ハブたち。これから私が言うことを聞いてください。
「私は長い間行ってしまいました。それが何であれ、夕食を温めた後、電子レンジに放置したその瞬間。たくさん見てきました。おそらく、峡谷、詐欺師、燃え上がる松林など、あまりにも多くのことが起こります。死。生まれたばかりの赤ちゃんは母親のおっぱいに吸い込まれています。」彼女の呼吸のペースが速くなった。「子供が落雷で亡くなり、その後、私はほとんど破産してしまいました。3年後、私はそれを描いた絵を売りましたが、それは非常に意地悪な女性にまったく役に立たなかったのです。私はやると言ったことはすべてやりました。しかし、私が家に帰ってきたのは、そのすべてにおいて、私には何かが欠けていたからです。あなただけではなく、何かが欠けていたからです。主は、それがこれらの壺ではなかったことを知っています。こんなにたくさんの瓶を持っているとは知りませんでした。」
マニオクは顔をしかめた。彼は顎を食いしばって、体を安定させようとした。「あなたは私の家族を訪問しました。」
"やった。" 彼女はかすかに微笑んだ。「あなたは決して行きたくなかったのです。」
"それは真実ではない。実際には存在しない壁をよじ登って立ち往生したことはありませんか?」
「何か障害があるはずだ。何かが起こったに違いありません。素敵ですね。彼らはあなたのことで混乱していて、とても心配しています。」
「彼らはキャッサバにちなんで私に名前を付けました」と彼は言いました。
「子供っぽくならないでください。」しぶきが雨に変わりました。リリアナはマニオクの頭を両手で抱え、耳を押さえながら天窓を見上げた。「これまでずっとオレゴンにしか行ったことがないんです。ユ・フェとイスラムはどうですか?」
「大丈夫だと思います。しばらく彼らから連絡がありませんでした。」マニオクは恥ずかしさで顔を赤らめながら泣き続け、窒息し続けた。
「あなたは愚か者です、それを知っていますか?どうしたの?」彼女は夫の頭を放し、くるりと回転し、瓶詰め室と台所の間の通路の枠に立ち、腕を上げて、まるで剥がして作り直す準備をしているかのようにトリムを握りしめた。「私も様子を見に戻ってきました。」
マニオクは険しくなった。「あなたにはいつも良心がありました。」
「それは私が見続けている夢です。それはあなたのことだと思います。小さな子供と森が見えます。彼は彼らに遭遇する準備をするたびに同じことを言います、そして彼がそれを言うとき、彼は私たちが会ったときと同じわずかなアクセントを持っています。」
"彼はなんと言ったの?"
「彼はそれを言わない、叫ぶだけだ。「私たちは無限であり、つま先の汚れを知っています。」そして彼は笑いながら森の中へ走っていきました。そして、すべてが白、緑、オレンジに変わります。あなたの家族の家、それはその色です。ファサード全体、木工品、その他すべて。」彼女のグリップの圧力でトリムがうめき声を上げた。「そして雨が降り始めて目が覚める。」
「今、雨が降っているようです。」
「今、雨が降っているようです。」
マニオクは、発作が治まり始めていたので、背が高くスリムなミッションスタイルのキャビネットに歩み寄った。彼はドアをカチッと開けて中に手を入れ、土が詰まった無地のパイントサイズのメイソンジャーを取り出した。彼は妻の突き出た腰と伸ばした腕の周りを歩き回り、握力で静脈が皮膚を突き抜けて浮き出た。マニオクは瓶を開けて土の匂いを嗅ぎ、それをリリアナの鼻にかざした。
「キノコや野生のミントのような匂いがするのは不思議ですね。」
「家の裏の森にある野生のミント畑から」とマニオクは肩を沈めながら言った。
リリアナは腕をトリムから下ろした。空に溜まった洪水が雨を降らせ、低く果てしない音を立てて家を濡らした。「素敵な匂いがするよ。」
「土のせい?それとも雨のせい?」
「中から雨の匂いがする?」
「どこに行ってもペトリコールの香りが漂います。」彼はなんとかウインクすることができた。リリアナは首を振って笑いました。「とにかく、これが私が満杯にしておく唯一の瓶です。他のものはすべて空にします。きっと気づいていたと思いますよ。」
「健康的ではありません、マニー、物事を避けるのは。」彼女は彼の肩を掴んで振り向かせ、後ろから腕を回した。彼女は彼の頭皮のマストの匂い、何年も前の髭剃り後のムスクの匂いを嗅いだ。彼女は彼の胴体の皮膚の革のような抵抗を感じた。
「自分たちで漬ける方法を見つけられるといつも思っていたんです」とマニオクさんは握り締めた質問に答えた。「特に私とあなたは、すべてをハッキングしてやろうと思っていました。いつも酸っぱくなるものを保存しておこうと思ったのです。」彼はパートナーが応答するのを待ちました。数分が経過し、雨が壁や屋根や天窓を叩きつけました。「待って、リリー?あなたは――鼻をすすっていないのですか?」
「ハブはいつも話題を変えますね。」彼女は腕を後ろに引き、手の甲で目を拭った。「毎度毎度。あなたは私に何も変わらないと思わせています。」
マニオクは瓶を鼻に引き寄せ、再び匂いを嗅いだ。彼はそれを下ろし、指の間に少しの土を取り込むために手を入れ、まるでそれが話したり啓示を呼び起こしたりするかのようにそれをこすった。「先ほど言ったことを繰り返しますが、おそらく私たちはそれほど変わっていないのです。あまり。"
「あなたの家族がいなくて寂しいです。」リリアナはマニオクの胸の下で指を組みました。「彼らが本当に気に入りました。なぜ私は彼らに会いに行ったのに、あなたは会わなかったのですか?彼らが会いたい。"
"もちろん。そしてあなたに会えなくて寂しい。" マニオクは瓶の蓋をねじ込み、手で握り、天窓に当たる雨のリズムに合わせて瓶の側面を叩きました。「あなたは彼らがいなくて寂しいし、私もあなたがいなくて寂しいです。それについてどう考えますか?
リリアナは笑い出した――生意気で際限なく、土のような濡れた砂利で笑い出した。彼女の笑い声を合図に、瓶の中に隠れていたたくさんのコオロギが鳴き始めた。家は野生の騒音で溢れていました。
「手がかりが足りません、マニー」彼女は笑いが止まらなかった。コオロギの鳴き声と雨が激しくなった。「あれだけの瓶があっても、十分な手がかりはどこにもありません。」

![とにかく、リンクリストとは何ですか?[パート1]](https://post.nghiatu.com/assets/images/m/max/724/1*Xokk6XOjWyIGCBujkJsCzQ.jpeg)